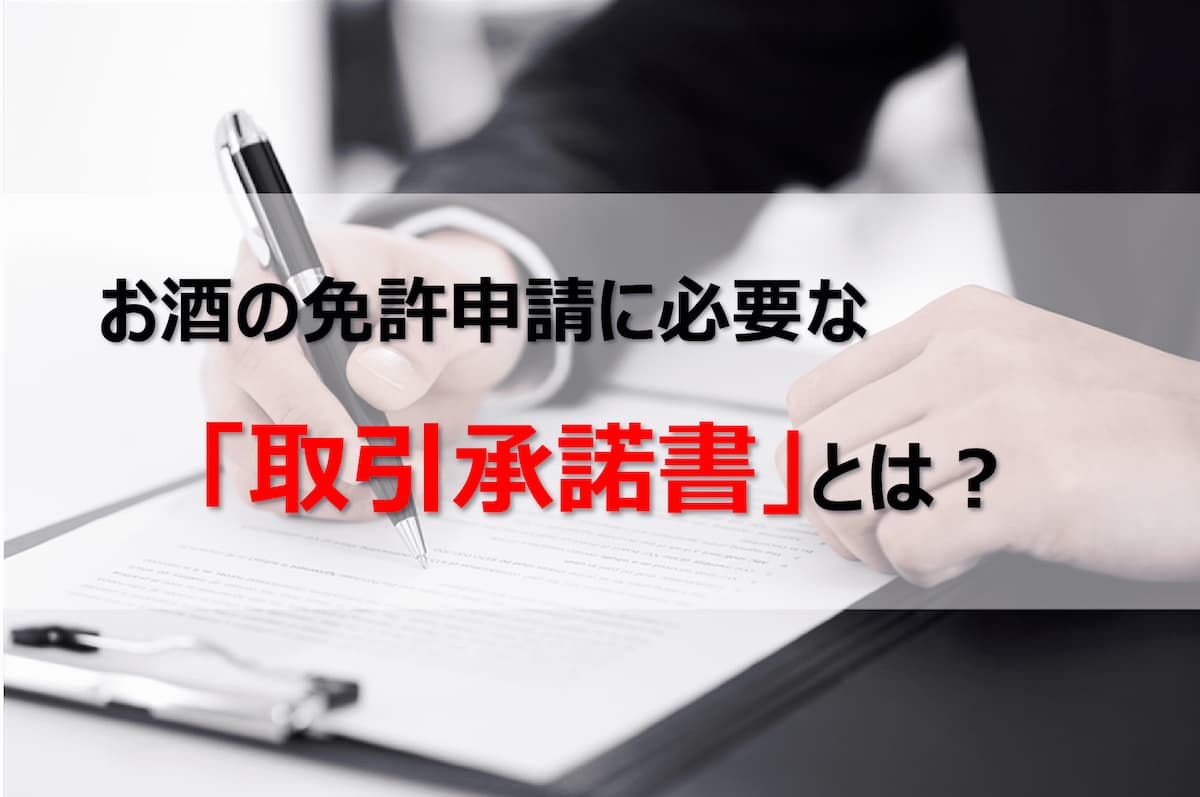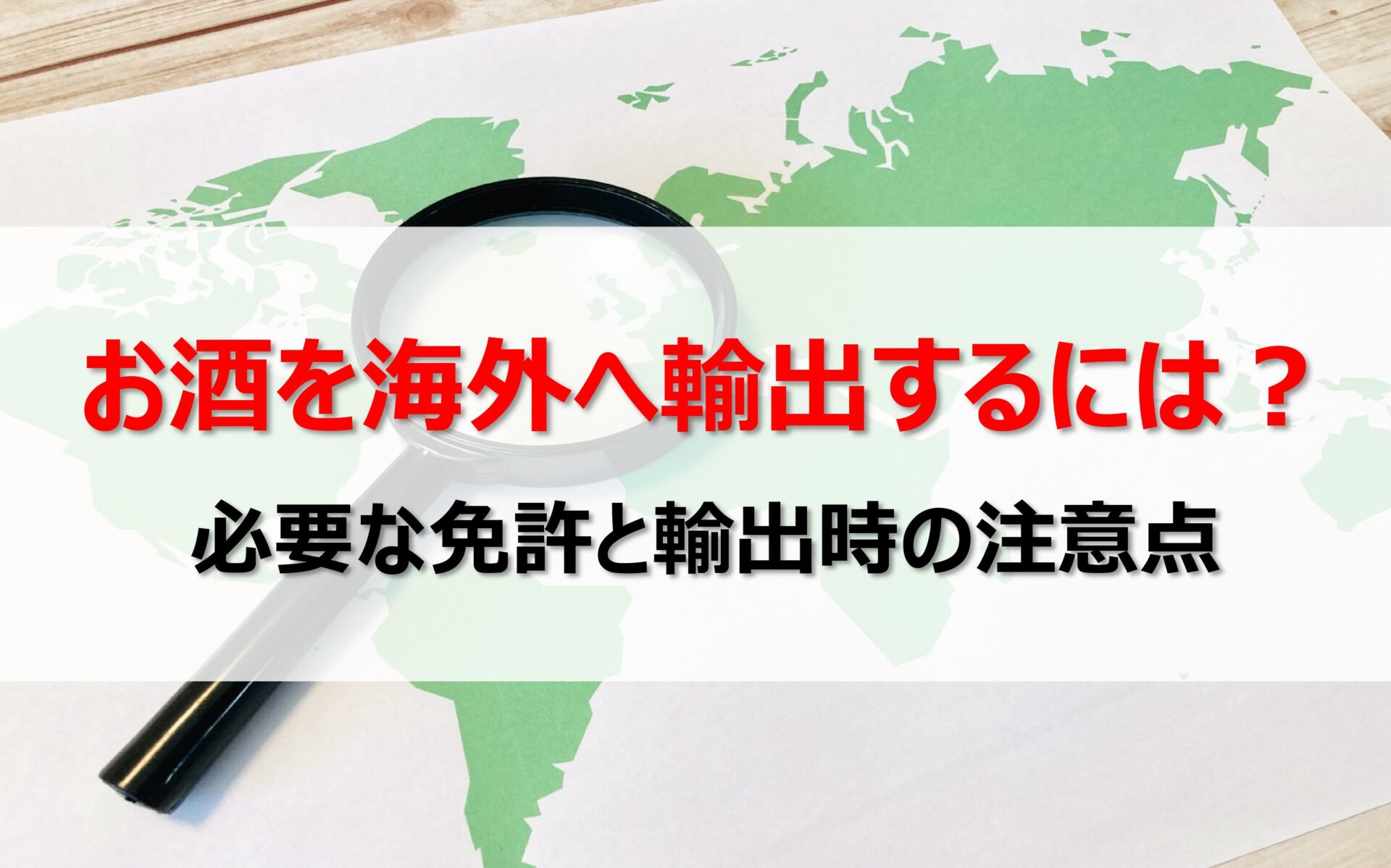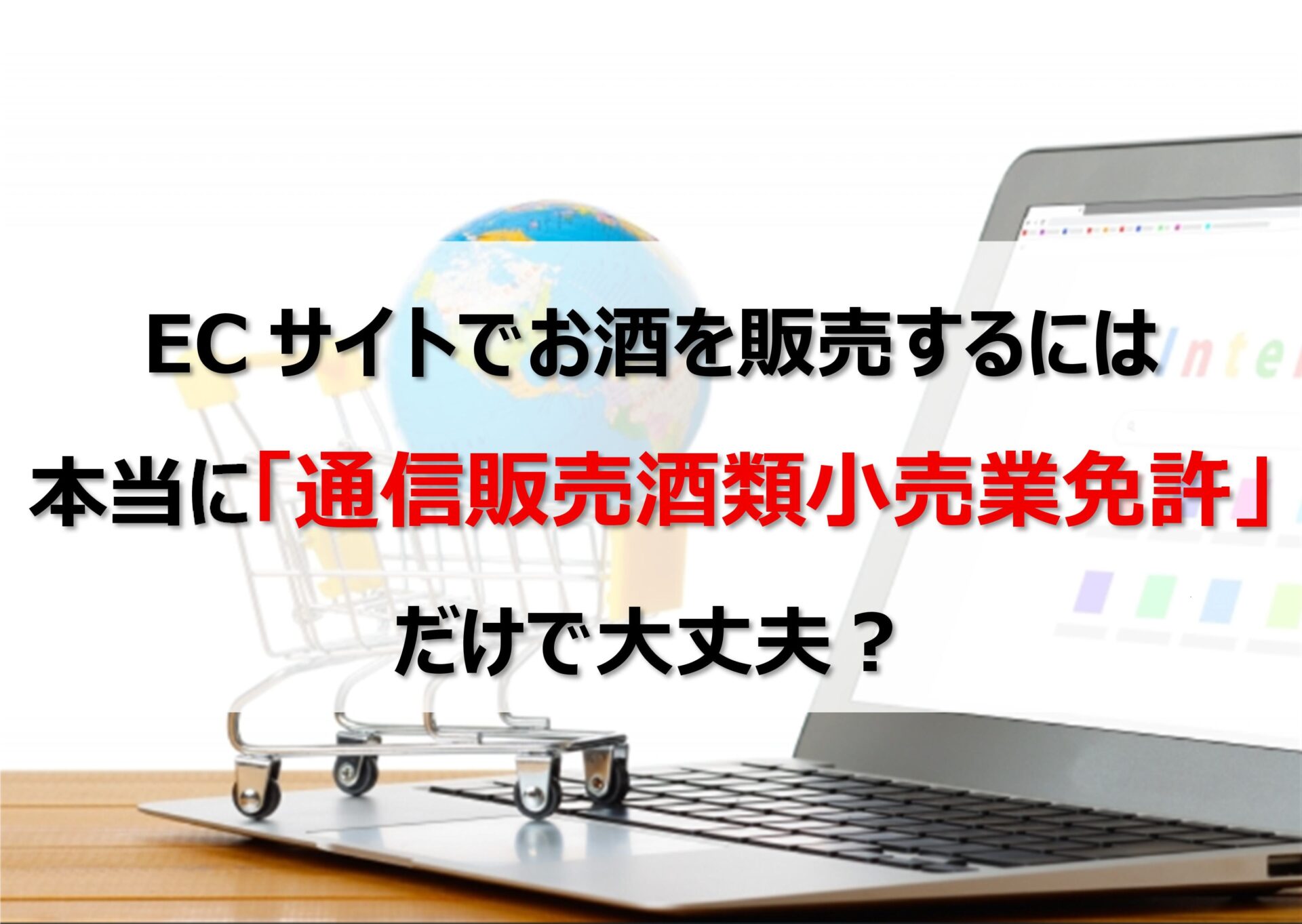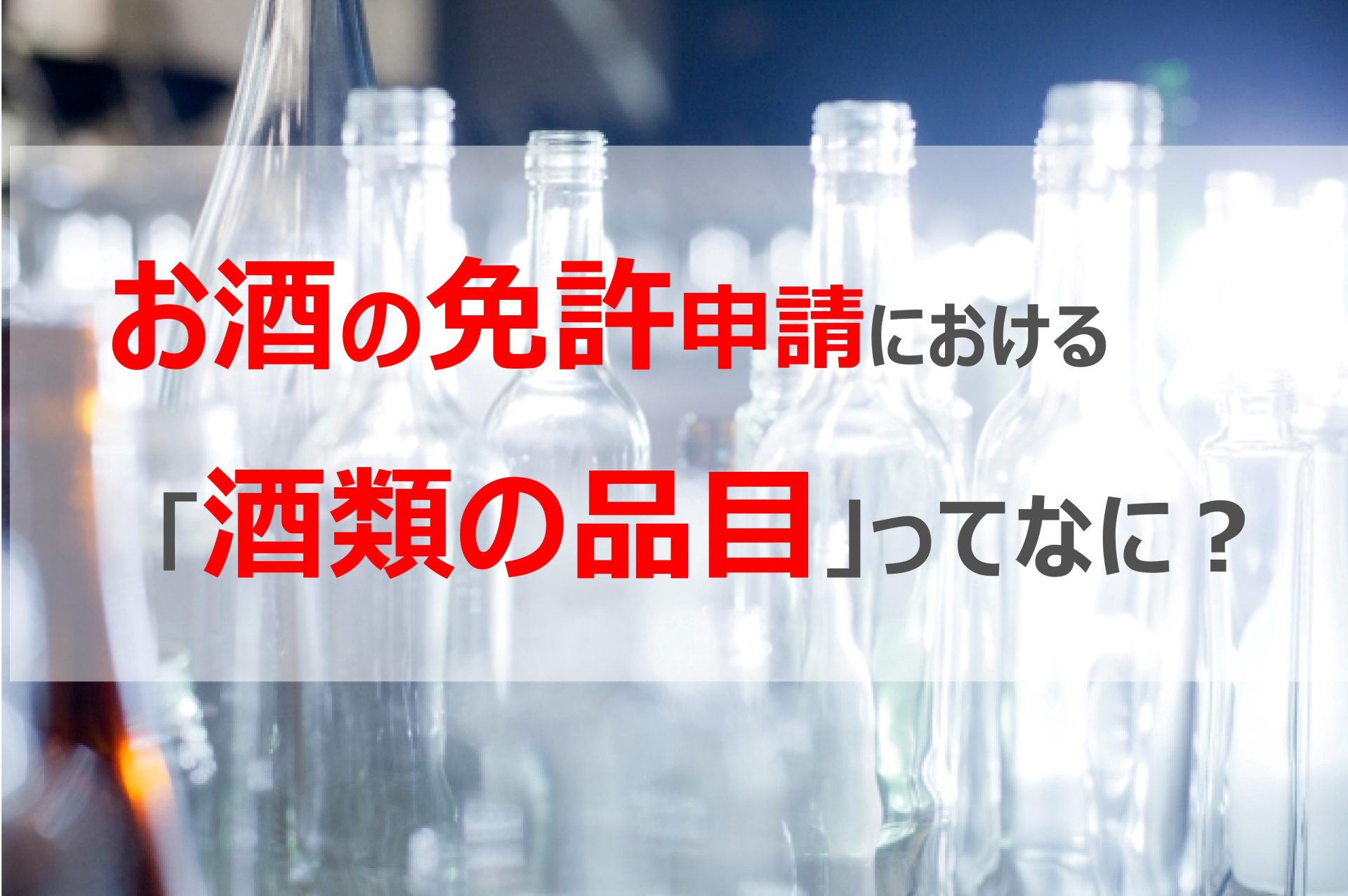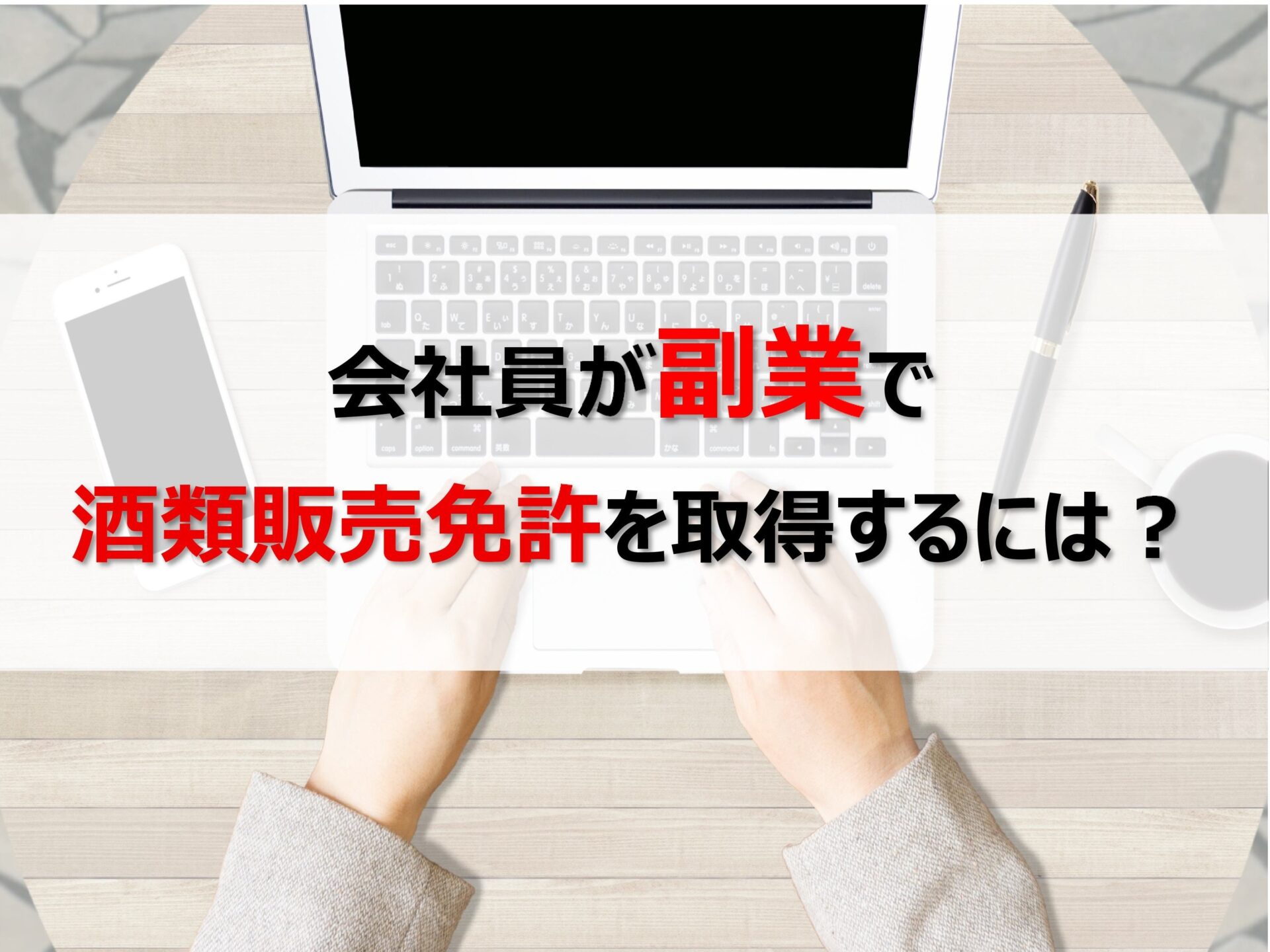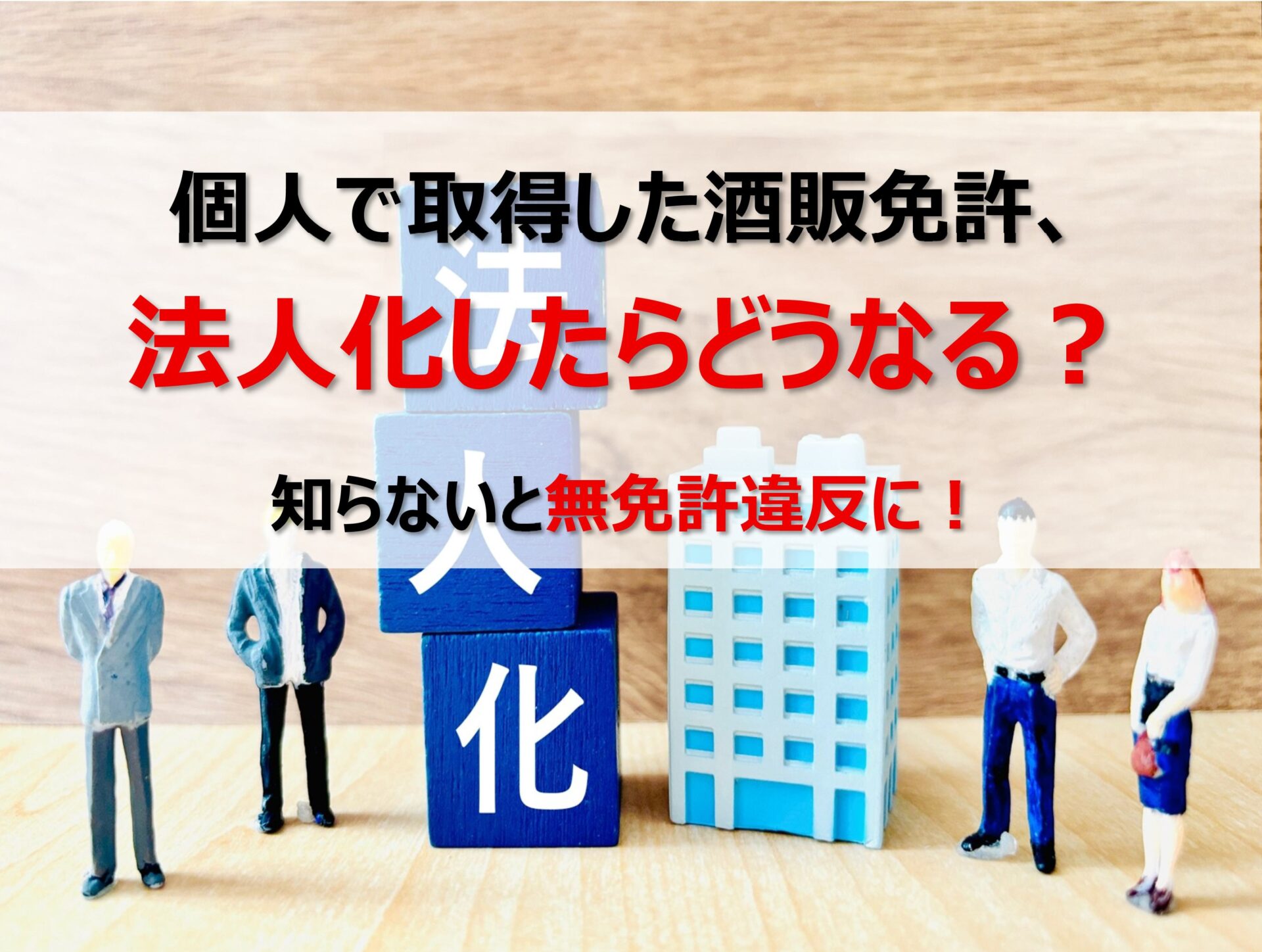輸出入酒類卸売業免許で「海外の取引承諾書」は「誰から」もらえば良い?
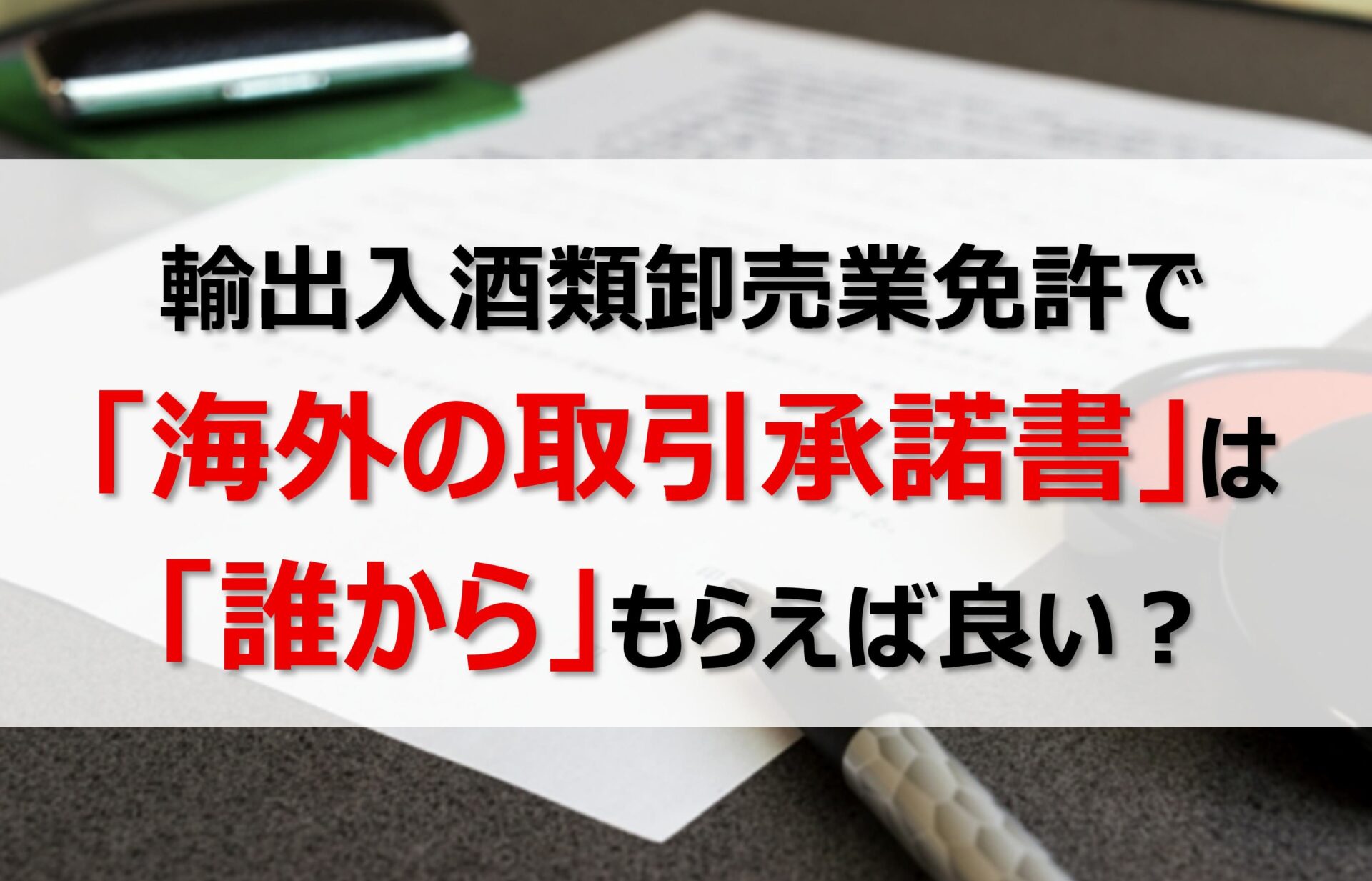
輸出酒類卸売業免許、輸入酒類卸売業免許を取得したい場合、海外の取引先から「取引承諾書」を取得する必要があります。海外に取引先の候補はいるけれど、どんな相手にお願いすればいいのか迷う方もいるのではないでしょうか。
この記事では、海外の取引承諾書を依頼する相手の選び方や注意するポイントについて解説していきます。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
目次
輸出酒類卸売業免許の場合(海外の販売先)
実体のある事業者なら、法人か、個人かについては問われません。また、必ずしも取引承諾書を取得した時点でお酒の取扱いをしている必要はありません。ですが、現在お酒の取扱いをしていない相手の場合は、今後はこれをきっかけにお酒の取扱いを始めてくれる相手であることを税務署に説明できる必要があります。
その他の注意点として、お酒を販売した相手が、その国で必要な販売ライセンスを保有しているかどうかを確認された事例があります。販売先の国における酒類販売に関する法律や規則についても、可能であれば事前に確認しておいたほうがいいでしょう。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
海外の一般消費者からも取引承諾書の取得が必要?
海外のECプラットフォームなどを利用して海外の一般消費者に販売したい場合は、海外の一般消費者から取引承諾書を取得することは現実的に困難ですので、提出は不要です。
相手が一般消費者の場合は、取引承諾書の代わりに「越境EC」であることを説明して申請します。取引承諾書の取得は不要ですが、その代わりに越境ECの事業もくろみや、販売のスキームなどについての説明資料を作成して税務署に説明することになります。
どのような説明資料を作成すれば良いか迷う場合は、管轄の税務署の酒類指導官または専門の行政書士に相談すると良いでしょう。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
輸入酒類卸売業免許の場合(海外の仕入れ先)
輸出酒類卸売業免許の場合と同様に、実体のある事業者であれば法人か、個人かについては問われません。ただし、取引承諾書を取得した先が、例えばワイナリーのように「果実酒」のみを扱っている場合、輸入酒類卸売業免許で取り扱える品目が「果実酒に限る。」などのように、限定されてしまう可能性があります。審査を担当する税務署によっては、酒税法及び通達を踏まえ、実際に予定のある品目に限定して免許を交付したいと考える場合があるためです。
(根拠法令 酒税法第11条、酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達第11条関係 製造免許等の条件 3「販売する酒類の範囲又は販売方法の条件」の取扱い )
免許の内容に制限がかかると、許可された品目以外のお酒は卸売りできません。ワイン以外にも、たとえばウイスキーやブランデー、ビール、スピリッツ、リキュールなど幅広い品目を輸入できるようにしておきたい場合は、複数の品目のお酒を取り扱っている商社などから取得するほうが取り扱える品目に幅があるため、「○○に限る。」といった制限を受けにくくなります。
一方、例えばワイン以外を取り扱う予定はなく取り扱える品目が果実酒のみに制限されても困ることは全くないようなら、限られた品目しか扱っていない事業者から取得しても問題ないことになります。今後の事業展開をどのように考えているかによって、どのような相手から取引承諾書を取得するか考えるのがいいでしょう。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
まとめ
- 事業者であれば法人でも個人事業者でもどちらでもよい
- 【海外販売先】今、お酒の取り扱いをしていなくてもいいけれど今後は取り扱う予定がある相手であることが必要
- 【越境EC】消費者からの取引承諾書を取得する必要はないが代わりに越境ECの説明資料が必要
- 【海外の仕入先】いろんな種類のお酒を扱いたいなら、品目の幅が広い商社などからもらう方が安心
- 今後の事業展開をどのように考えているかによって取得先を決める