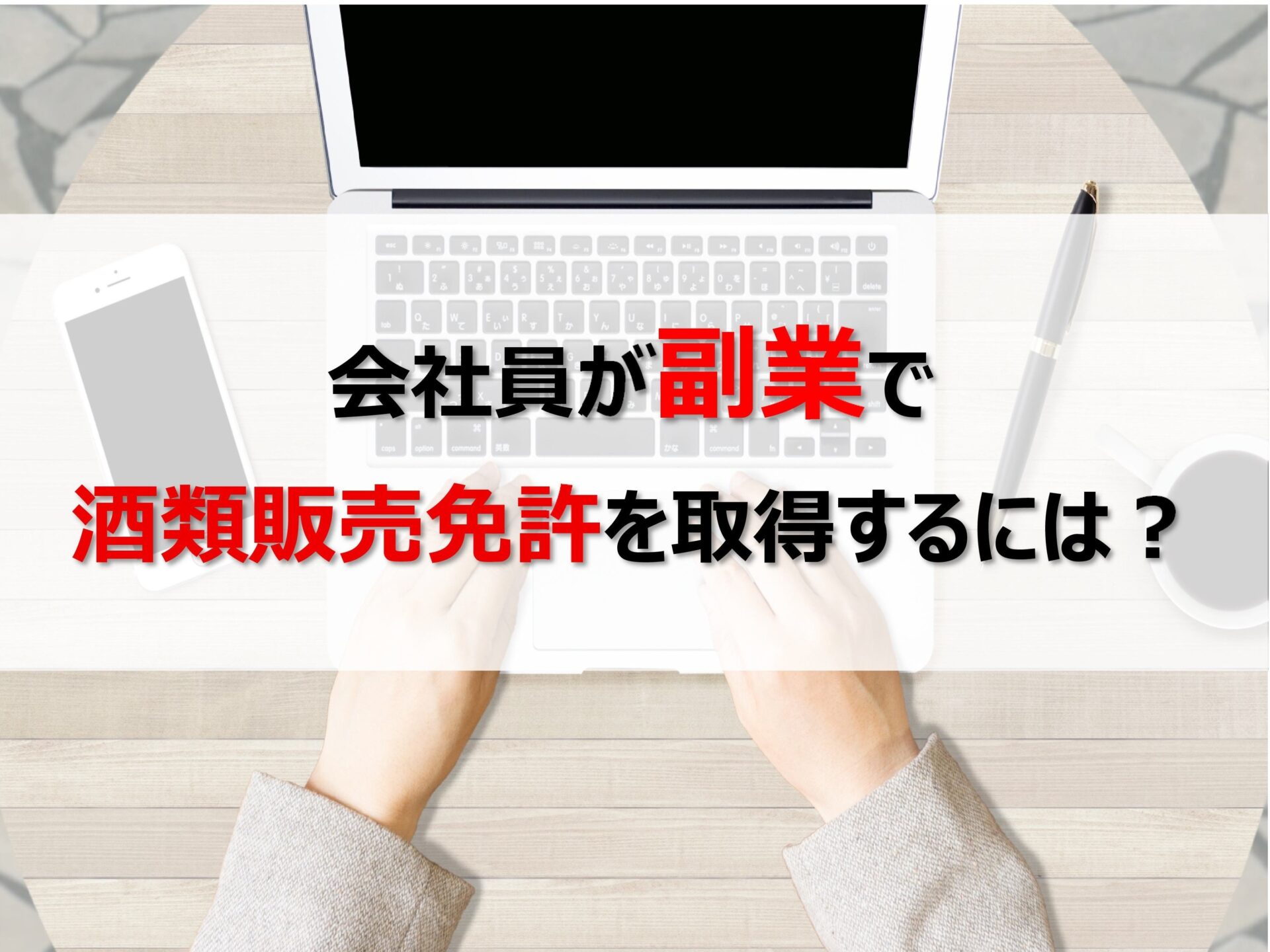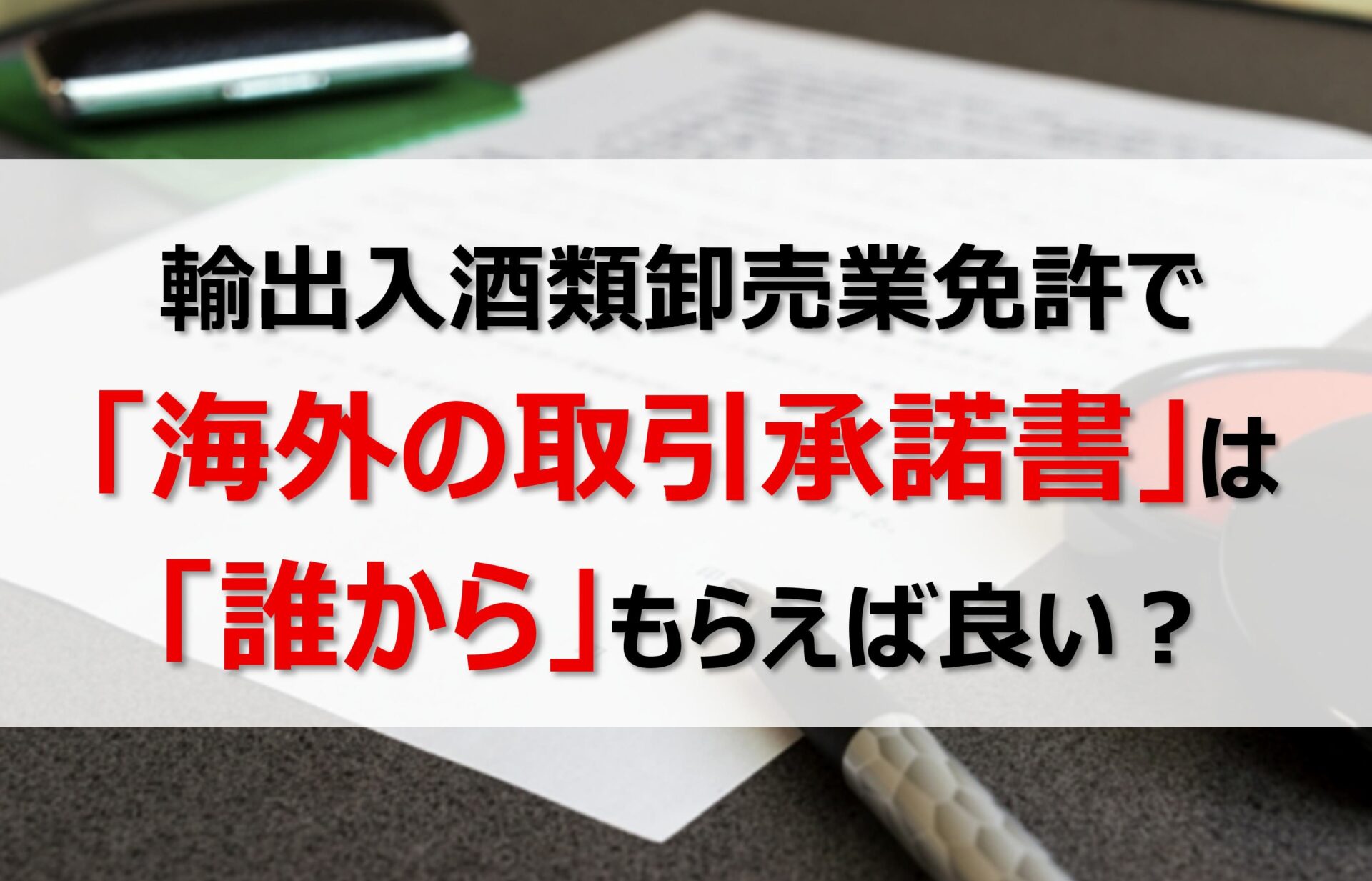個人で取得した酒販免許、法人化したらどうなる?知らないと無免許違反に!
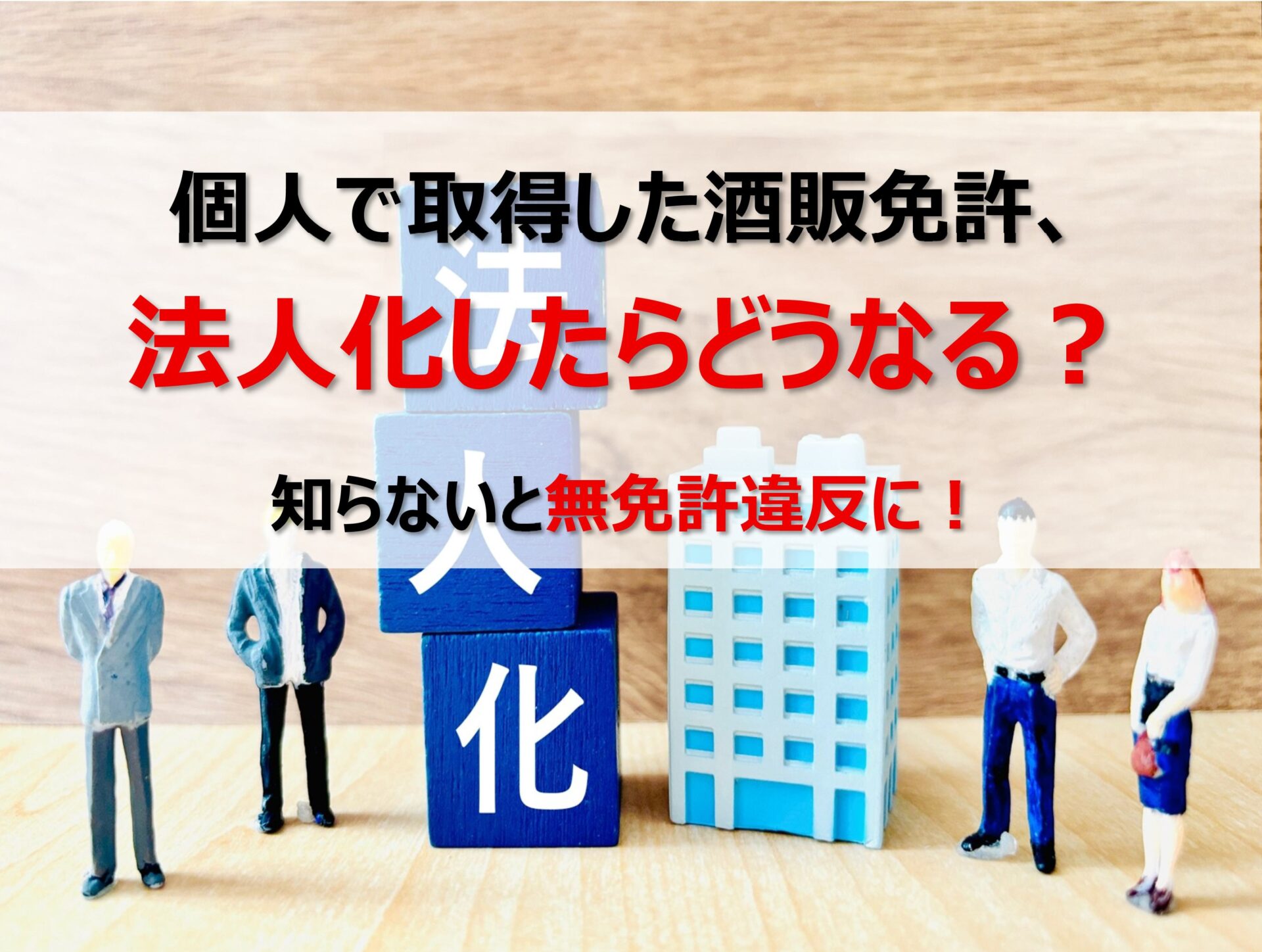
個人事業として酒類販売免許を取得して数年——。事業が軌道に乗り、法人化(法人成り)を検討する人も多いでしょう。しかし、「個人名義の免許のまま販売を続けてもいいの?」「法人に引き継げるの?」と不安に思う方も少なくありません。
実は、そのまま販売を続けてしまうと無免許販売に該当し、罰則の対象となってしまいます。この記事では、法人化にあたって必要な酒販免許の手続きや注意点をわかりやすく解説します。
目次
個人名義のまま販売したら無免許違反になってしまう
酒類販売免許は、「名義」と「販売場」に紐づく免許です。したがって、個人事業主として取得した免許は「個人の名義」と「個人が使用する販売場」に対して有効なものです。法人化した場合、たとえ同じ店舗で販売を続けても、法人は別の人格とみなされるため、新たに免許を取得しなければなりません。
個人名義の免許ままだと無免許販売に該当し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
法人化したらどんな手続きが必要?
法人化にあたっては、個人名義の「酒類販売業取消申請書」と法人名義の「酒類販売業免許申請書」を管轄の税務署へ同時に提出をします。取消申請書を提出したらすぐに取り消されてしまうのではないかと不安になるかもしれませんが、法人の審査が終わるまでは個人名義の免許は有効です。個人名義での販売は継続できますので安心してください。
一定の要件を満たすと「法人成り等」という扱いになり、通常の新規申請に必要な添付書類を一部省略できます。ただし、最終的な判断は所轄の税務署(酒類指導官)によるため、提出書類については事前相談を行うとよいでしょう。
酒類販売業免許申請書「次葉」添付書類
| 新規申請(通常) | 法人成り等 | |
| 次葉1(販売場の敷地の状況) | ○ | ○ |
| 次葉2(建物の配置図) | ○ | ○ |
| 次葉3(事業の概要) | ○ | ▲ |
| 次葉4(収支の見込み) | ○ | ▲ |
| 次葉5(所用資金の額及び調達方法) | ○ | ▲ |
| 次葉6 (酒類の販売管理の方法に関する取組計画書) | ○ | ▲ |
※▲変更がない場合は添付を省略することができる。
法人成りの際の注意点
販売場の使用権限が法人であること
新規申請の際、販売場(店舗)の使用権限を証明する書類が必要です。もし賃貸物件で営業している場合、賃貸借契約書の名義を法人に変更しなければなりません。名義が個人のままだと、法人が販売場を使用していることを証明できず、免許が下りない場合があります。
フランチャイズ(FC)契約の場合は契約名義の変更も必要
フランチャイズ(FC)契約を結んでいる場合、契約主体が個人から法人に変わる際には、フランチャイザーとの契約名義変更も行う必要があります。契約の主体が変わっていないと、税務署から「営業実態が異なる」と判断されるリスクがあります。
既存販売場と同じ場所において営業がなされること
「法人成り等」に該当させるためには、法人化後も、既存販売場と同じ場所で営業を継続することが前提です。別の場所で新たに営業を始める場合は、単なる「法人成り」ではなく、新規販売場としての免許申請が必要になります。
既存販売場が「休業場」でないこと
「法人成り等」に該当させるためには、既存販売場が「休業場(原則1年以上、酒類の販売実績がない販売場)」でないことも条件の一つです。休業状態が長く続いている販売場は、実質的に営業していないと判断されるケースがあります。該当する場合は事前に税務署や専門家に確認するようにしましょう。
審査期間は原則2か月。法人化を考えているなら早めに申請準備を
酒類販売業免許の審査には、原則として2か月程度の期間が必要です。申請が遅れてしまうと、法人化したにも関わらず、法人としては一時的に「酒類のみ」販売できない期間が生じるおそれがあります。そのため、法人として営業を開始したい日から逆算して2か月前までに申請を行うことが重要です。
また、申請時に「法人として営業を開始したい日」を税務署へ伝えておくことで、審査完了後の免許通知日を月初など区切りのよい日付で受けることも可能です。例えば、1月末頃までに法人成り等の申請を行った場合、4月1日から法人としての営業を開始できます。
この場合、3月31日までは個人事業としての販売を継続することになります。法人化を検討中の段階で、まずは税務署または専門の行政書士に相談し、スケジュールを立てておくとよいでしょう。
まとめ
- 個人から法人へと名義が変わる場合は法人名義での免許取得が必要
- 契約関係(賃貸・FCなど)の法人への名義変更が必要
- 「法人成り等」に該当すると審査が一部簡略化できる
- 営業切替日から逆算したスケジュール調整が大事