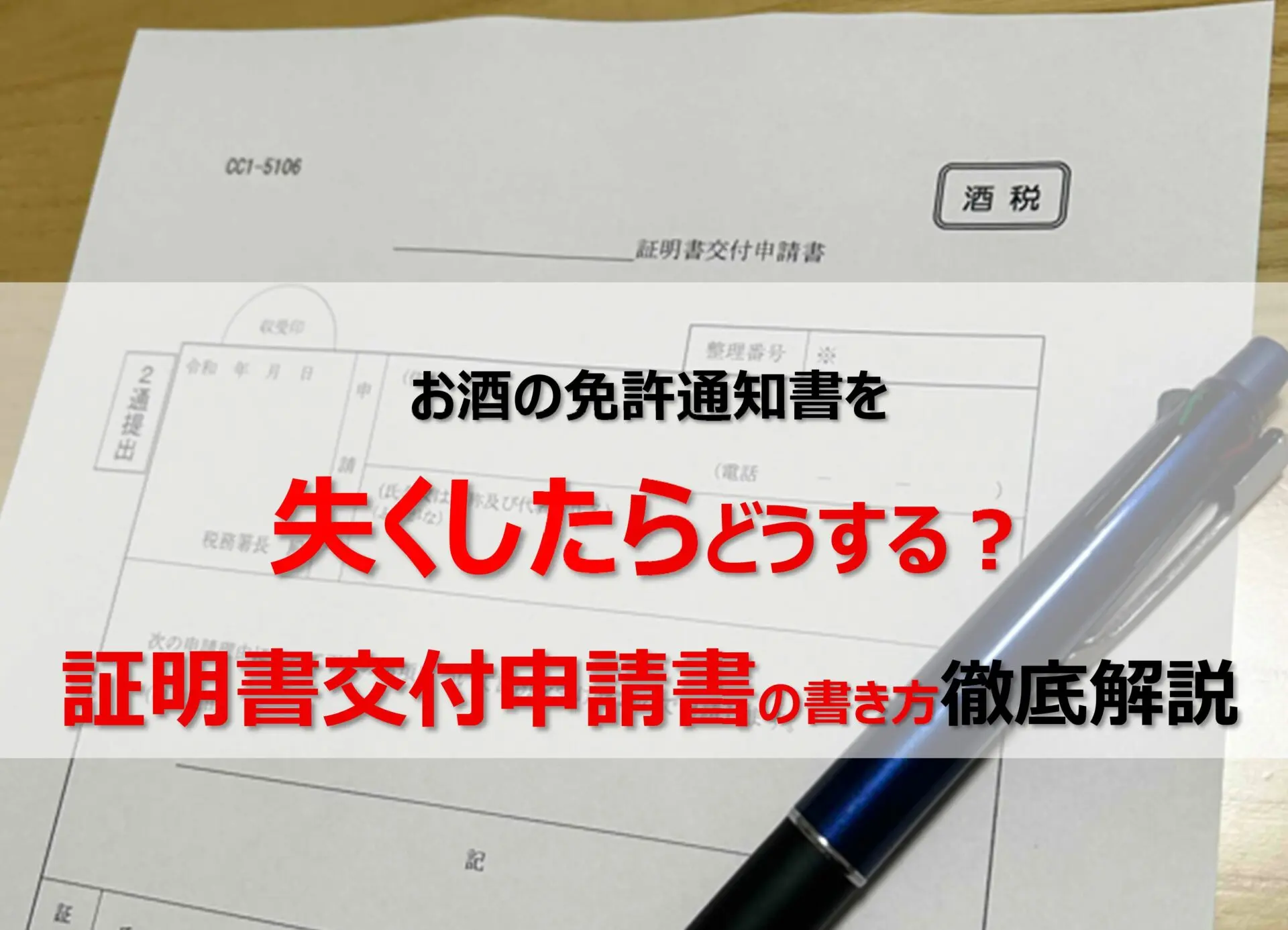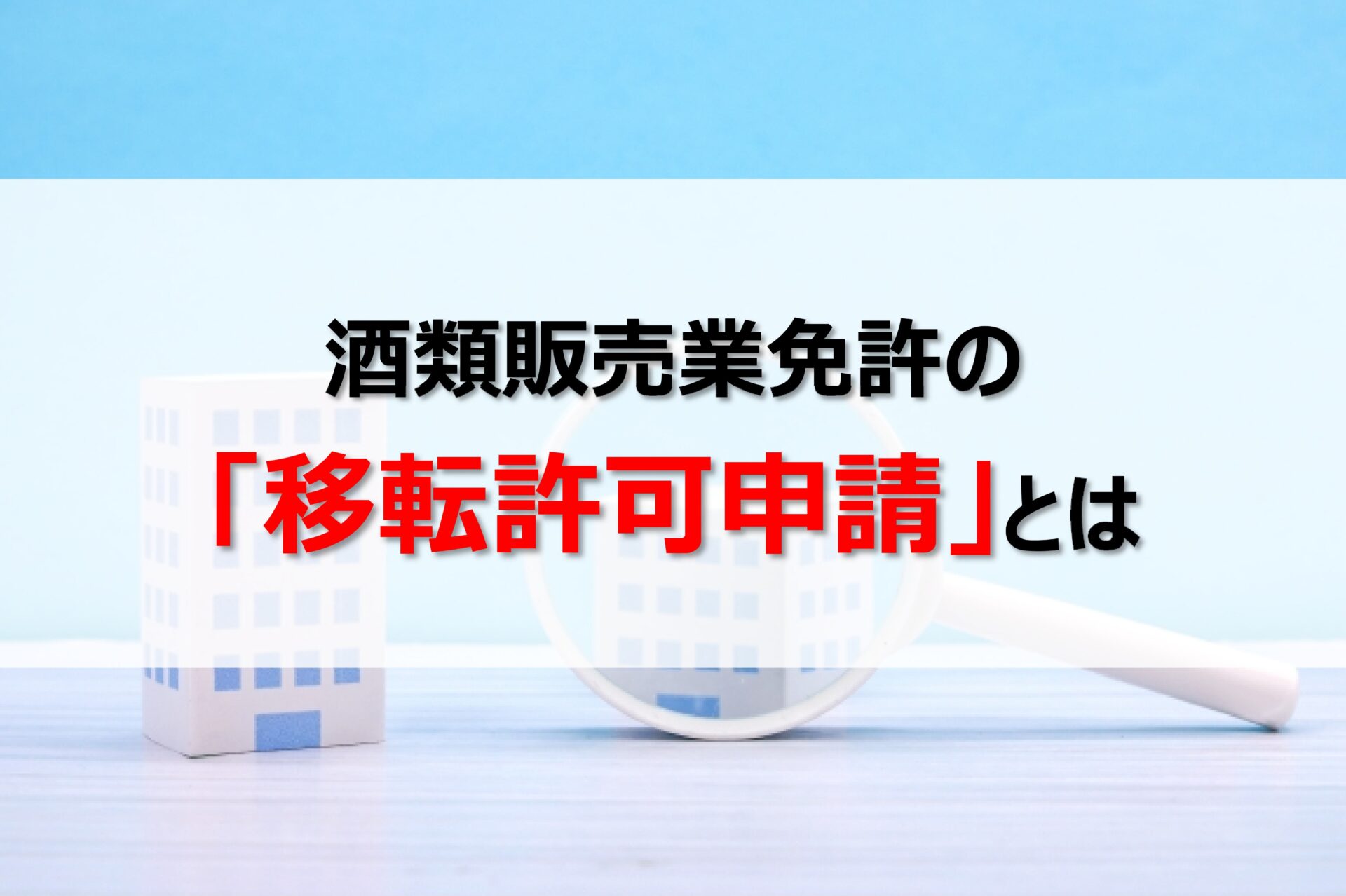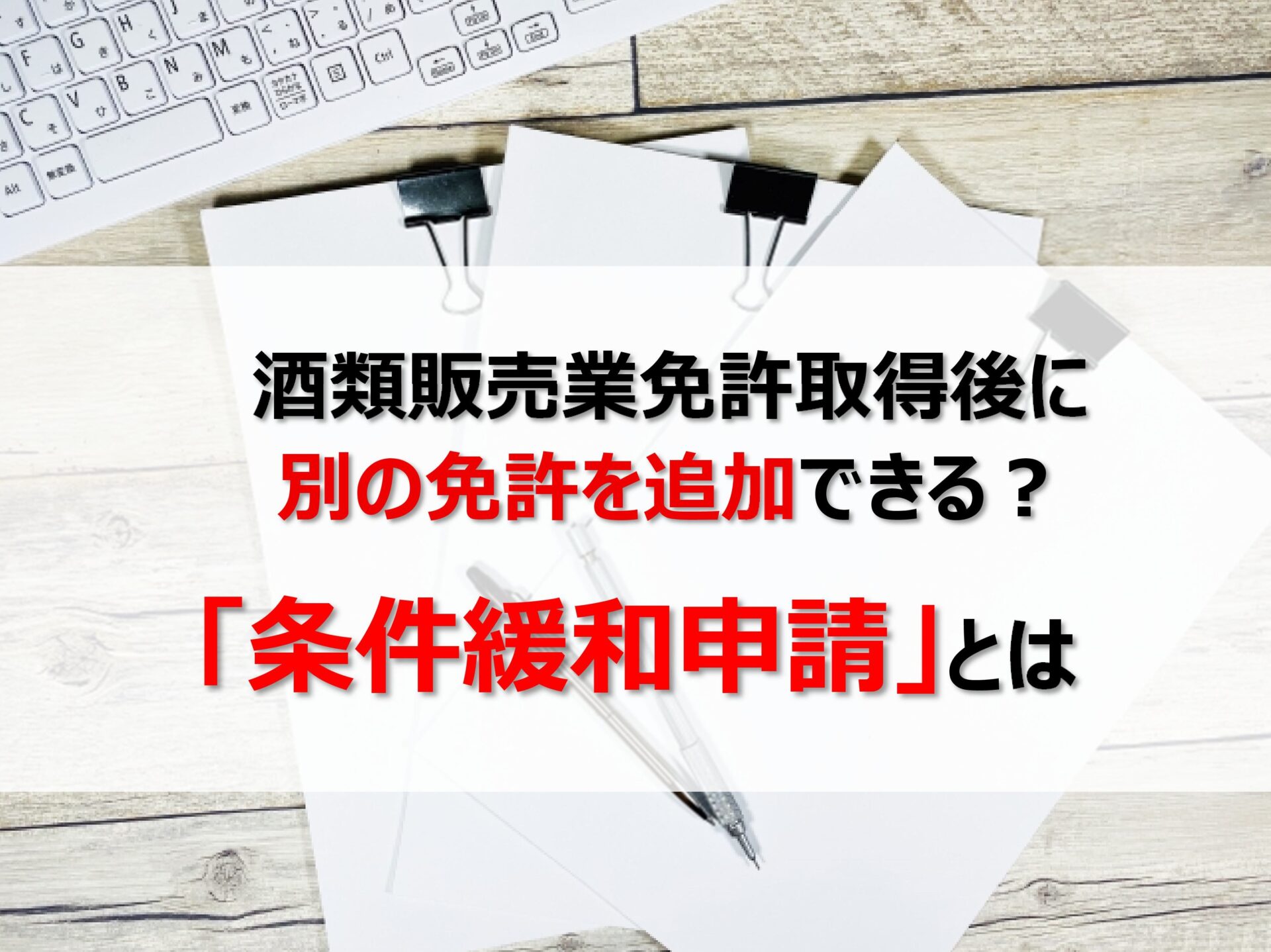酒類販売免許に「免許番号」はある?取引先に求められたらどうする?
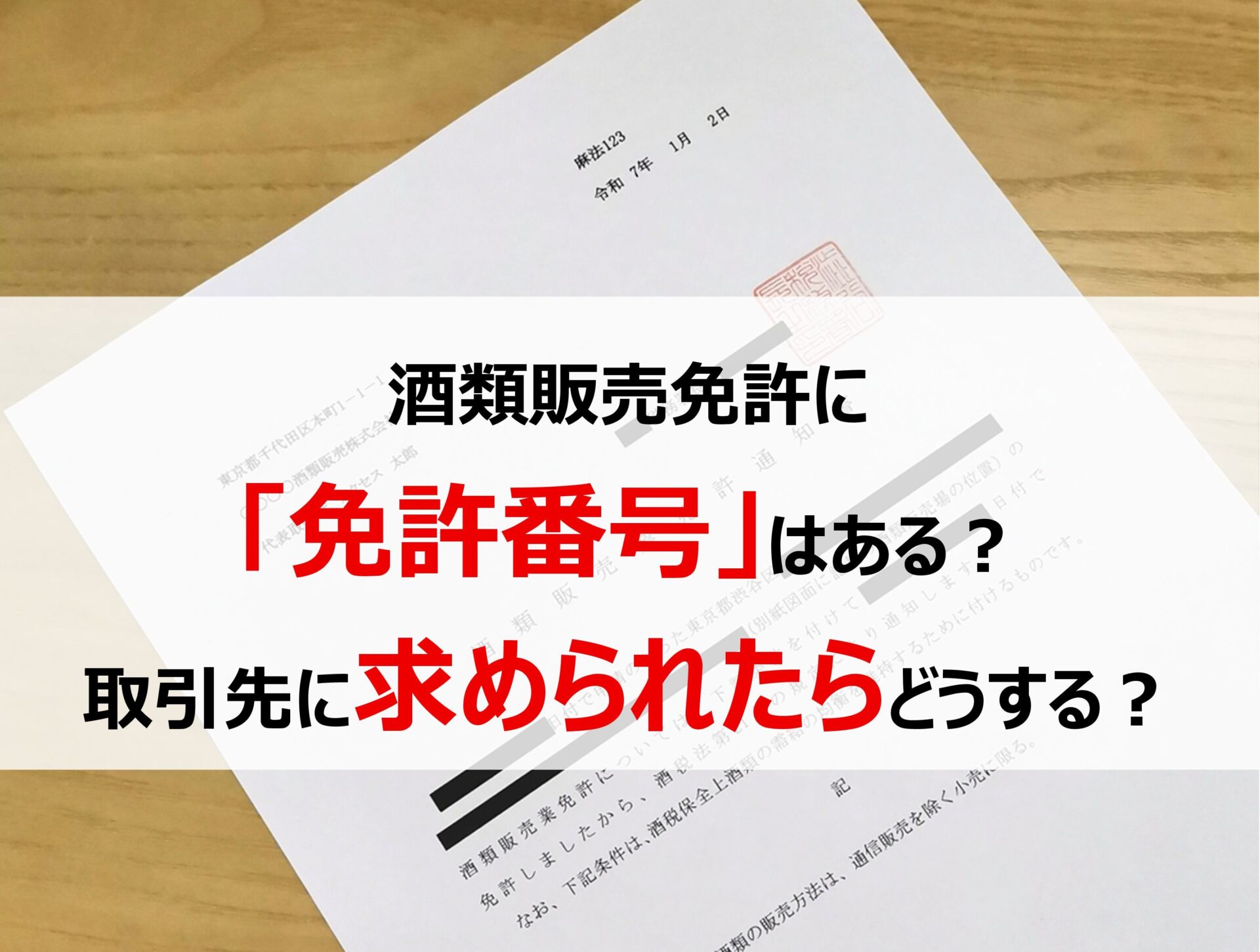
酒類販売免許を取得したあと、取引先やECサイトの登録時に「免許番号を教えてください」と言われて戸惑った経験はありませんか?実は、酒類販売免許には「免許番号」というものは存在しません。
それでも、登録フォームで入力を求められたり、取引先から提出を求められることがあるため、現場では混乱することがあります。この記事では、免許番号を求められる背景や、その際の対応方法について、実務の視点から分かりやすく解説します。
目次
酒類販売免許に免許番号はない
建設業や宅建業、古物商など、多くの許認可では「免許番号」が割り当てられますが、酒類販売業免許は免許番号が割り当てられません。つまり、免許番号は存在しません。税務署から発行される免許通知書そのものが免許の証明になります。
取引先から免許番号を求められる理由
取引先やECサイトの登録フォームなどで「免許番号」の入力を求められるケースがあります。それには次のような背景が考えられます。
・他業種の許認可のように「免許番号があるはず」との思い込み
・通知書右上の「京法第123号」「麻酒第45号」などを免許番号と勘違いしている
・何かしら番号をもらっておいた方が安心
しかし、酒類販売業免許通知書の番号は税務署内での書類管理番号であり、免許情報とは直接紐づいていないため、実はあまり意味がない番号というのが本当のところです。
求められた場合の対応
もしECサイト出店や取引先登録などで番号入力が必須の場合は、免許通知書右上の管理番号をそのまま記入すると良いでしょう。
「免許番号は存在しません」と取引先に一生懸命説明しても相手が混乱するだけで、手続きが円滑に進まなくなってしまう可能性があります。実務上は、取引先が納得すればそれで良いと思いますので、スムーズに進むことを優先するのが現実的です。

条件緩和通知書や移転許可通知書を持っている場合
最初に免許を取得したときは「酒類販売業免許通知書」ですが、その後、販売品目の追加などで条件緩和を行った場合は「条件緩和通知書」が発行されます。
この場合、条件緩和通知書が最新の免許条件を示していますので、取引先に提出する際は条件緩和通知書の情報をもとに対応するのが望ましいでしょう。
また、販売場を移転したことがあると、「移転許可通知書」が交付されます。移転許可通知書に最新の販売場の住所が記載されていますので、移転も、条件緩和もしたことがある場合など、判断に迷う場合は、取引先に確認をすると良いと思います。
相手の免許を確認したい場合の正しい方法
はじめてお酒の取引する相手の免許を確認する場合は、免許通知書のコピーの提示を求めるのが基本です。免許通知書には、業種区分(小売・卸売など)や取扱品目、販売場の所在地などの詳細が記載されており、内容を確認することで、取引先として問題ないかを判断できます。
上記の通り、取引先から免許番号の提示を求められた場合は、柔軟に対応するのが現実的です。相手が安心し、取引が円滑に進むことを優先する。それでよいと思います。
まとめ
・酒類販売免許には「免許番号」はない
・通知書右上の「京法第○号」などは税務署内の書類の管理番号であり、免許情報とはリンクしていない
・取引先から番号入力を求められたら、免許通知書右上の管理番号を記入して対応する他ない
・条件緩和している場合は、条件緩和通知書が最新の免許条件
・相手の免許を確認する際は、免許通知書のコピーを確認するのが基本