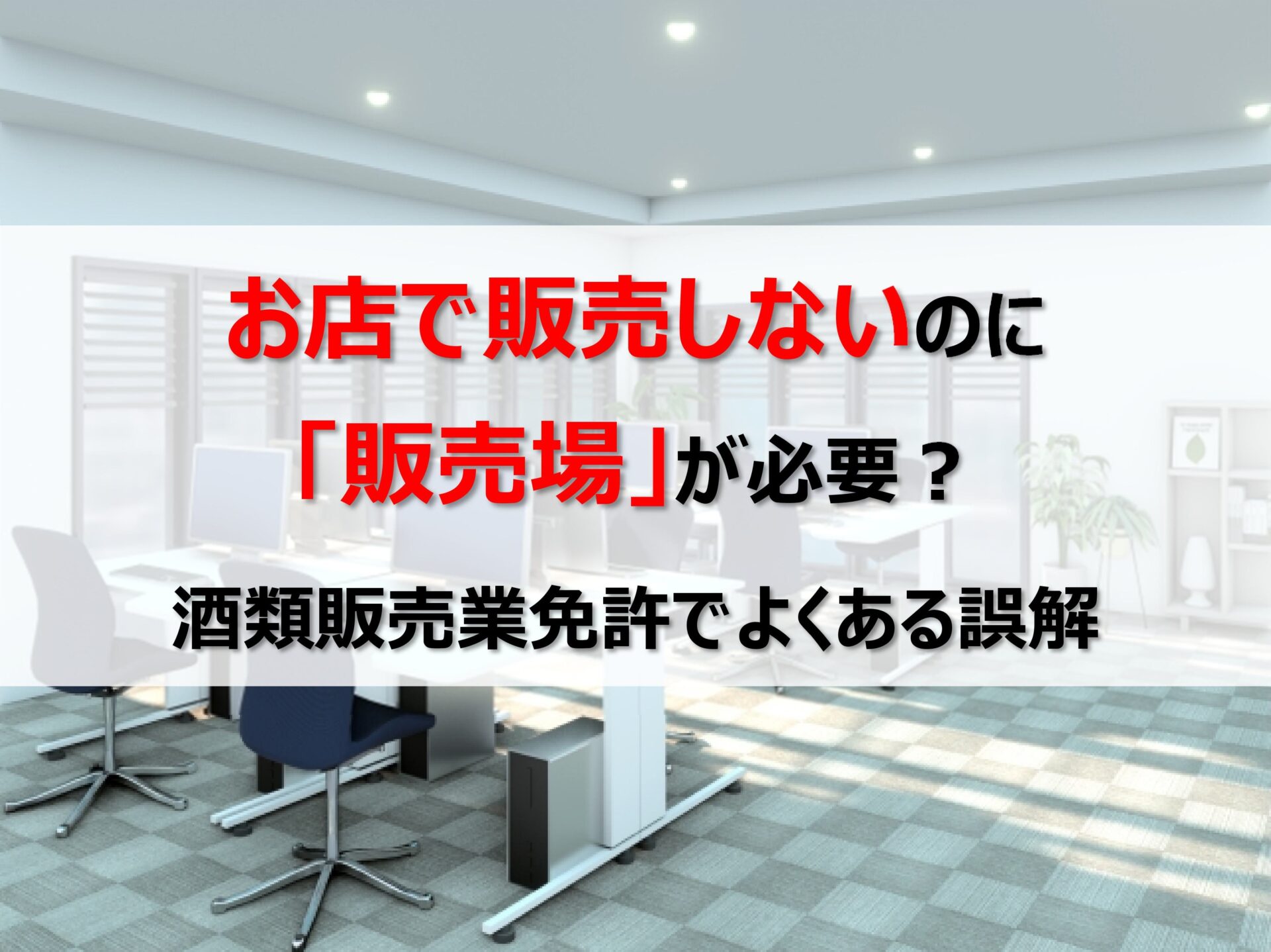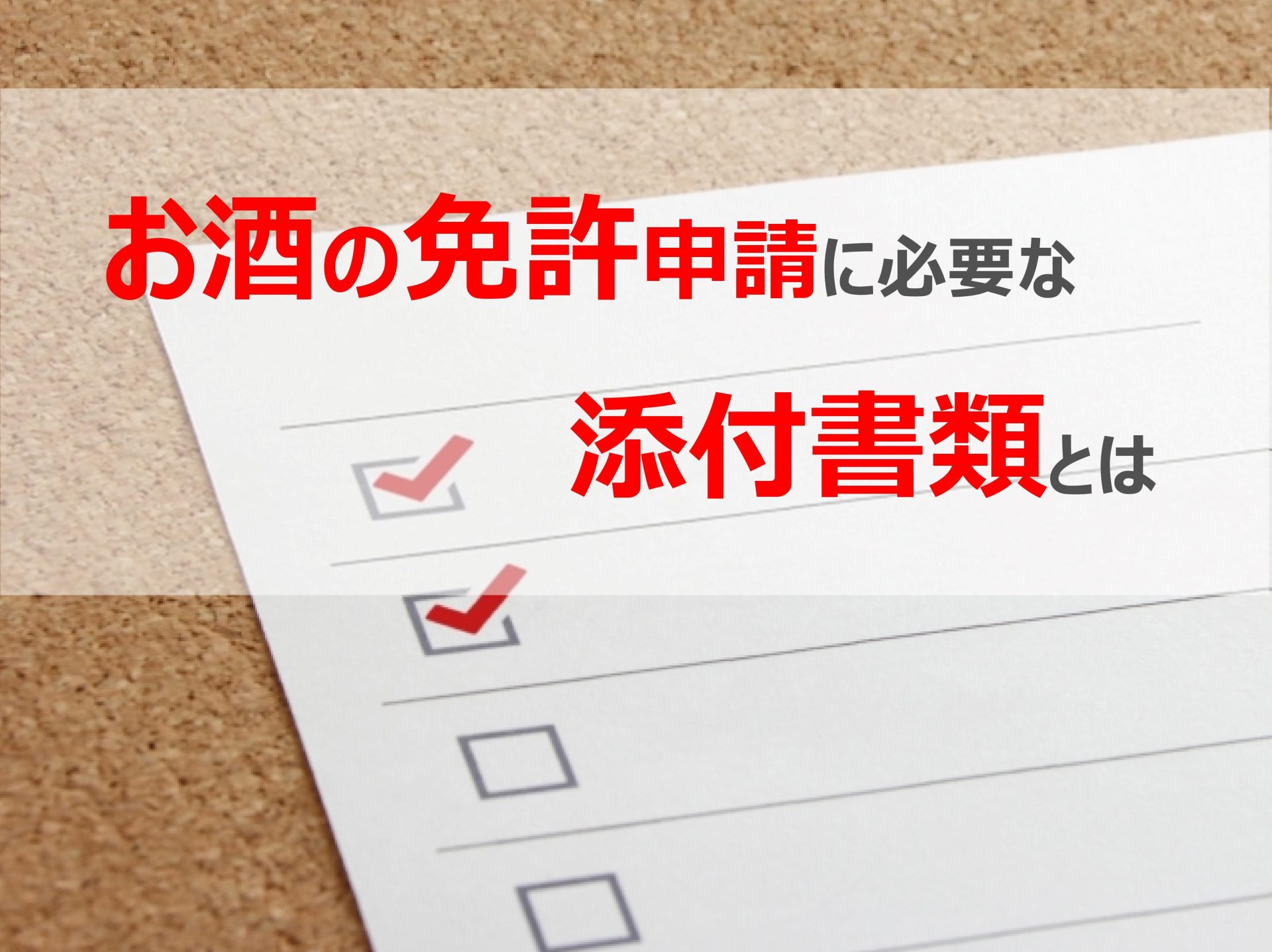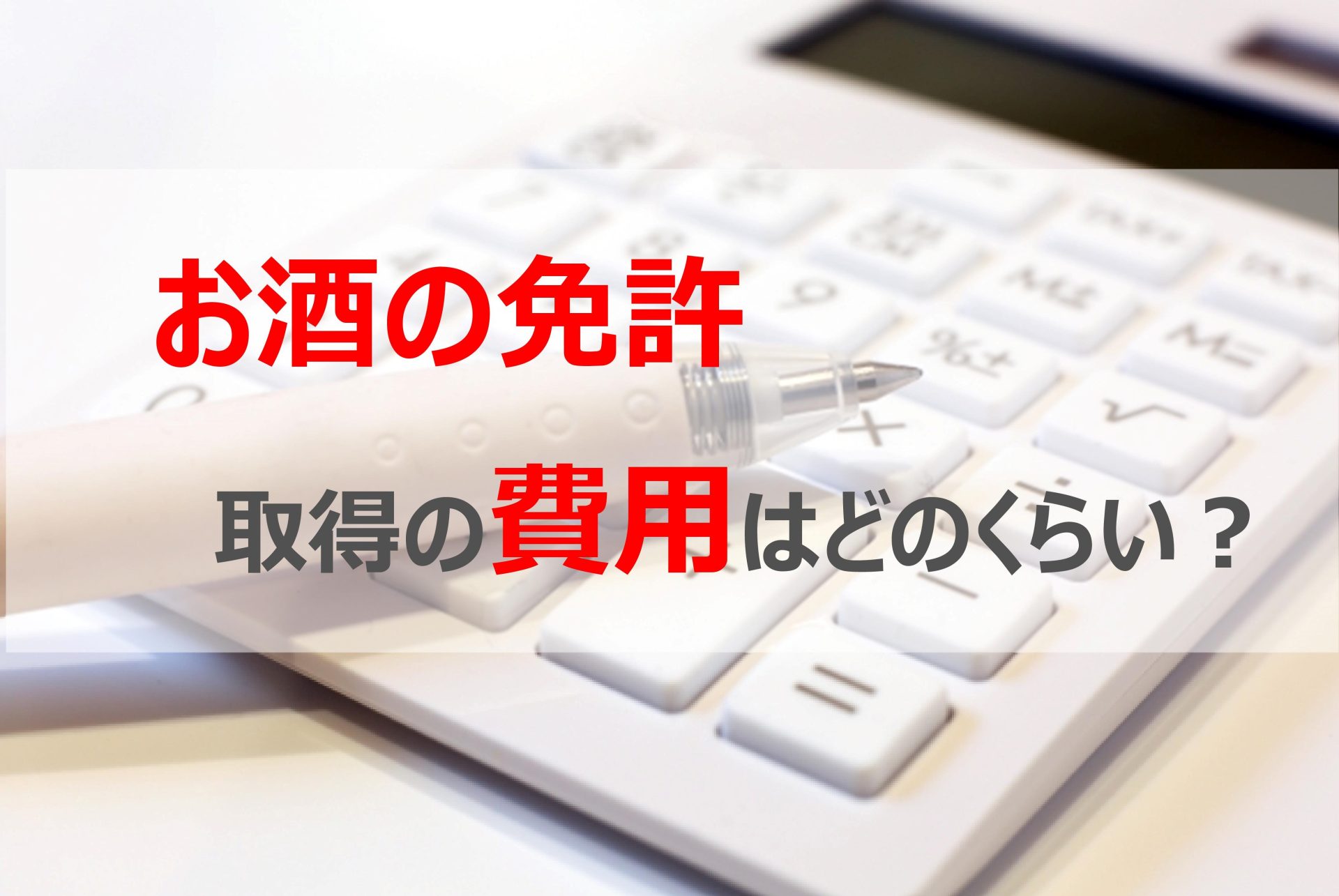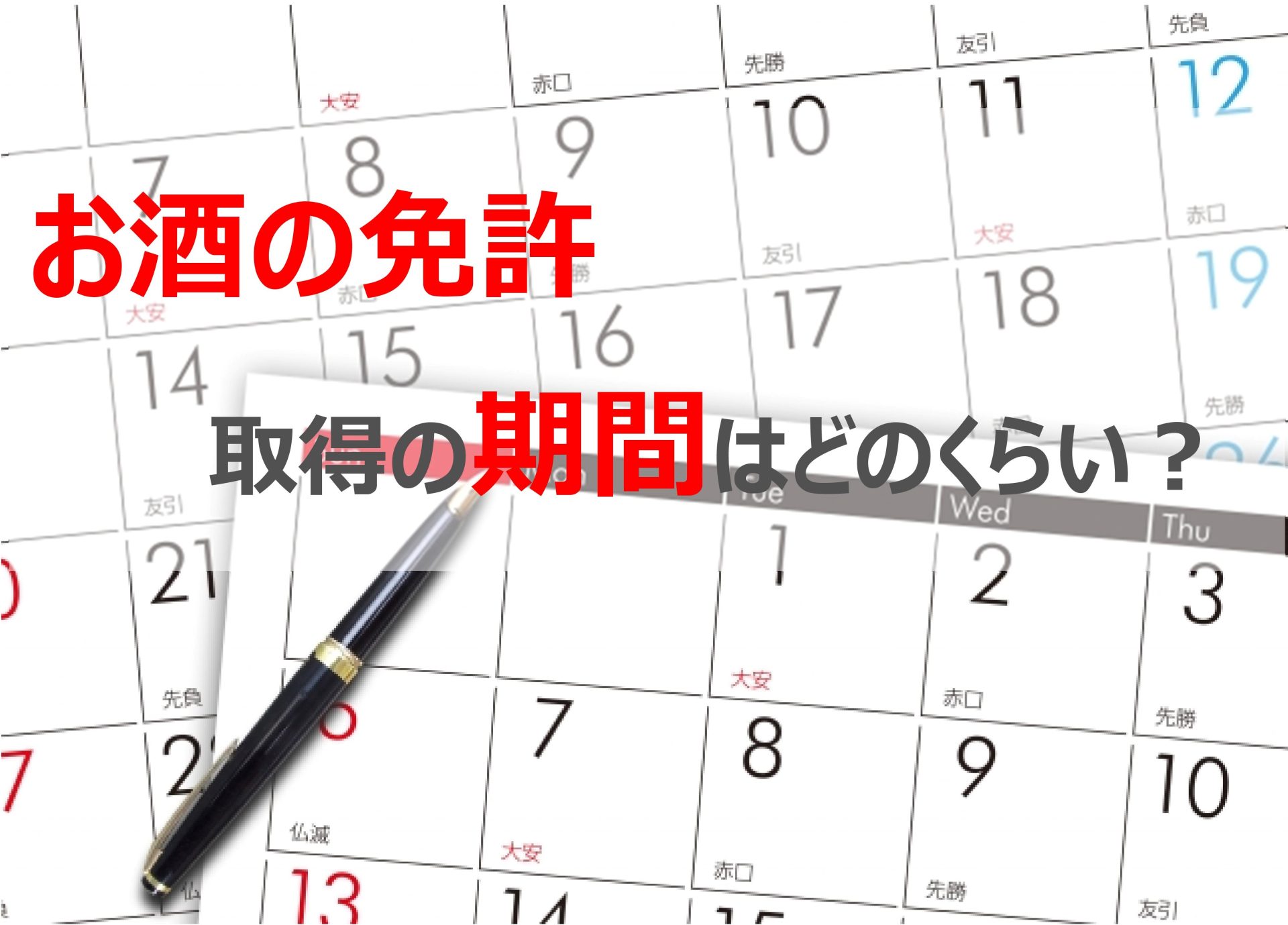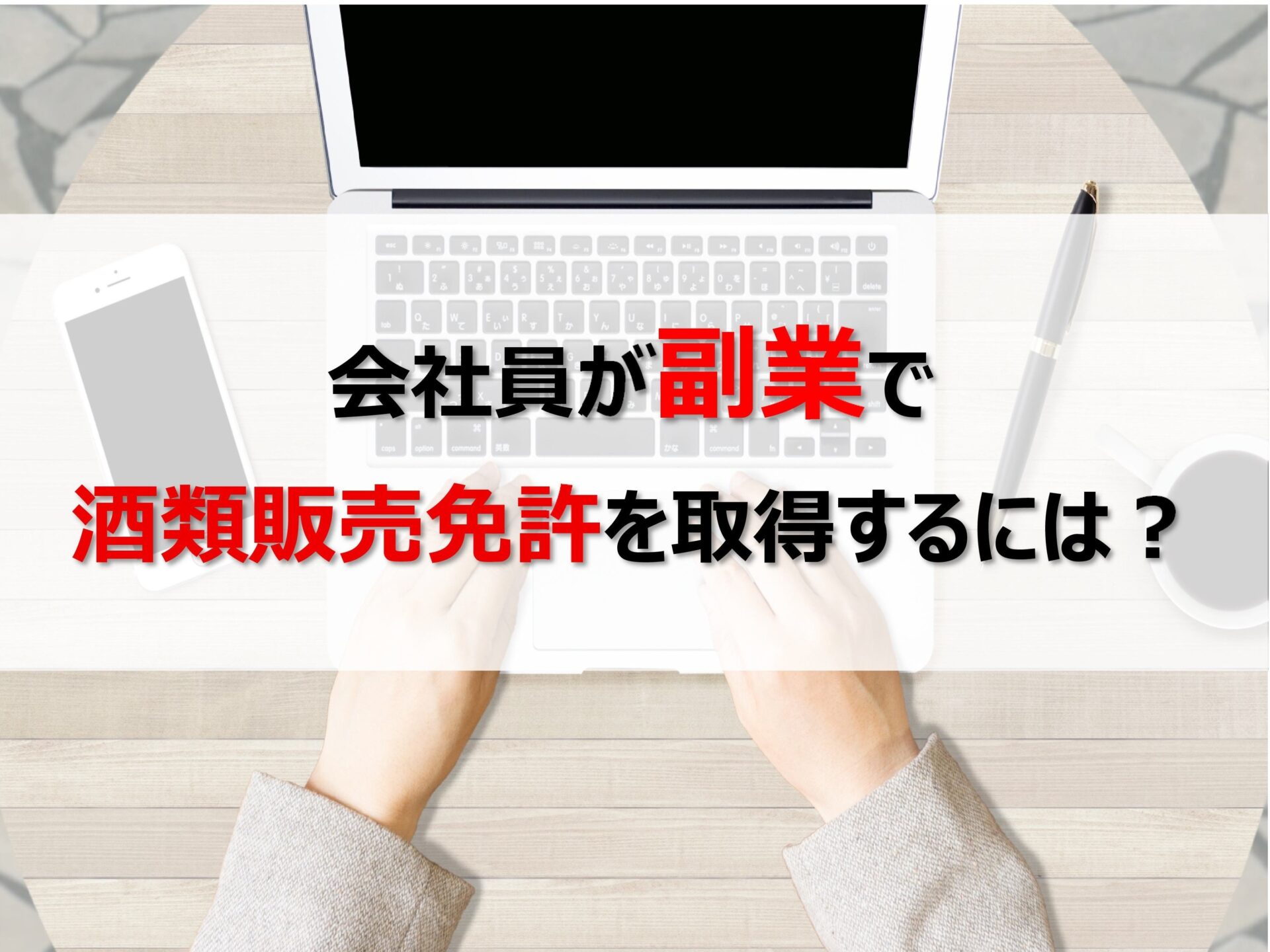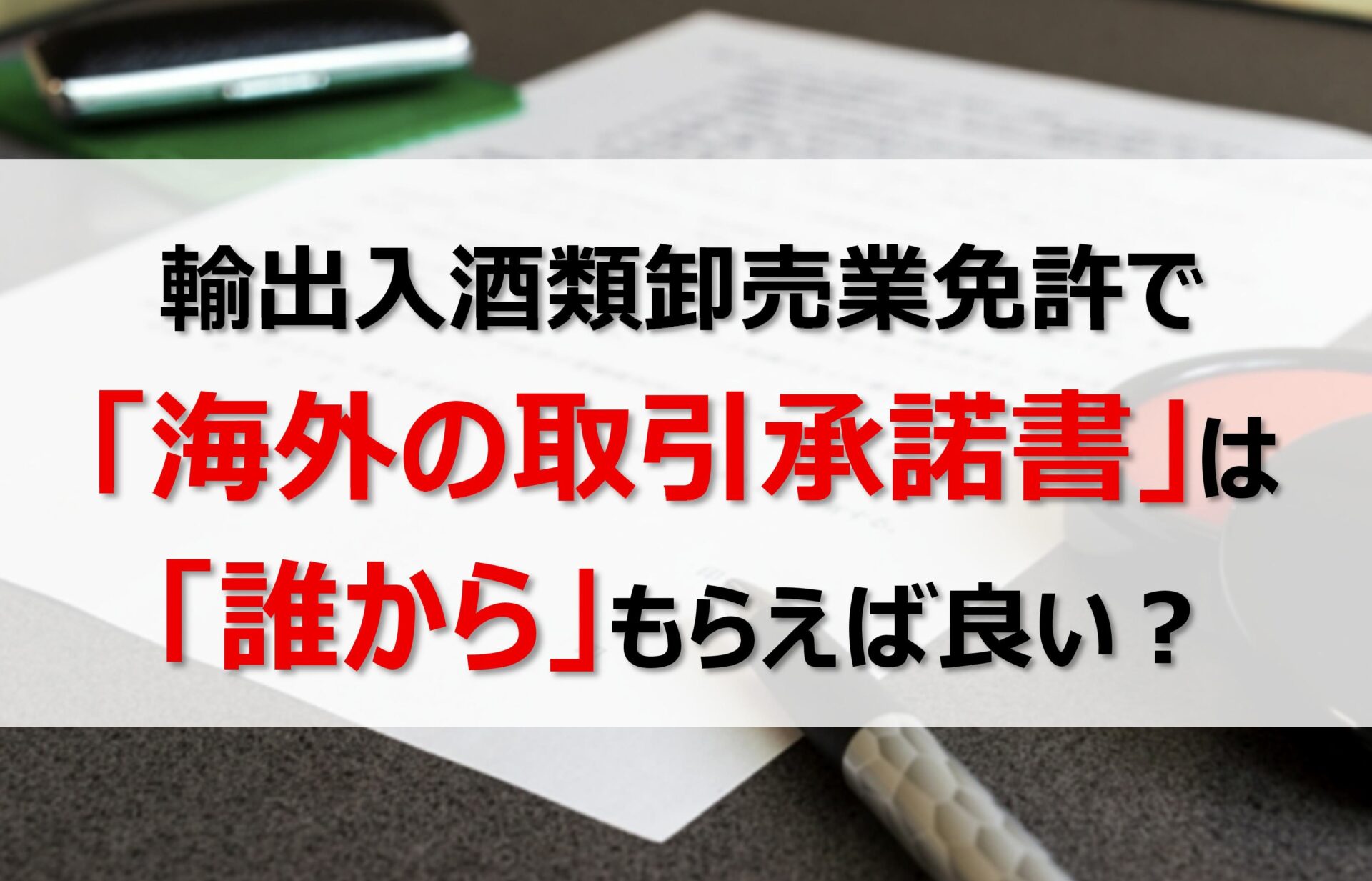酒類販売免許は「販売場ごと」に必要? 複数拠点で販売を行う際の注意点
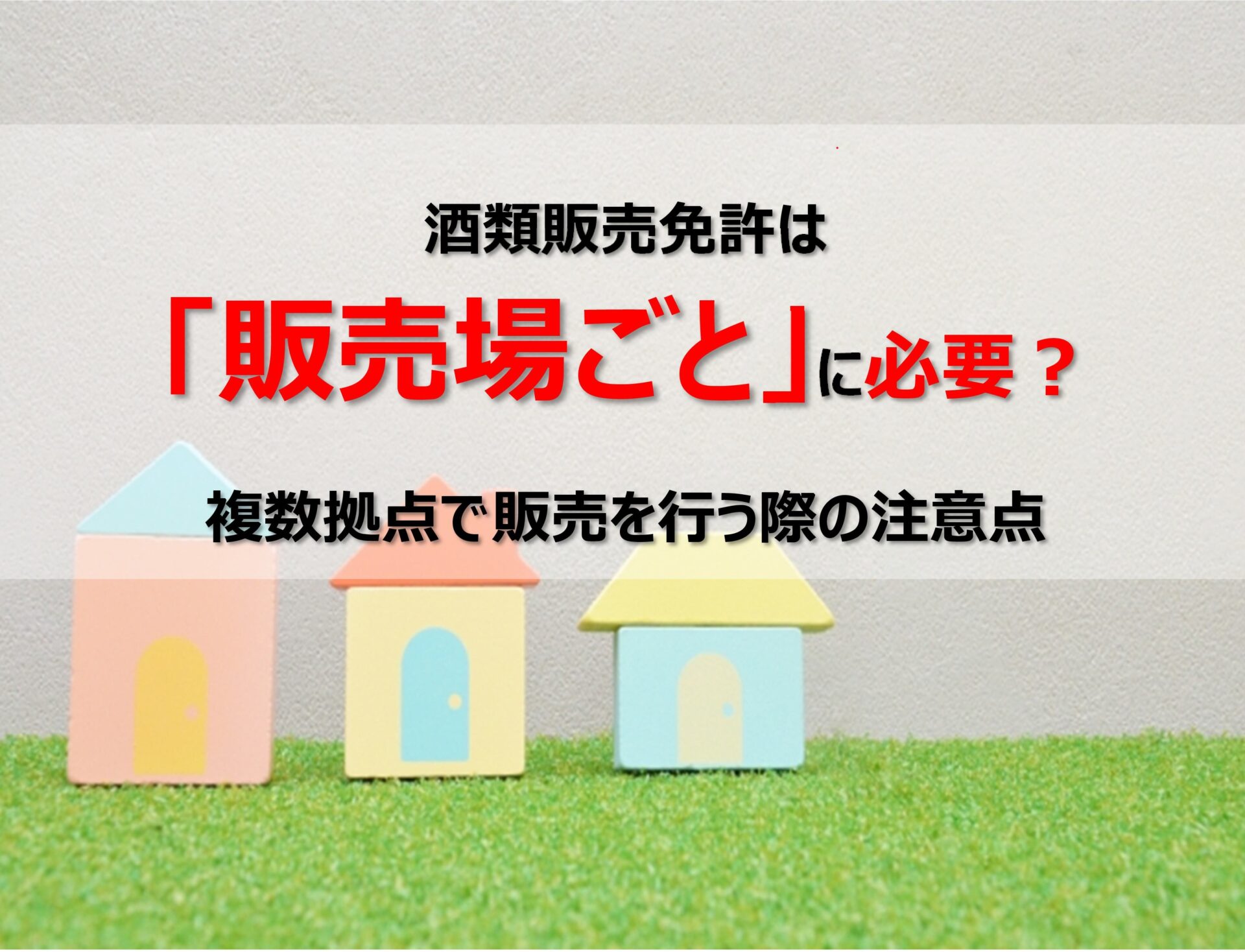
「本社に免許があるから、支店でも販売できるのでは?」そんな誤解が多いのが、酒類販売免許の「販売場ごと」という考え方です。実は、酒類の販売免許は法人や個人単位ではなく、販売場(販売を行う場所)ごとに必要です。この記事では、「販売場」とは何か、なぜ場所ごとに免許が必要なのかを具体例を交えて解説します。
目次
販売場とは
「販売場」とは、実際に酒類の取引(受注や引渡し)を行う場所を指します。店舗、事務所など、顧客との売買契約が成立する拠点が該当します。たとえば以下のような場所が販売場になります。
- 店舗でお酒を販売する場合 → その店舗
- 通信販売の場合 → 受注を行う本社や営業所
- 法人登記上の所在地と別に販売拠点がある場合 → その販売拠点
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
「販売場ごと」とはどういうこと?
たとえば次のようなケースを考えてみましょう。
| ケース | 販売場 | 必要な免許 |
| 本社(東京)でネット通販 | 東京本社 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 支店(大阪)でもネット通販を開始 | 大阪支店 | 通信販売酒類小売業免許 |
| 百貨店に常設店舗を出店 | 百貨店店舗 | 一般酒類小売業免許 |
つまり、販売が行われる場所ごとに免許が必要であり、たとえ同じ法人でも、別の住所の販売場では新たな申請が必要となります。
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
免許を受けないで販売を行うと「無免許販売」になる
酒類を販売するには、必ず販売場ごとに酒類販売業免許を受ける必要があります。免許を受けずに販売を行った場合は、酒税法上の「無免許販売」にあたります。
無免許販売の罰則
酒税法第56条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる場合があります。法人が行った場合には、法人自体も処罰の対象となります。
販売場を増やすには「新規申請」が必要
新たに店舗や営業所を設けて酒類を販売する場合は、販売場を追加するたびに、その販売場を管轄する税務署へ新たに酒類販売業免許の申請が必要となります。
申請の流れは通常の新規申請と同様で、
- 必要書類の準備(申請者の定款、履歴書、通帳コピー、納税証明書、販売場の賃貸契約書・間取図・登記事項証明書など)
- 税務署での審査(おおむね2か月程度)を経て、免許が交付されます。
また、申請の際には登録免許税がかかります。
免許の種類により1販売場あたり3万円または9万円(納付書による納付)が必要です。
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
こんな時は? イベントで一時的に販売したい場合
イベントや期間限定ショップなど、一時的に酒類を販売する場合は、「期限付酒類小売業免許」の届出(または申請)をすることで、期間限定の販売が可能になります。すでに免許を受けた販売場が行うことが出来ます。免許を受けた販売場が、期間限定で出張販売を行うイメージです。
(例:3日間のイベント出店など)
🔸期限付酒類小売業免許のポイント
- 既に免許を受けた販売場または製造場が申請可能
- 開催地の所轄税務署で事前に申請又は届出が必要
- 開催期間・販売品目を限定して許可される
▼こちらの記事も併せて読みたい▼
酒類販売免許は、法人や個人単位ではなく「販売場ごと」に必要です。本店で免許を取得していても、支店や新店舗で販売を行う場合には、それぞれの拠点で新たに免許を取得しなければなりません。
審査には2か月を要するため、新規出店のスケジュールに免許取得が間に合うか不安がある場合は専門の行政書士に相談するとよいでしょう。
まとめ
- 酒類販売免許は会社単位ではなく販売場ごとに必要
- 「販売場」とは、実際に取引・販売が行われる場所のこと
- 免許を受けないで販売を行うと「無免許販売」になる
- 支店や別拠点で販売する場合は、それぞれ免許を新規で取得する
- イベント販売は「期限付酒類小売業免許」で対応