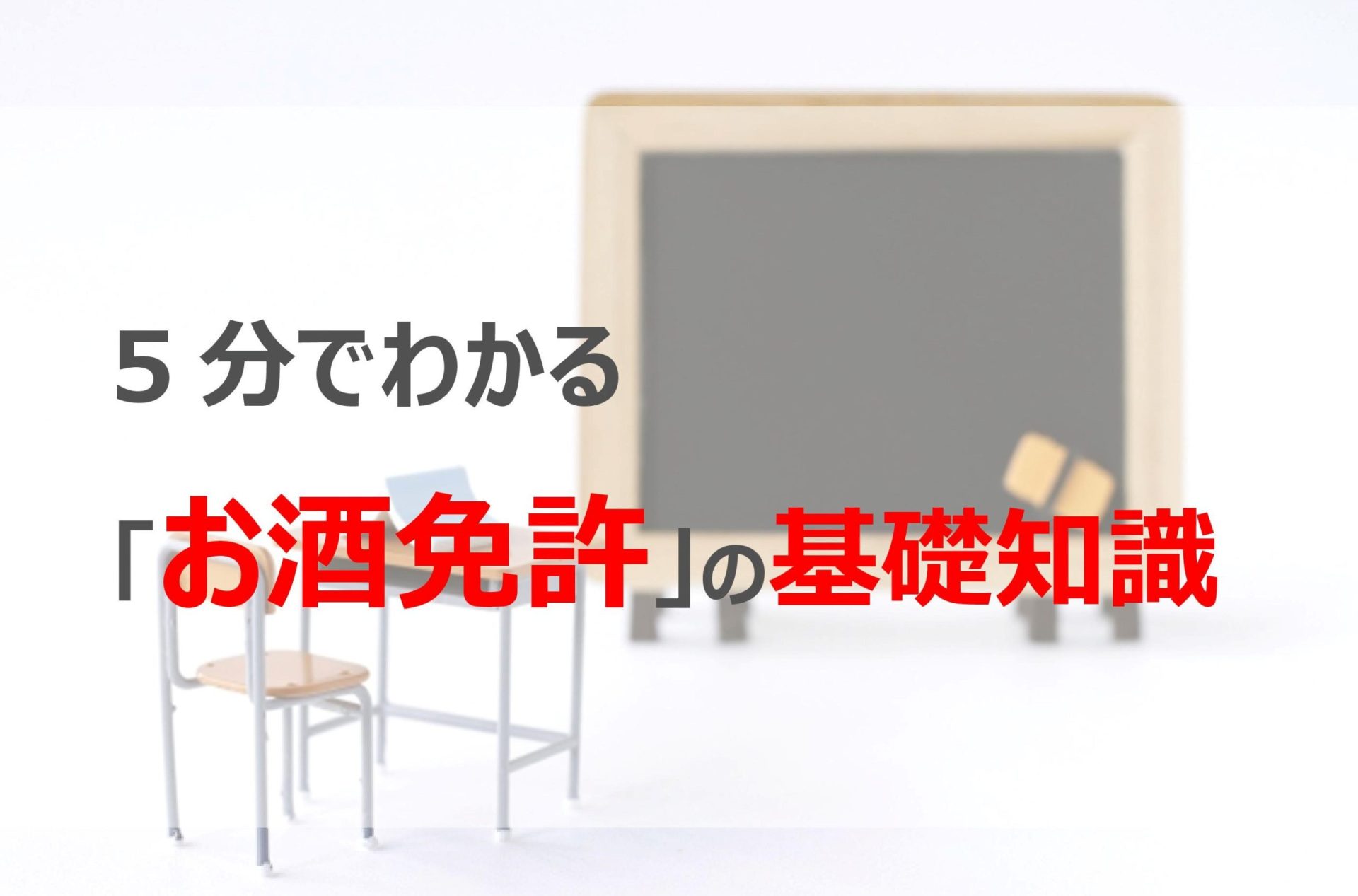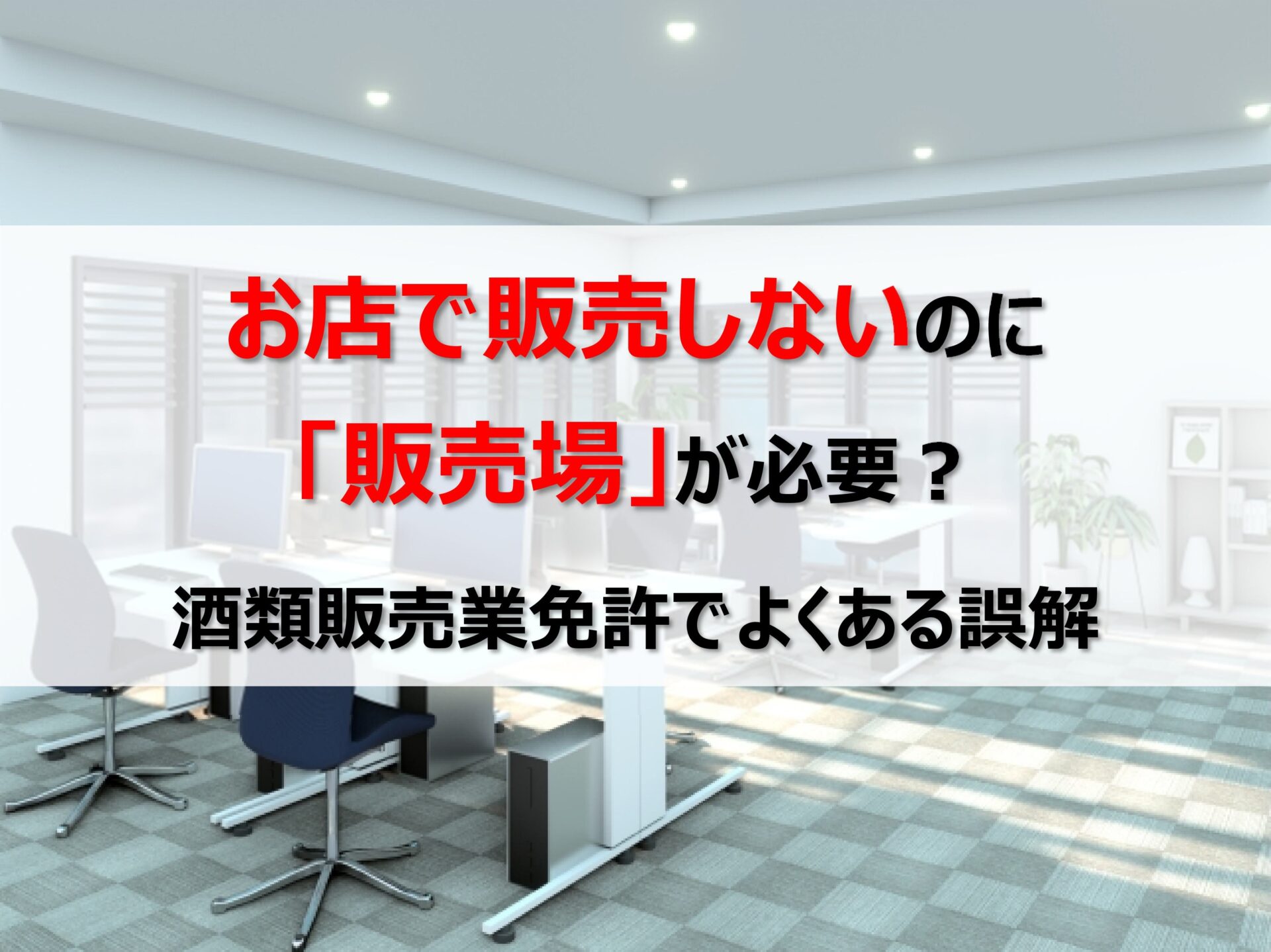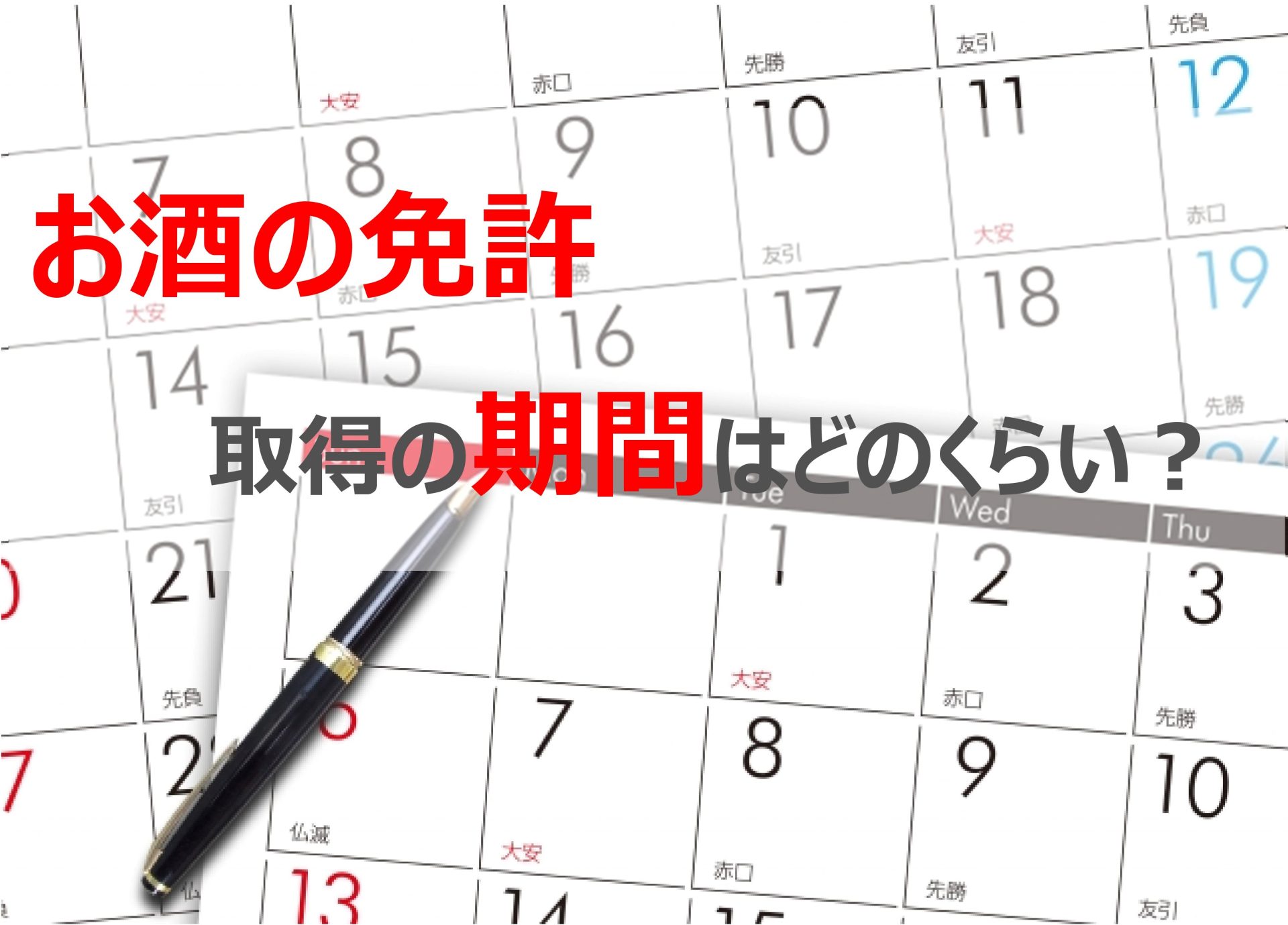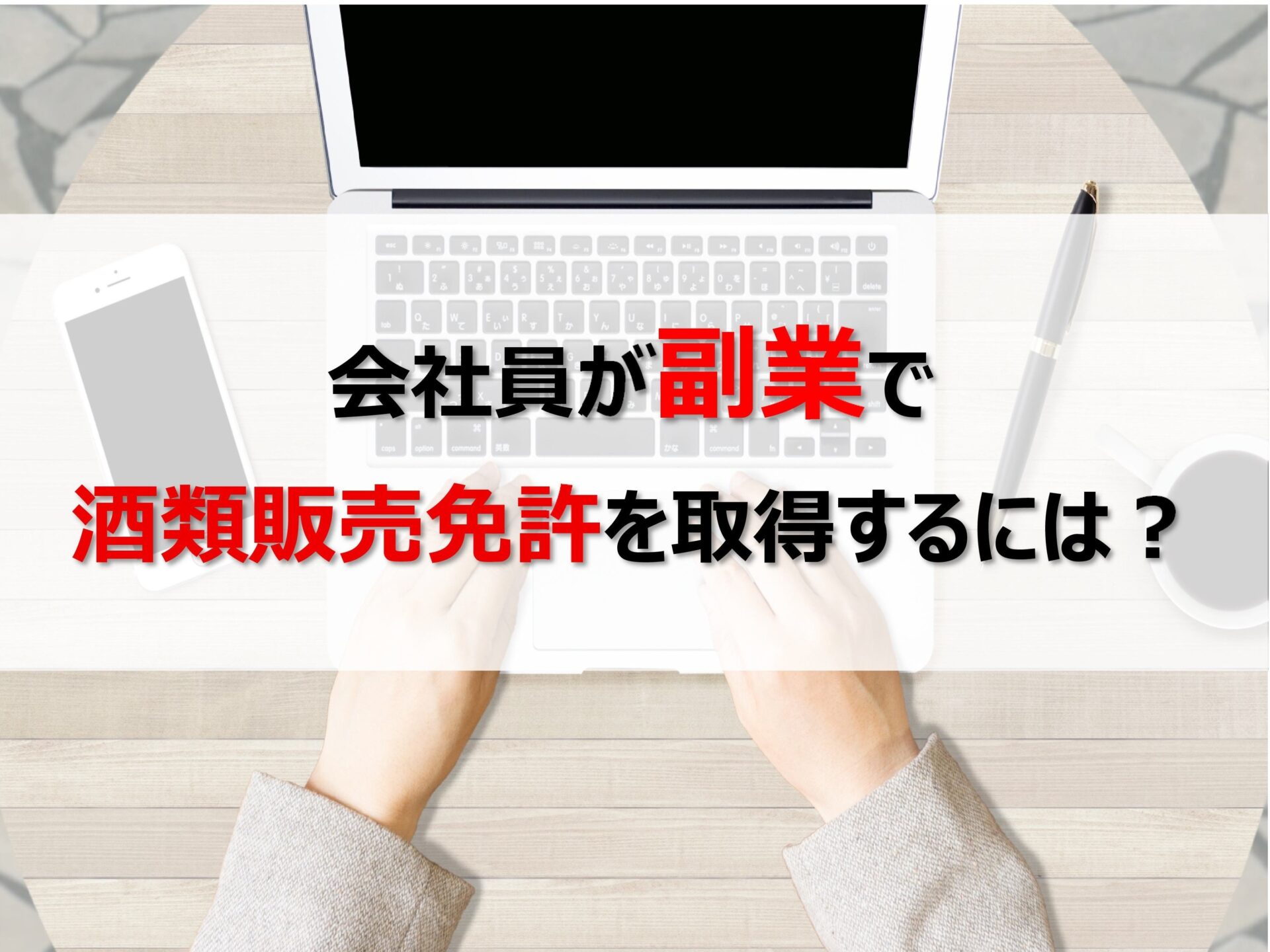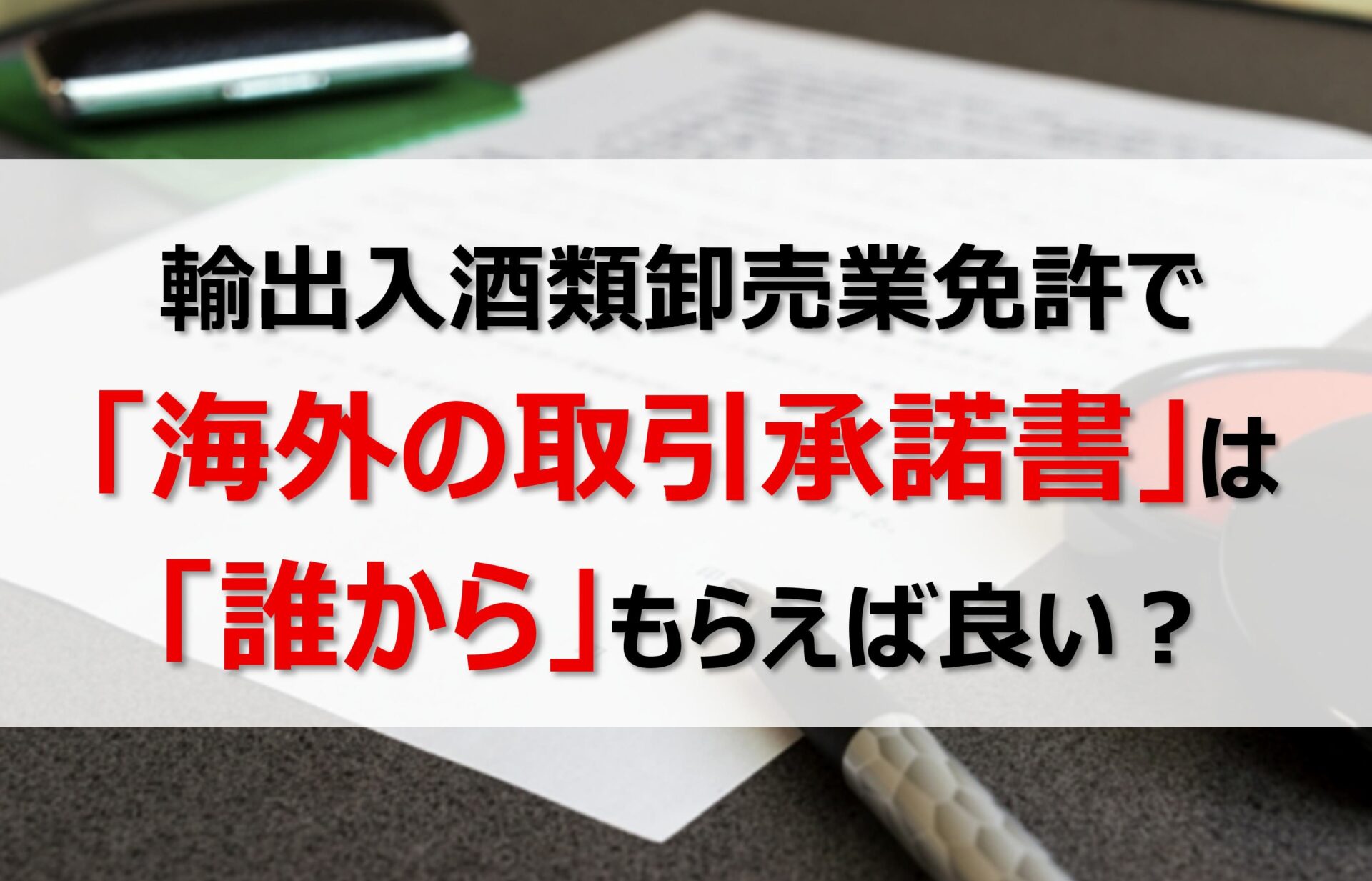ECサイトでお酒を販売するには本当に通信販売酒類小売業免許だけで大丈夫?
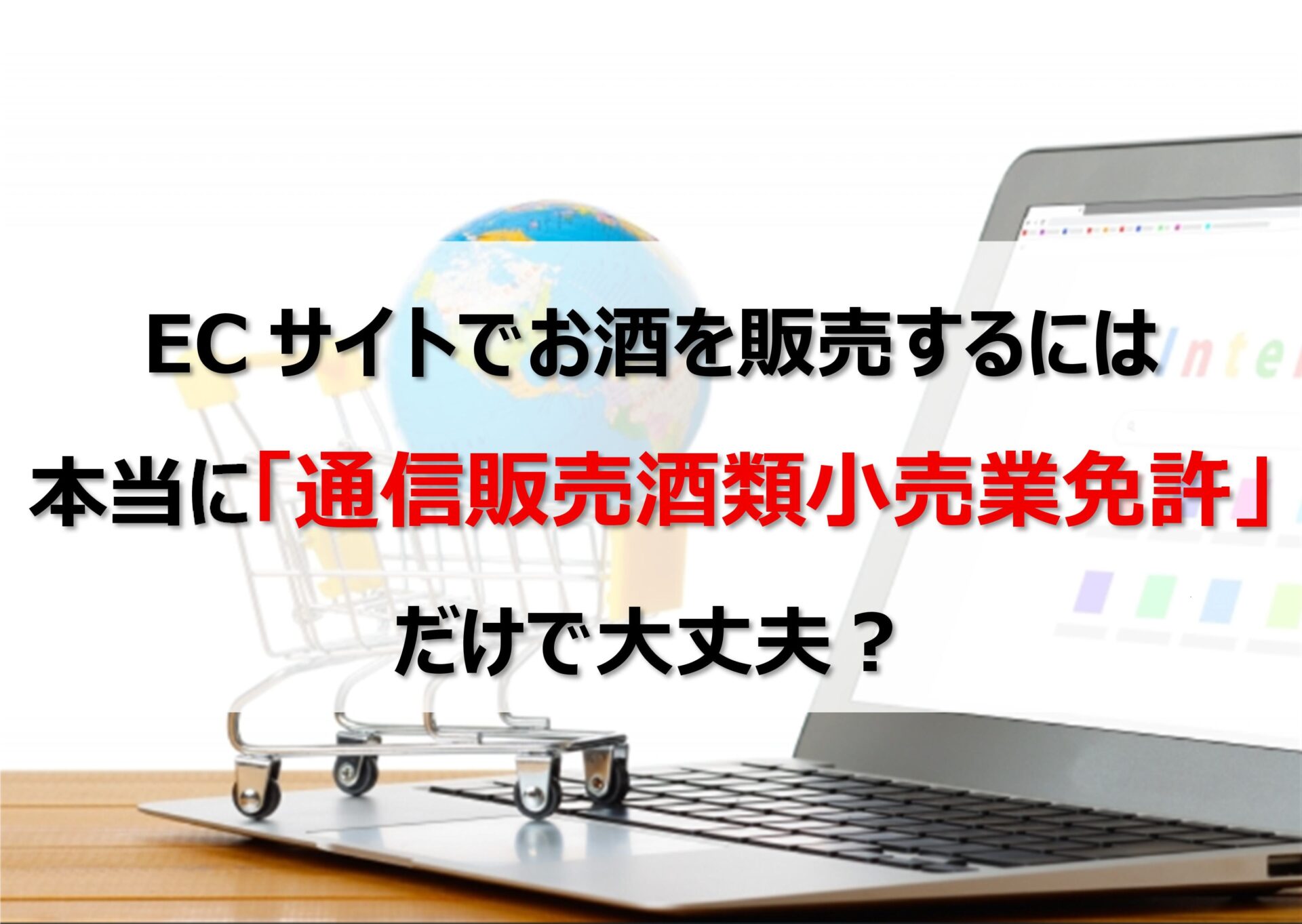
近年、ワインやクラフトビール、日本酒などをオンラインで販売する事業者が増えています。
「お酒を販売するには酒類販売業免許が必要で、その中でも通信販売酒類小売業免許を取得すればEC販売ができる!」そう思われている方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際には販売する相手(国内・海外・業務用など)によって必要な免許が異なります。
通信販売酒類小売業免許だけでは足りないケースもあり、誤った免許で営業を開始すると「免許条件違反」で罰せられる可能性があります。
この記事では、ECサイト運営で必要となる酒類販売免許を「販売先別」に整理し、間違えやすいポイントを実務の視点からわかりやすく解説します。
目次
お酒を販売するには酒類販売免許が必要
まず、前提として酒類を販売するには、「酒税法」に基づく酒類販売業免許が必要です。
免許を受けずに販売した場合は「無免許販売」、間違った免許で販売をしてしまった場合は「免許条件違反」となり罰則の対象になります。
無免許販売や免許条件違反の罰則
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(酒税法第56条、酒税法第58条)
酒類販売免許は販売方法や販売先によってたくさんの種類に分れていて、ECサイトで販売する場合は、販売する相手によって、免許の種類が異なります。適切な免許を取得するようにしましょう。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
ECサイトで必要となる免許の種類
それでは、ECサイトで必要となる免許の種類を「販売先別」に見ていきます。
① 国内向けECサイト
国内の消費者に販売する場合は、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
最も多いケースがこちらです。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
② 海外向けECサイト(越境EC)
海外の消費者にお酒を通信販売する場合は、「輸出酒類卸売業免許」が必要です。
免許を間違えてしまうことが多いのがこのケースです。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
③ 国内・海外どちらにも販売するECサイト
国内海外両方への販売を行うECサイトの場合は、「通信販売酒類小売業免許」と「輸出酒類卸売業免許」の両方を取得する必要があります。
このケースでは、審査がスムーズに運ぶように所轄税務署に事業スキームを説明することをお勧めします。
④酒類販売業者向け業務用卸ECサイト
一般消費者ではなく、「酒類販売業者」向けにオンラインで販売する業務用卸サイトの場合は、通信販売酒類小売業免許ではなく卸売業免許(全酒類卸売業免許、洋酒卸売業免許など)が必要になります。このケースも誤解が多いため注意が必要です。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
どこで免許を取得する?
免許は受注業務を実際に行う場所(販売場)で申請します。
販売場とは、受注処理・契約管理・在庫管理などを行う事務所または店舗を指します。
倉庫や配送センターが別にあっても、契約行為を行う場所が販売場となります。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
申請する税務署
販売場の所在地を管轄する税務署が申請先です。
たとえば、本社事務所で受注業務を行う場合は、本社事務所が販売場となりますので、本社の所在地を管轄する税務署で申請します。
費用(登録免許税)と期間
- 登録免許税(申請時の手数料):3万円または9万円
※免許により金額が異なります。 - 審査期間:原則2か月
※申請内容や添付書類に不備があると、さらに時間がかかる場合があります。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
注意するポイント
上記のように、ECサイトの販売=必ずしも「通信販売酒類小売業免許」とは限りません。海外販売を含む場合は「輸出酒類卸売業免許」が必要ですし、酒類販売業者向け業務用卸サイトは卸売免許(全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許)が必要になる点に気を付けましょう。
判断に迷う場合は、税務署の酒類指導官や専門の行政書士に相談すると良いでしょう。
まとめ(チェックポイント)
- ECサイトでお酒販売するには、販売相手によって必要な酒類販売業免許が異なる
- 国内販売は「通信販売酒類小売業免許」
- 海外販売は「輸出酒類卸売業免許」
- 国内外両方の場合は両方の免許を取得(事前相談推奨)
- 酒類販売業者向け業務用卸ECサイトは卸売り免許(全酒類卸売業免許や洋酒卸売業免許)が必要