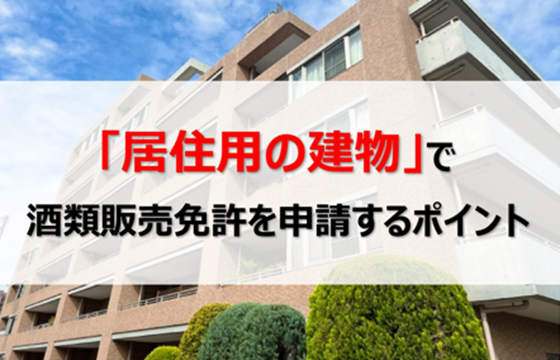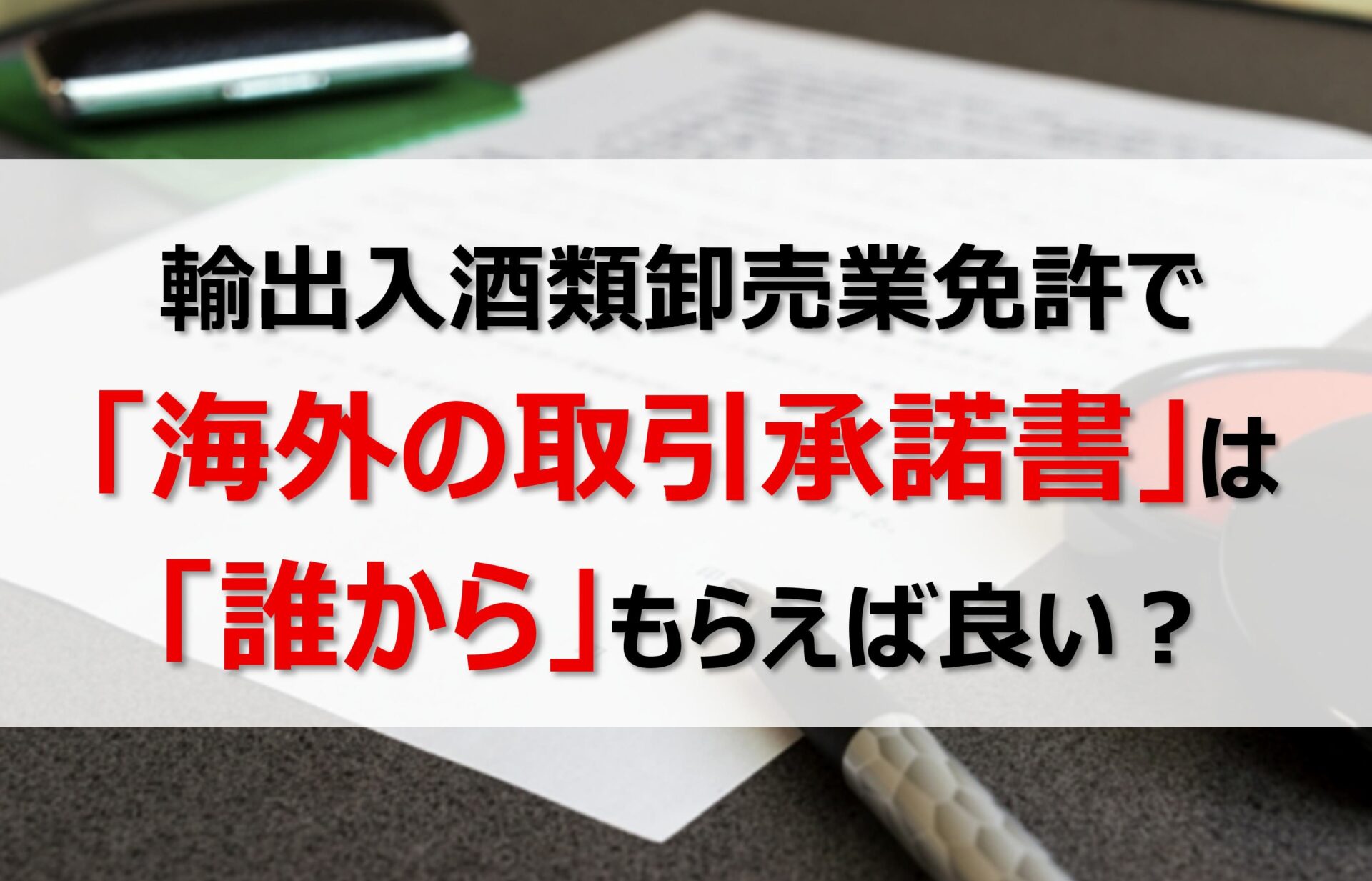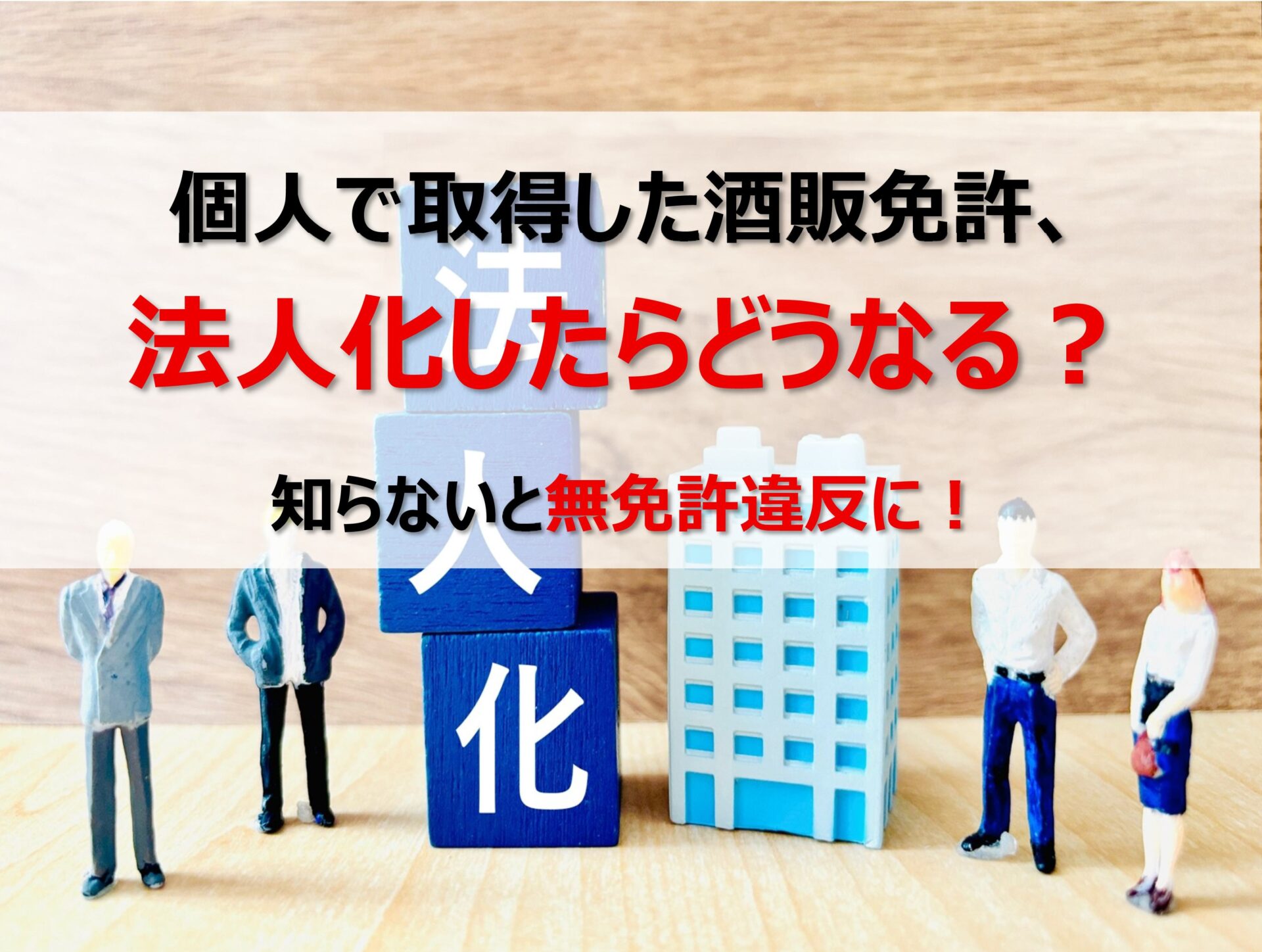建物が未登記でも酒類販売業免許は取得できる?

酒販免許の申請を進めるなかで、「建物は完成しているけれど、まだ登記が終わっていない」「家主の事情で登記をしていない建物を借りている」そんなケースも少なくありません。
建物が未登記であっても、免許が取れないわけではありません。
ポイントとなるのは、その建物の所有者を明確に確認できるかどうかです。
この記事では、未登記建物で申請する際に求められる「所有者確認」の考え方と、具体的な対応方法を解説します。
▼こちらの記事も合わせて読みたい▼
目次
建物の登記事項証明書は、なぜ必要なのか?
酒類販売業免許の申請書類には、「建物の登記事項証明書」の提出が求められます。では、なぜこの書類が必要なのでしょうか。
それは、申請者が販売場として使用する建物について、所有者を確認するためです。
登記事項証明書には、建物の所在地、面積、構造、そして所有者の氏名・住所などが記載されており、所有権の所在を裏付ける基本的な資料として位置づけられています。
国税庁が公表している「一般酒類小売業免許申請の手引」。その21頁「Ⅳ 申請書類一覧表」には、申請時に建物の登記事項証明書の添付が求められていることが明記されています。
ただし、建物が未登記の場合については明文化されておらず、実務では建物の所有者を証明する代替資料を提出することで対応するのが一般的です。
未登記建物での申請に必要な書類
実務上は、建物がすでに完成している場合と、新築で登記前の場合に分れることがほとんどで、ここでは、それぞれのケースごとに必要書類の例を紹介します。
建物がすでに完成している場合
📄固定資産課税証明書
固定資産の評価額や税額等を証明する書類で、固定資産税は所有者が支払うことから、課税対象者が所有者であると説明できます。この書類が最も有力な代替書類の一つです。
※建物の所有者が自治体や大学などで、固定資産税の課税対象になっていない場合は、その代わりに固定資産台帳や財産目録など、所有者が管理する資産台帳の写しを提出しましょう。
新築で登記前の場合
📄建築検査済証または仮使用認定通知書
建物が建築基準法に適合していると認められた際に、建築主に交付される書類で、建築主が所有者と同一の場合は所有者者であることを説明する根拠資料になります。
📄建築請負契約書
建築主と施工業者の契約書は、建築主が施工業者に代金を支払うことから、所有者であると間接的に説明できます。
💡ワンポイントアドバイス
これらの書類は、あくまでも建築主を特定できるものであり、所有者と必ずしも一致しない可能性があるため、税務署に相談のうえ、複数の資料を提出することで所有者であることを説明すると良いでしょう。
実務上のポイント
- 未登記でも申請は可能
建物が未登記だからといって、直ちに申請ができないわけではありません。上記のような登記事項証明書に代わる資料が揃えば、酒類販売業免許の申請は可能です。大切なのは、建物の所有者が客観的に確認できることです。 - 事前相談が重要
所轄税務署の酒類指導官に事前相談を行い、必要となる書類や提出方法を確認しておきましょう。地域や税務署によって求められる資料や運用に差があるため、早めの相談がスムーズな申請につながります。
また、不安がある場合は、お酒の免許申請に詳しい行政書士へ相談すると安心です。実務での書類の整え方や税務署とのやり取りのポイントなど、現場に即したサポートが受けられます。
まとめ
- 建物が未登記でも、所有者を確認できる資料があれば申請は可能。
- 固定資産課税証明書は最も有力な所有者確認資料。
- 自治体・大学所有の建物は、固定資産台帳や財産目録で代替できる。
- 新築登記前の建物は、建築検査済証・請負契約書などを組み合わせて説明する。
- 税務署やお酒の免許申請に詳しい行政書士への事前相談がスムーズな審査につながる。
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。