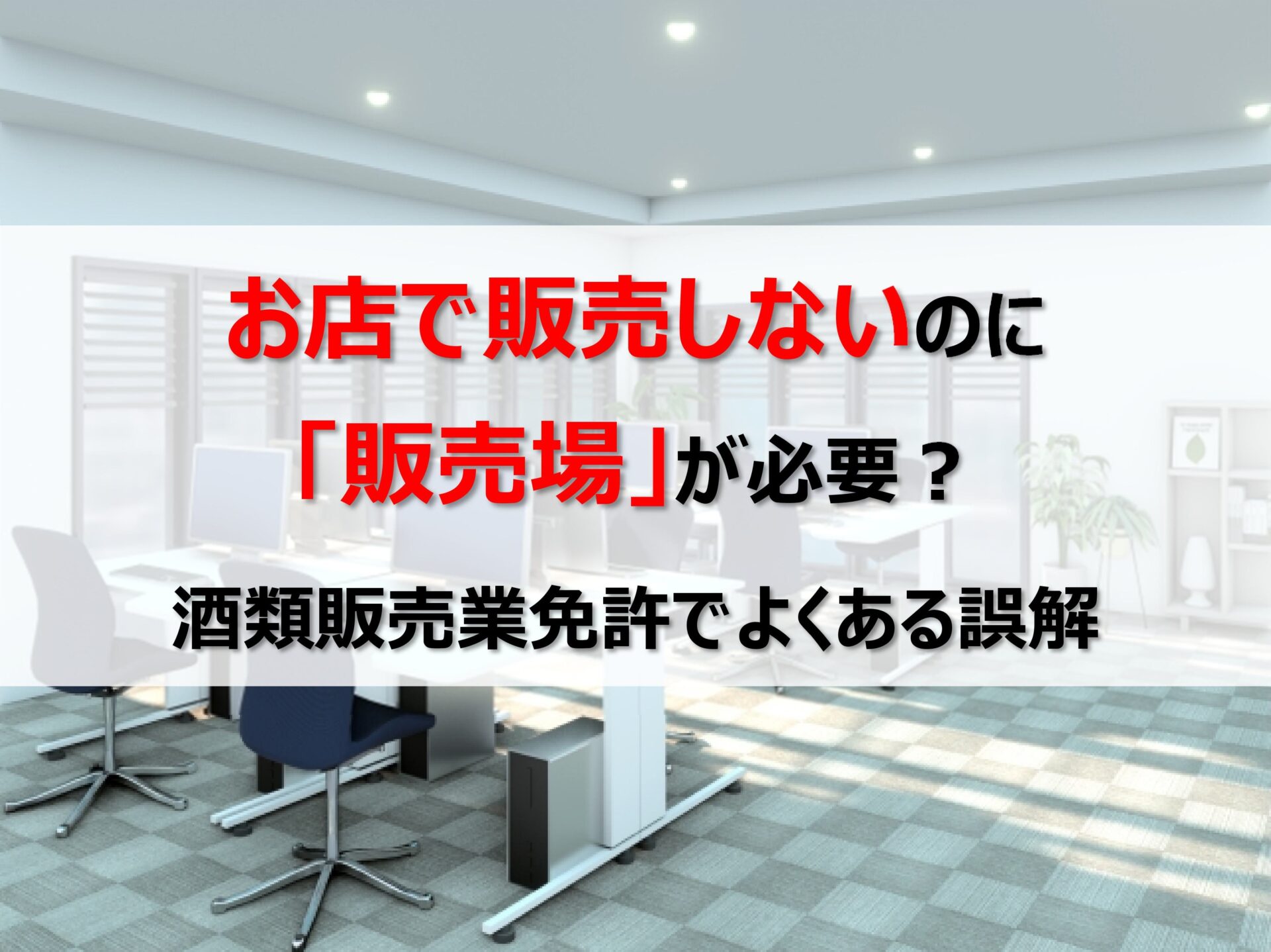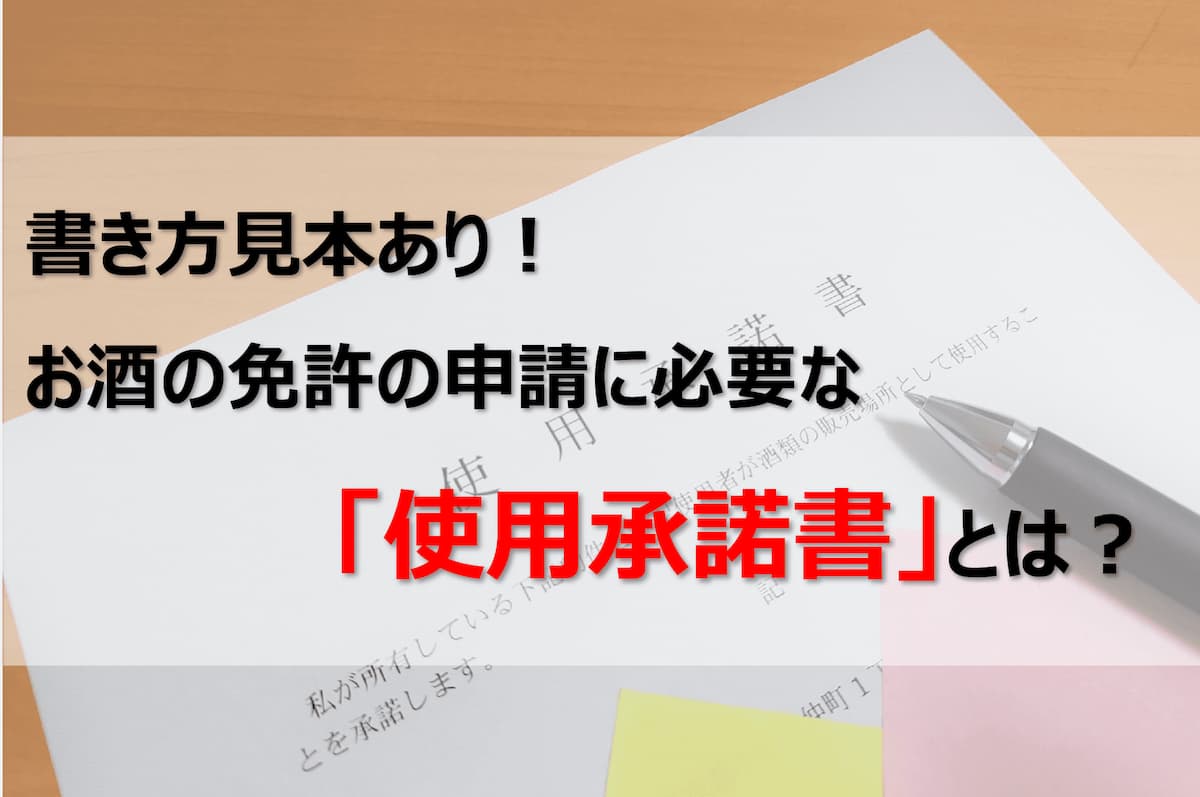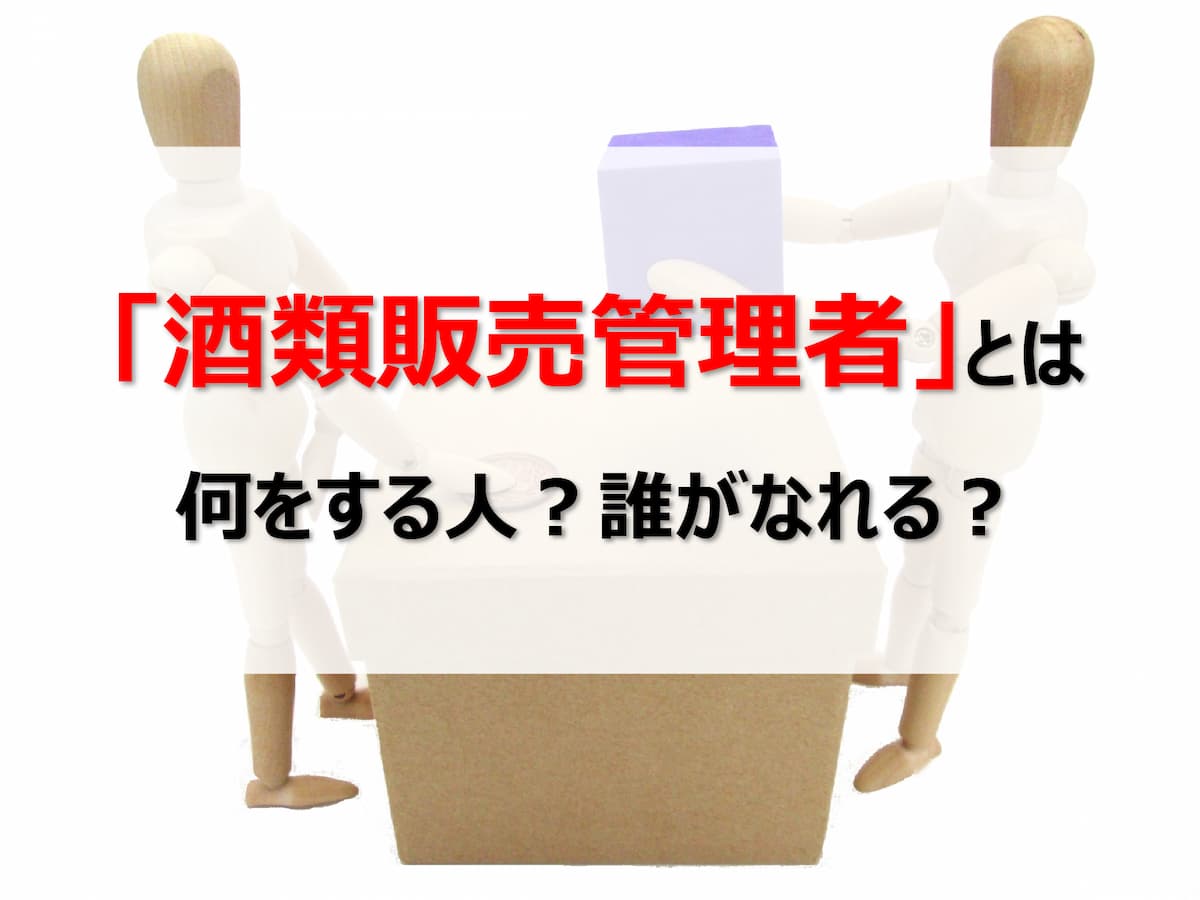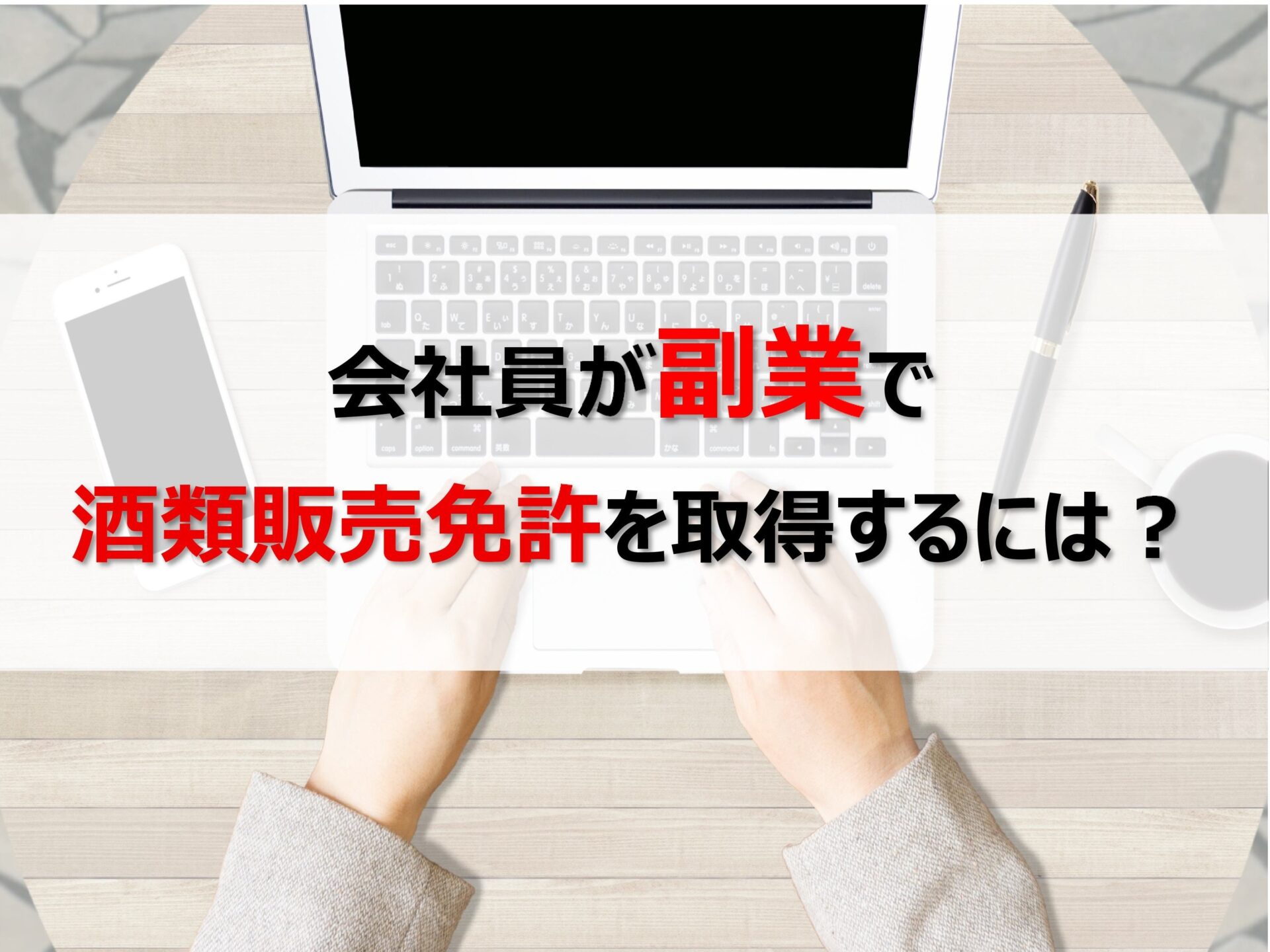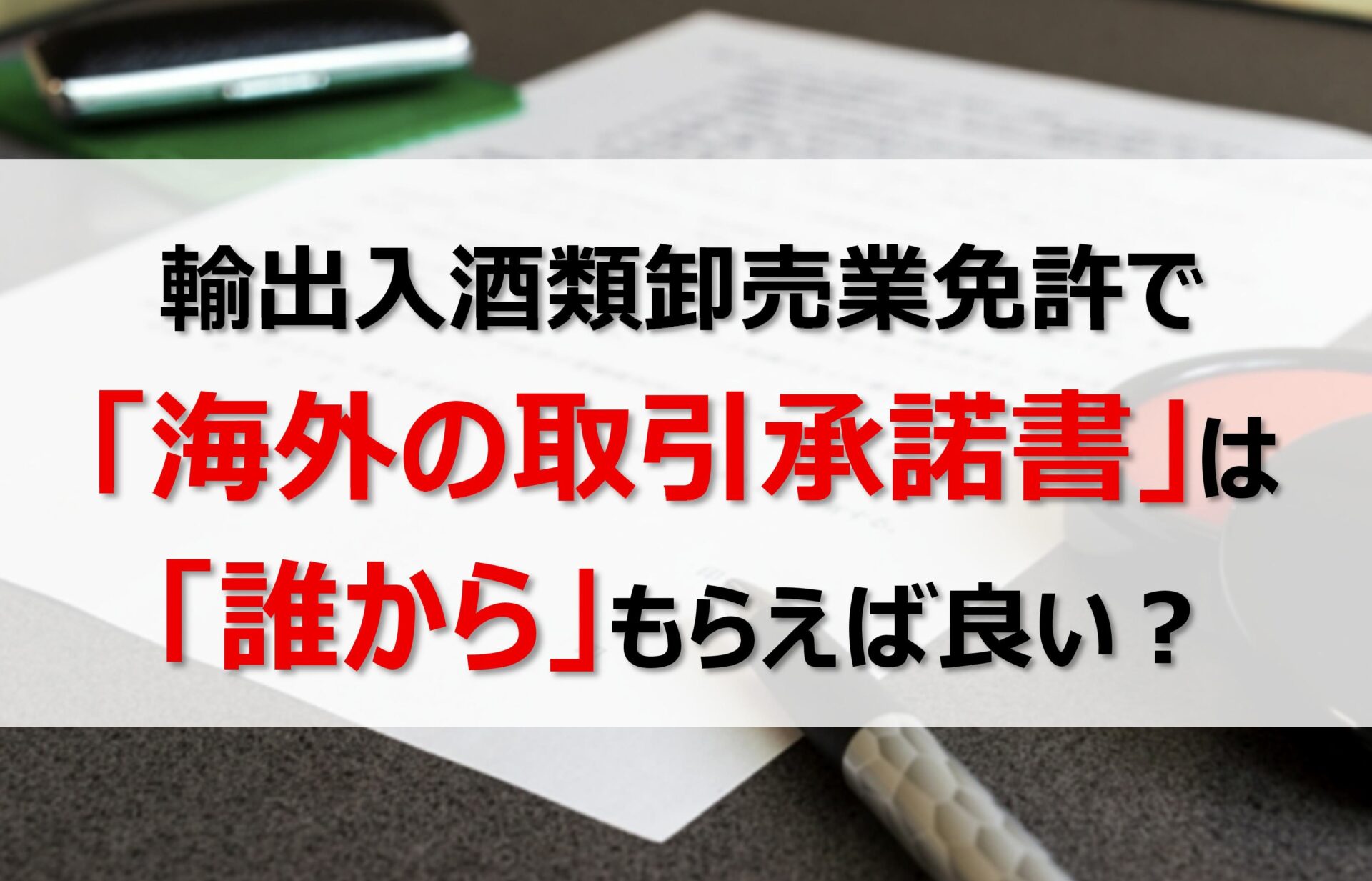バーチャル・シェア・レンタルオフィスで酒販免許は取得できる?場所的要件を徹底解説
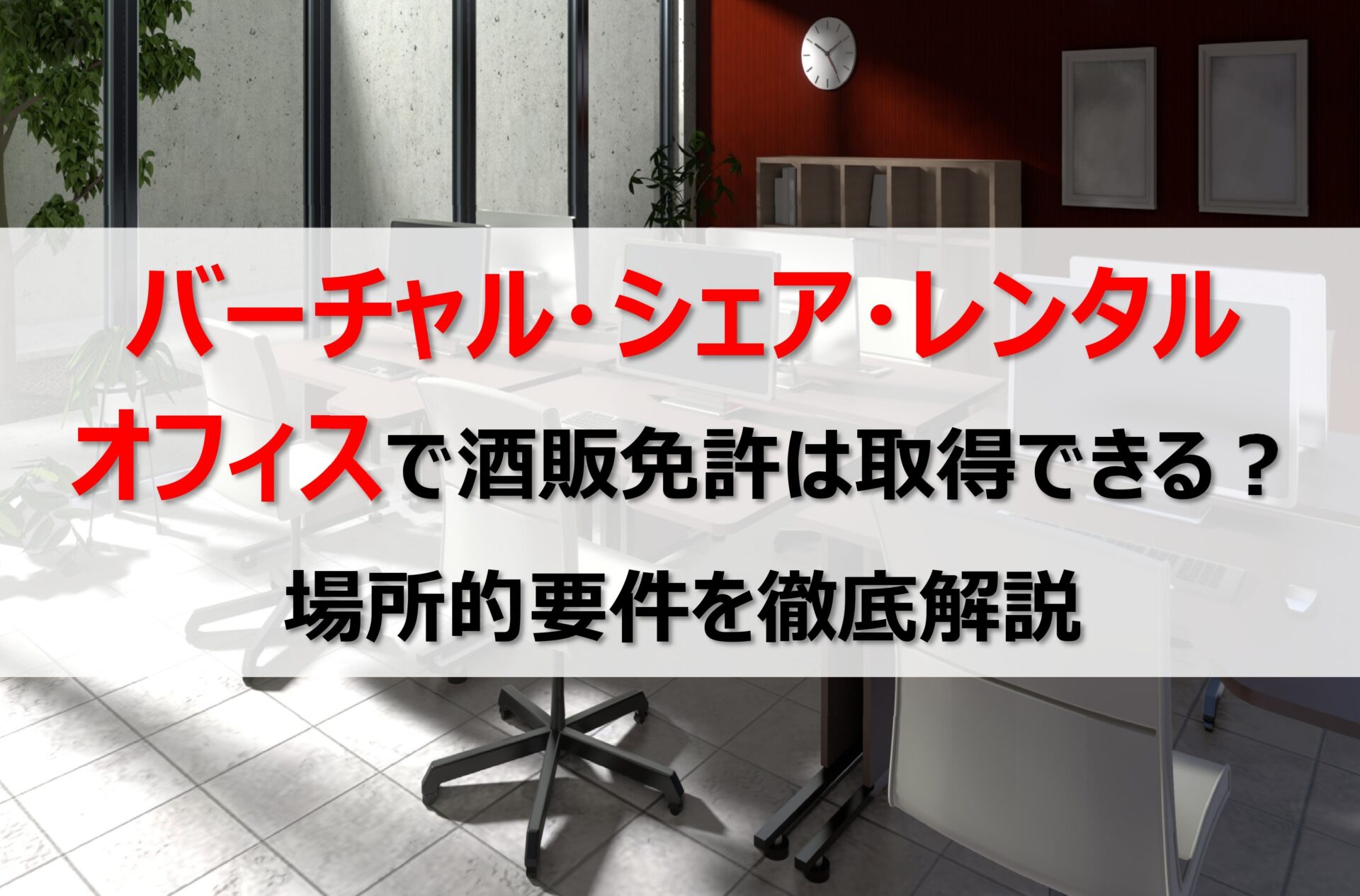
酒類販売業免許を取得したいと考えたとき、最初に確認しておきたいのが「販売場の場所的要件」です。特に近年、リモートワークの普及・柔軟な働き方によりバーチャルオフィスやシェアオフィス、レンタルオフィスを利用する企業が増えていますが、これらのオフィス形態で酒販免許は取得できるのでしょうか?
この記事では、3つのオフィス形態それぞれについて、酒類販売業免許の申請可否を分かりやすく解説します。
目次
酒類販売業免許の「場所的要件」とは?
お酒の免許申請では、大きく4つの要件を満たす必要があり、そのうちのひとつが場所的要件になります。国税庁の手引では、下記のように記載されています。
2 酒税法 10 条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
簡単に言うと、「事業用(酒類販売場)として使っても問題がない場所であること」ということです。
具体的には、下記の2つを満たす必要があります。
①すでに酒類販売業免許を受けている場所ではないこと
②他の営業主体の営業とは明確に区分できること
この場所的要件を満たさなければ、事業計画の内容に関わらず免許は交付されません。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
オフィス形態別・酒販免許取得の可否
バーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィス、それぞれのオフィス形態でどのように判断されるのか、専門家の視点から解説します。
1.バーチャルオフィス: 取得は基本的に不可能×
原則として申請は認められません。
バーチャルオフィスは「住所のみを借りる」サービスであり、実際の執務スペースが存在しません。税務署が求める“実態のある販売場”の条件を満たさないため、バーチャルオフィスでは場所的要件を満たせず、申請は通らないのが一般的です。
⚠️よくある誤解
「法人登記ができる=酒販免許も取れる」と思われがちですが、登記と免許は別物です。登記は場所の審査がないので住所があれば登記できますが、酒販免許は場所的要件を満たした物件でないと免許は取れません。なお、別途実体のある事務所を用意すれば、本社がバーチャルオフィスでも申請は可能です。
2.シェアオフィス: 条件次第で取得の可能性あり△
複数の事業者が同じフロアを共有するシェアオフィスでは「専有スペースの確保」が最も重要なポイントとなります。
○許可が下りる可能性が高いケース
- 鍵付き個室を契約している
- 契約書に「専有スペース」「継続使用」の記載がある
- 他社が自由に出入りできないプライベートな空間である
これらの条件を満たしていれば、シェアオフィスでも販売場として認められる可能性があります。
×許可が難しいケース
- フリーアドレス型(毎回席が変わる)
- パーテーションなどで区切られているだけのオープンスペース
重要なのは、他の営業主体の営業と明確に区分できるかどうかです。
3.レンタルオフィス: 条件を満たせば取得可能〇
レンタルオフィスは、個室を借りる形態が主流のため、他のオフィス形態に比べて場所的要件を満たしやすいと言えます。実際に、多くの事業者がレンタルオフィスで酒販免許を取得しています。
◎取得を成功させるためのチェックポイント
- 鍵付きの個室でプライバシーが確保されているか
- 契約期間が概ね1年以上など、事業の継続性が認められるか
- デスク、パソコンなど、業務の実態が確認できる備品はあるか
- 物件の貸主から酒類販売についての「使用承諾書」を取得できるか
これらの条件をクリアできれば、レンタルオフィスは酒販事業の拠点として、非常に有効な選択肢となり得ます。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
💡ワンポイントアドバイス
販売場には普段、酒類販売管理者が常駐していることが求められます。
実際には業務を行っていないということがない様に業務フローや人材配置等、体制を整えましょう。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
まとめ
| オフィス形態 | 申請可否 | 主な理由 |
| バーチャルオフィス | ×不可 | 実態のある販売場が存在しない為 |
| シェアオフィス | △条件付き | 固定席・鍵付き個室なら可能性あり |
| レンタルオフィス | ○可能 | 通常のオフィスと同等の扱い |
酒類販売業免許の取得には、オフィスの「実態」が何よりも重要です。住所だけで選ぶのではなく、税務署が求める場所的要件を満たしているかを事前に確認しましょう。疑問がある場合は、税務署の酒類指導官や専門の行政書士に相談するとよいでしょう。
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。