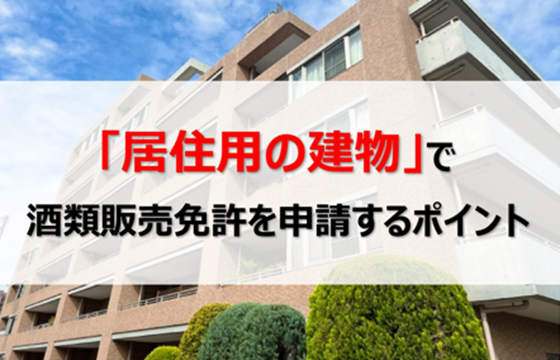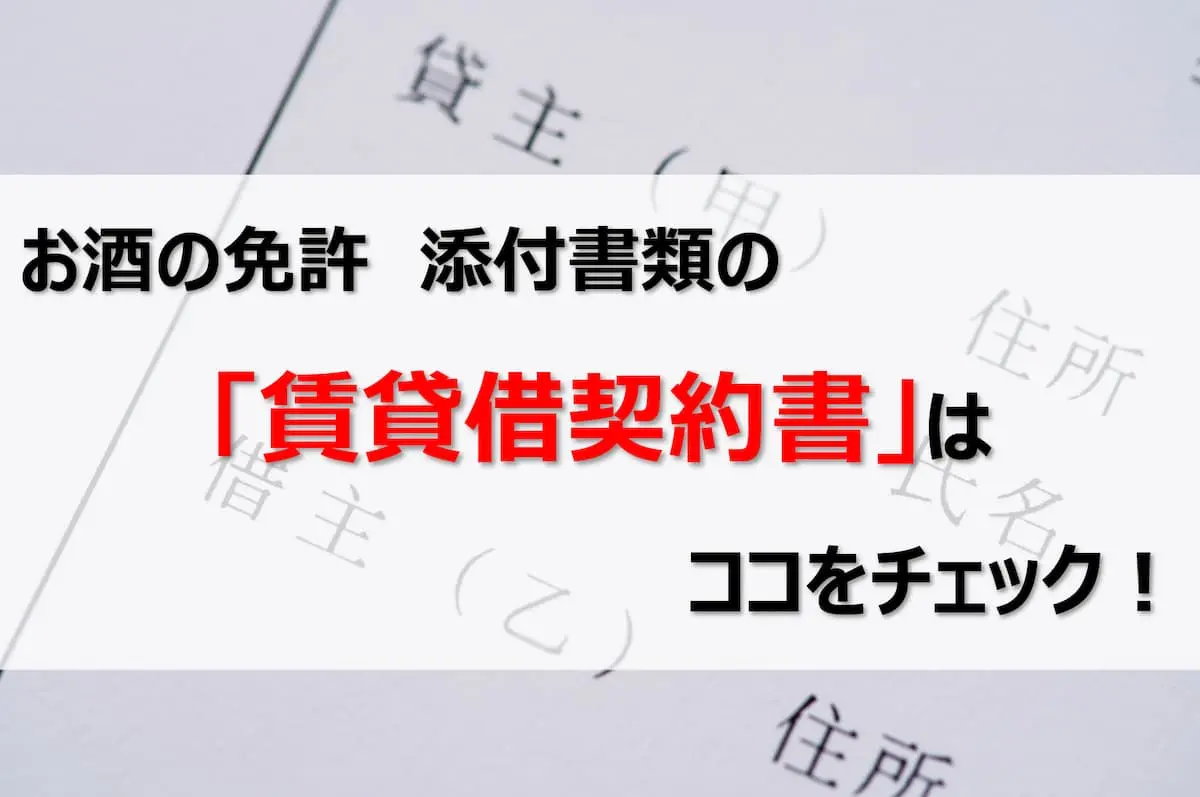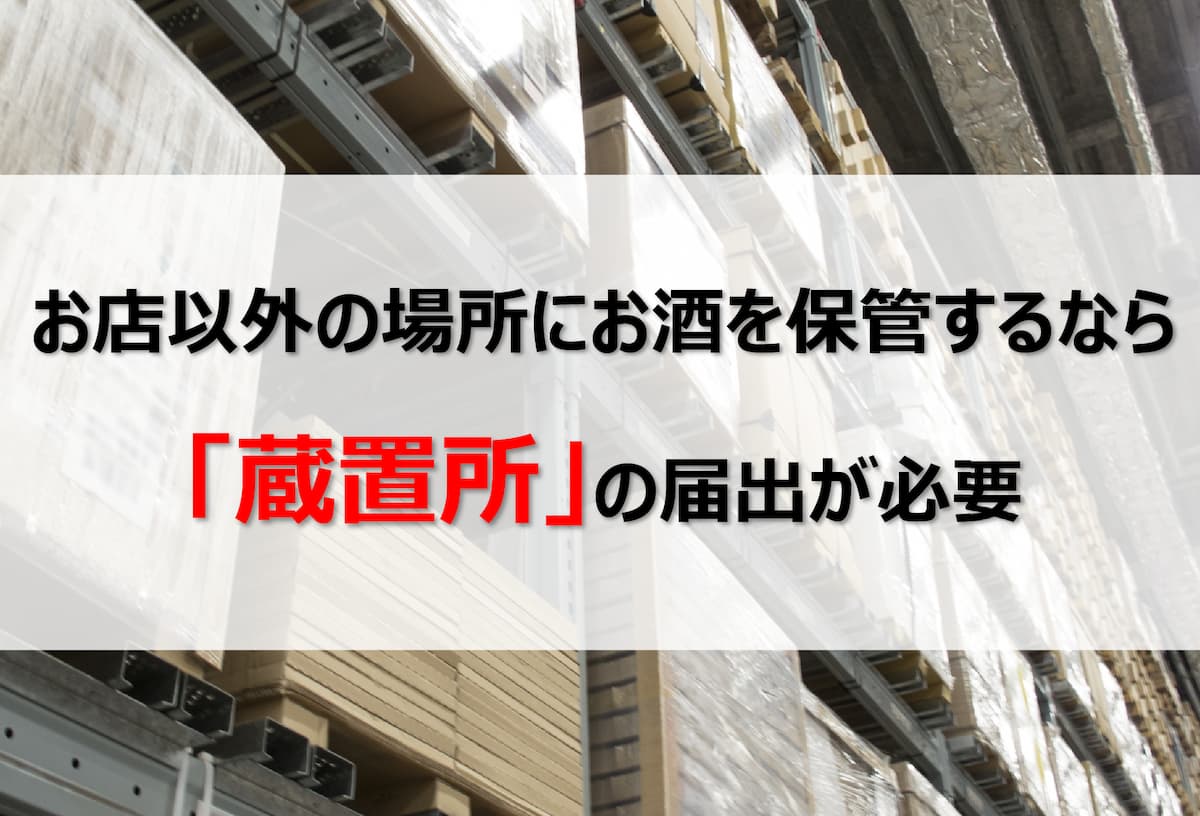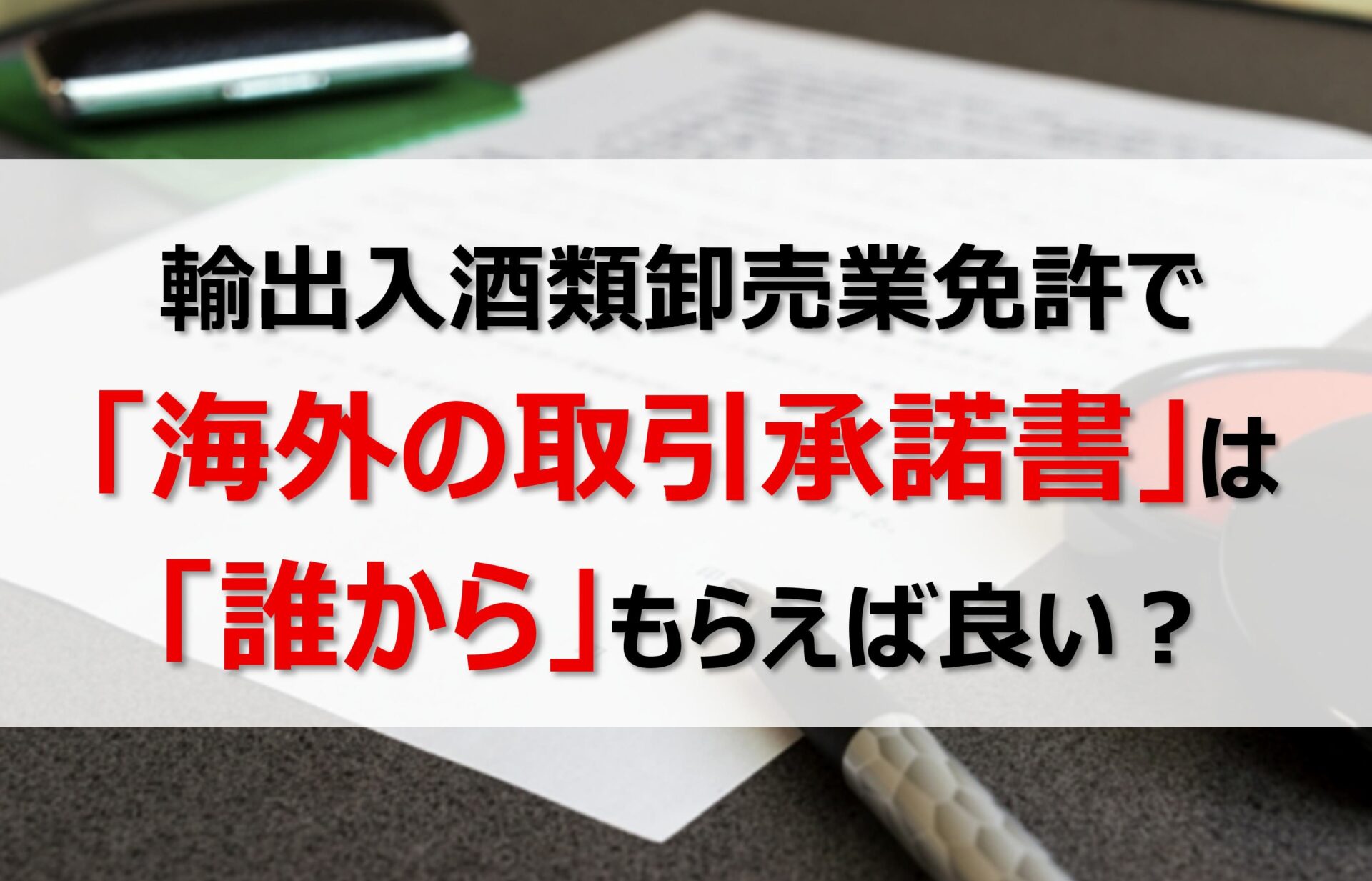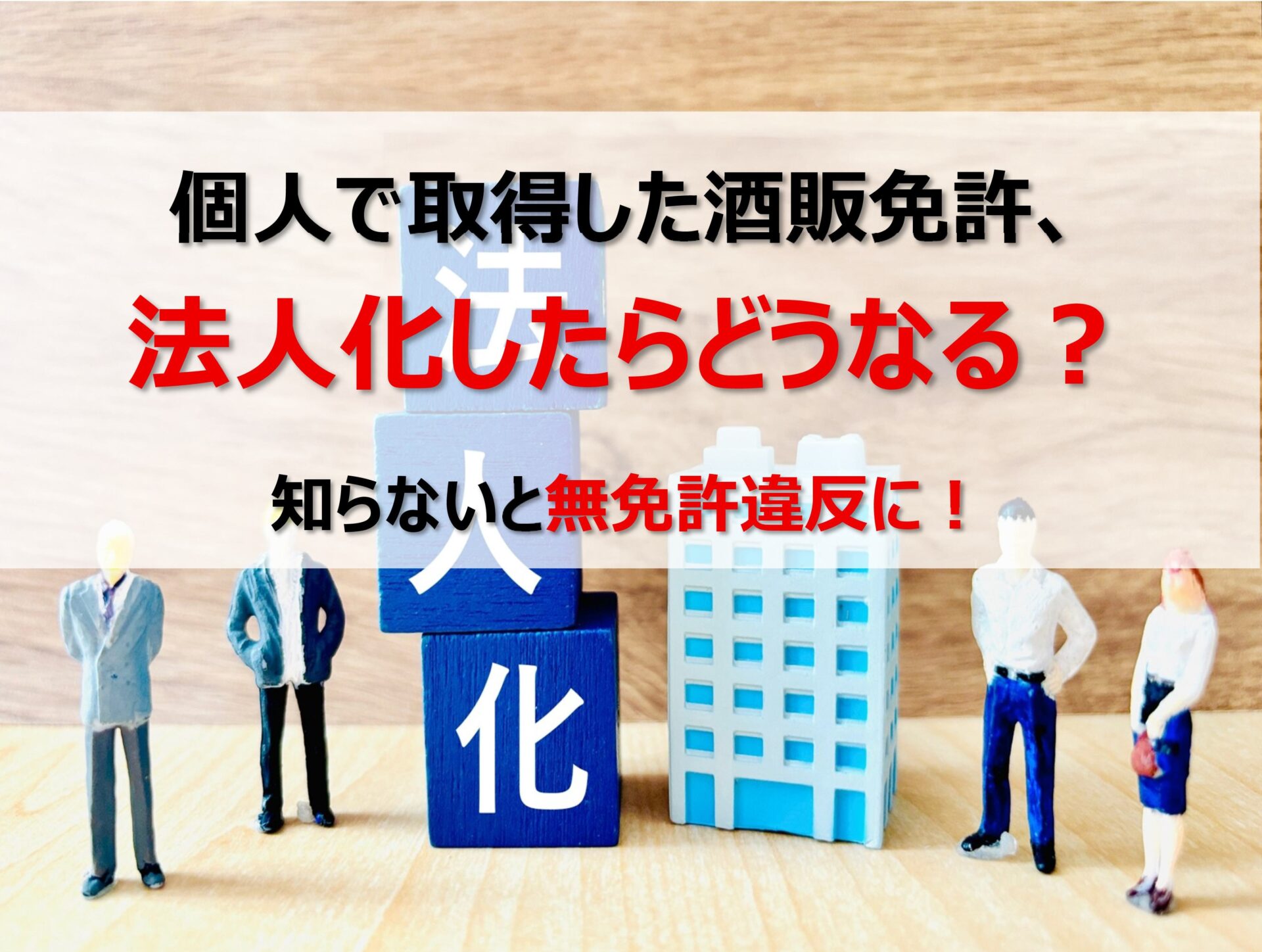お店で販売しないのに「販売場」が必要? 酒類販売業免許でよくある誤解
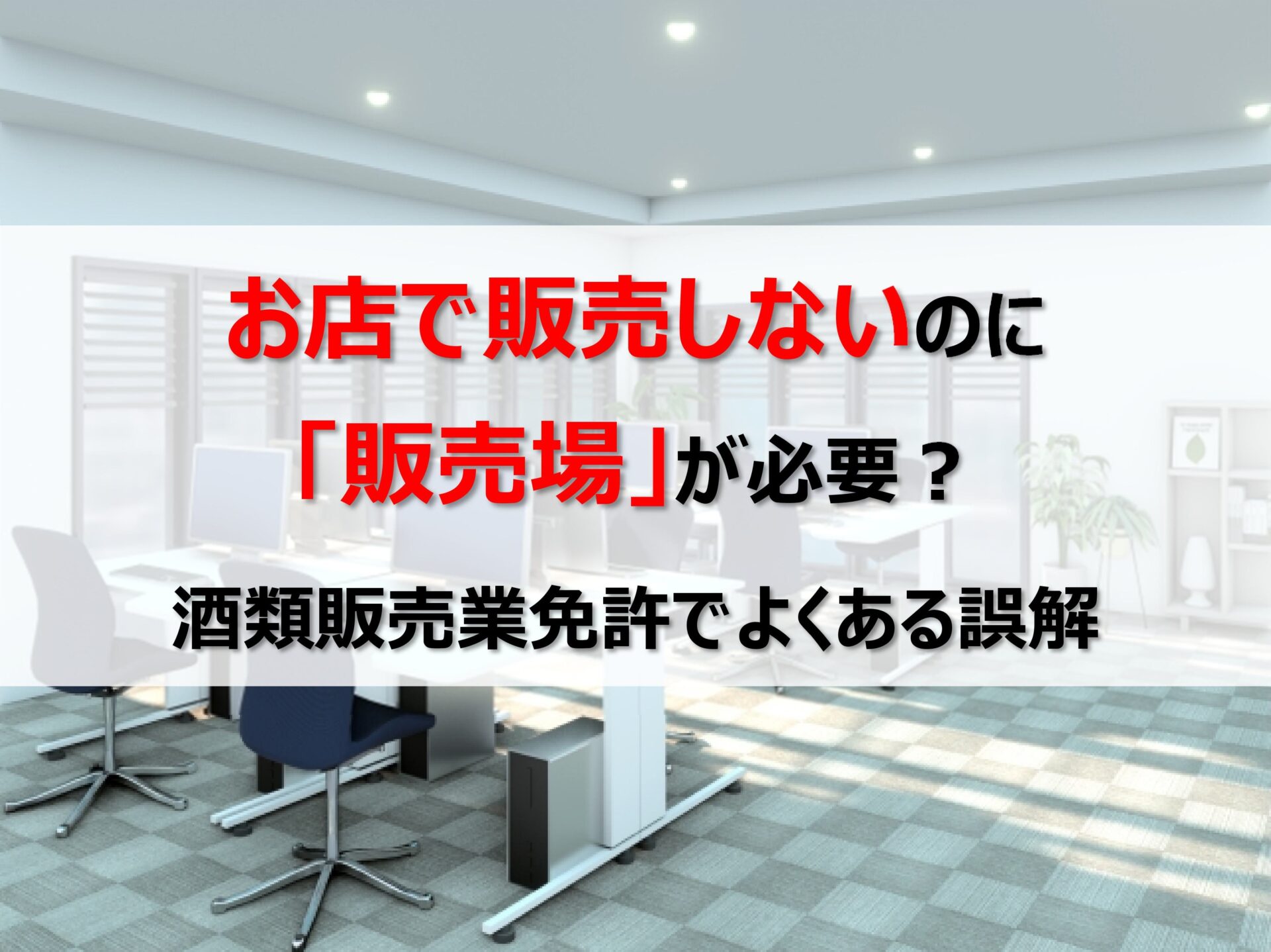
お酒の通信販売や海外輸出を目的として、酒類販売業免許の取得を検討する法人が増えています。そのような中でよく混乱が生じるのが、「販売場」という言葉の意味です。
「実際に店舗で販売しないのに、販売場は必要なのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、販売場は“お店”そのものを指すとは限らず、申請上とても重要な意味を持っています。
この記事では、酒類販売業免許の申請でよくある「販売場」に関する誤解について、よくある相談事例も紹介しながらわかりやすく解説いたします。
目次
そもそも「販売場」って何?
酒類販売業免許における「販売場」とは、「お酒の販売事業を行う拠点となる場所」のことを指します。
店舗を構えて店頭販売を行う場合は、商品の陳列や保管、来店客への販売を行う「店舗」が販売場となります。
一方、店舗を持たずにお酒の販売事業を行う場合は、お酒の受発注業務を行う「事務所」などが販売場となります。つまり、仕入先への発注や、お客様からの注文受付など、お酒の販売に関する業務を行う場所を「販売場」と呼ぶのです。
酒類販売業免許は「販売場」という「場所」に与えられる
酒類販売業免許は、「法人」や「個人」の本社住所に与えられるのではなく、お酒の販売を行う「場所」に対して与えられます。そのため、“免許を持っていればどこでもお酒を販売できる”ということはありません。酒類販売業免許を取得した場所、すなわち税務署から許可が下りた「販売場」においてのみ、お酒の販売事業を行うことができます。
たとえ在庫を持たず、メーカーや卸業者から購入者へ直接配送する形式であっても、お酒の販売事業を行うためには、免許を取得する「販売場」が必須なのです。
販売場、どこにする? よくある相談事例
販売場を決めるにあたって、よくご相談いただく事例をご紹介します。
- 法人の本店所在地がバーチャルオフィスなのですが、申請できますか?
バーチャルオフィスは事務所としての実体がないため、販売場にすることはできません。
しかし、販売場の住所は、本社の住所と一致している必要はありません。法人の本店所在地がバーチャルオフィスであっても、別途、実体のある事務所を用意すれば申請可能です。
- 自宅で申請できますか?
自宅の一部を販売場として申請することは、条件を満たせば可能です。下記コラムで詳しく解説しておりますので、該当する方は合わせてご確認ください。
▼こちらの記事も合わせて読みたい▼
▼こちらの記事も合わせて読みたい▼
- 事務所と倉庫があるのですが、どちらで申請すればいいですか?
お酒の受発注業務を事務所で行う場合は、事務所が販売場となります。なお、お酒の在庫を倉庫に保管するのであれば、別途、倉庫について「蔵置所」という届出が必要になります。
倉庫に事務所機能が備わっていて、倉庫にてお酒の受発注業務を行う場合は、倉庫が販売場となります。
▼こちらの記事も合わせて読みたい▼
酒類販売業免許の取得には、販売場の用意が必須となります。販売場にしたい場所が申請要件を満たしているかどうか判断に迷う場合は、税務署の酒類指導官または専門の行政書士に相談するとよいでしょう。
まとめ
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。