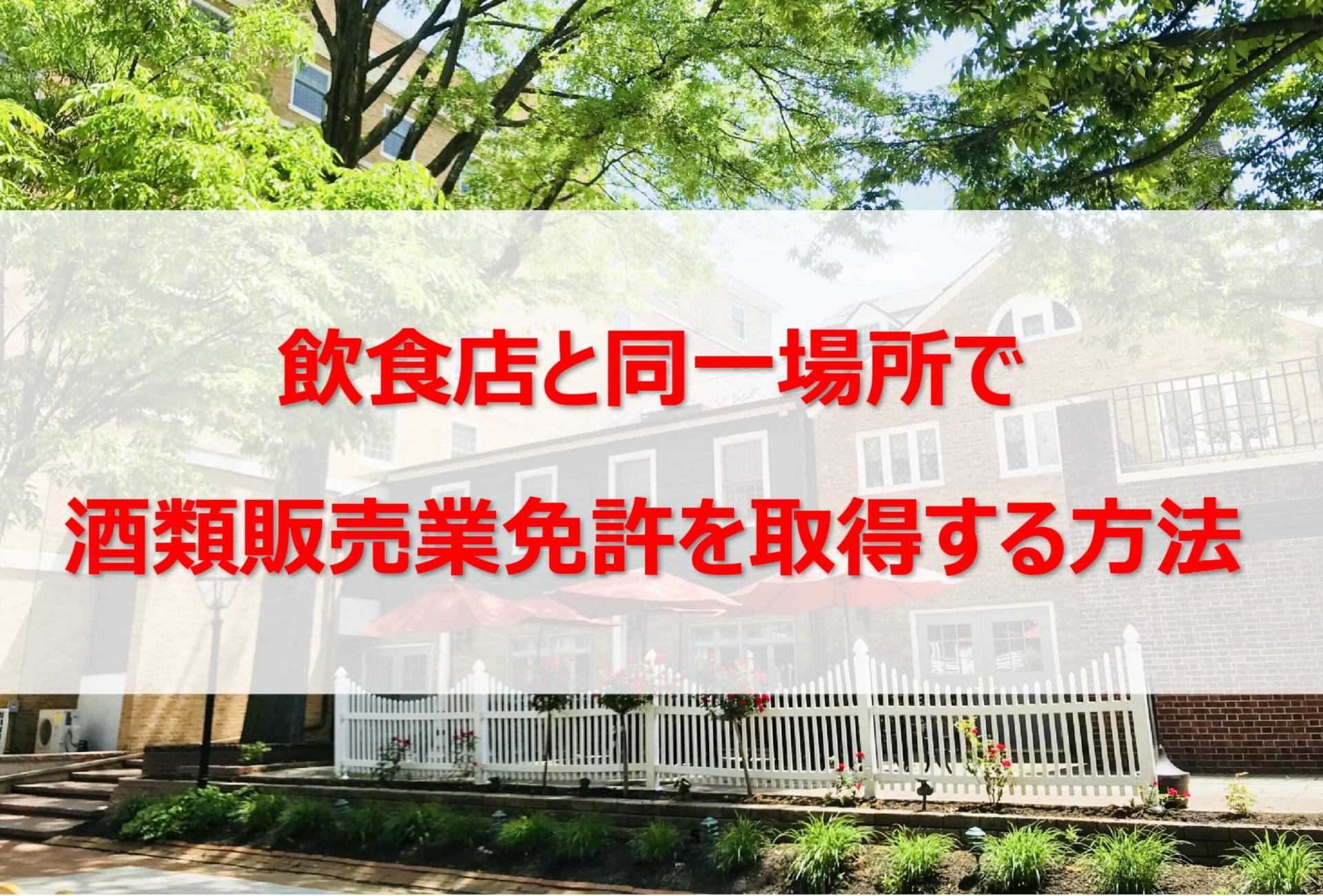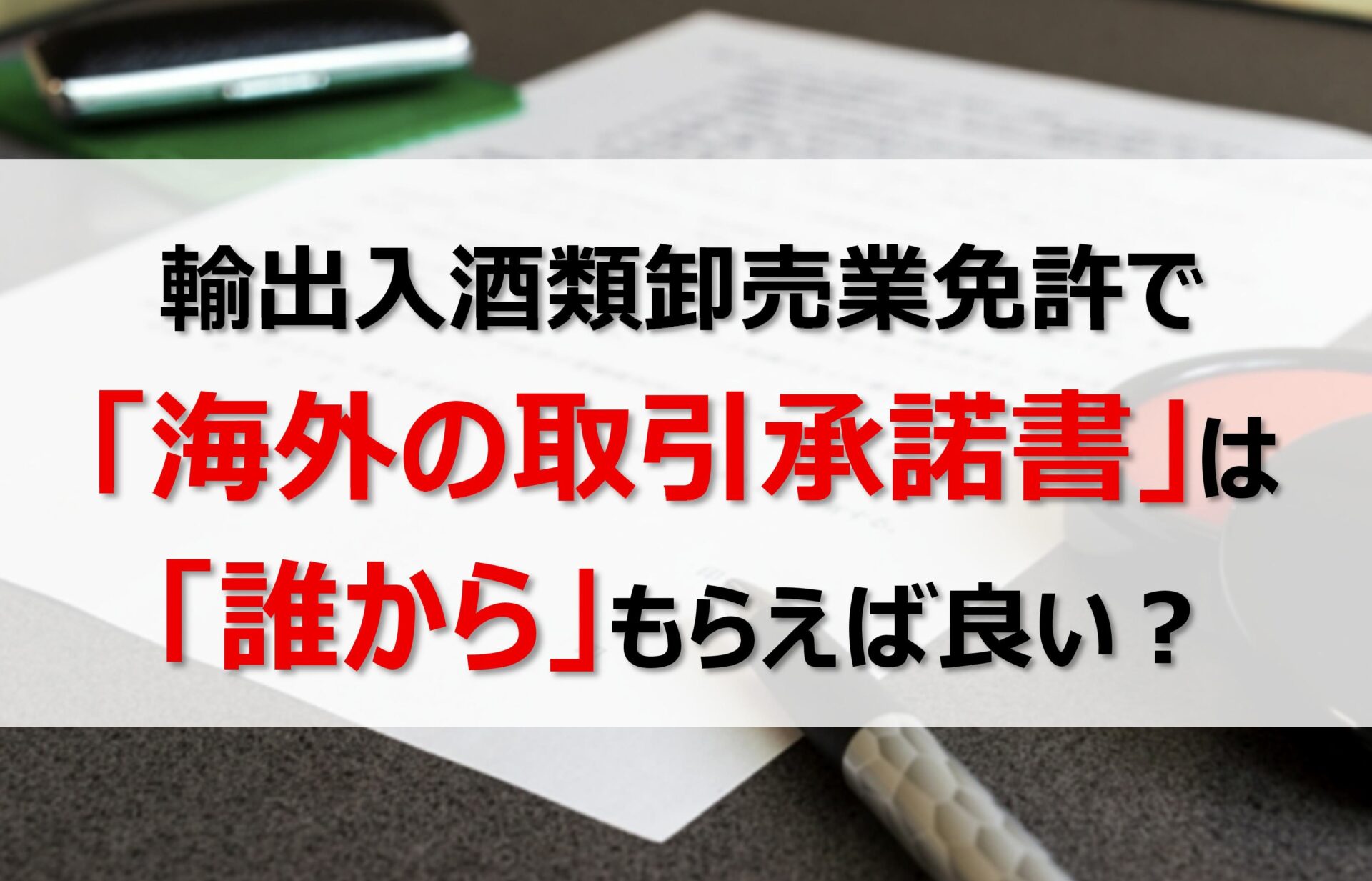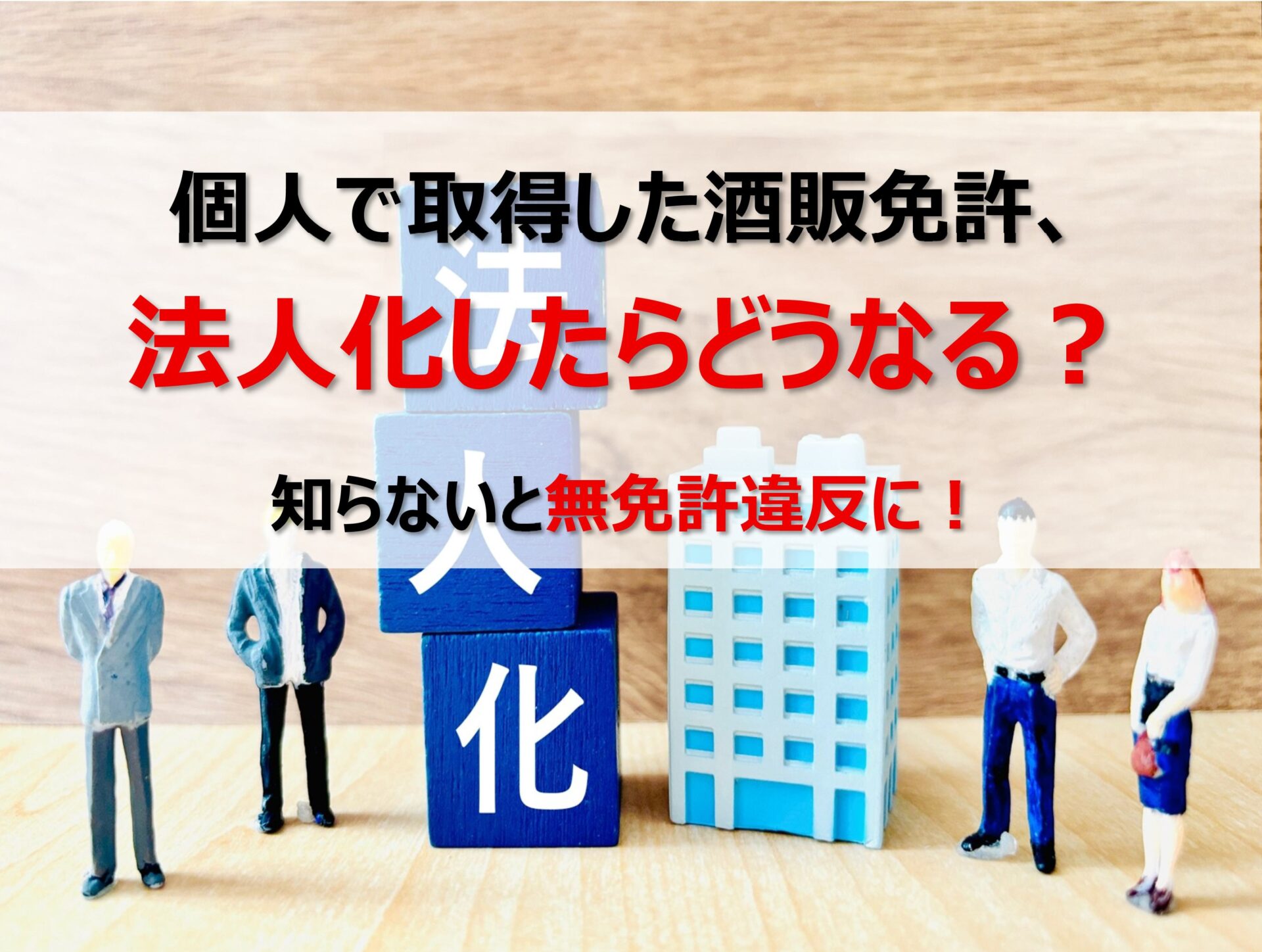お祭りやイベントでビールを売るには、お酒の販売免許は必要?
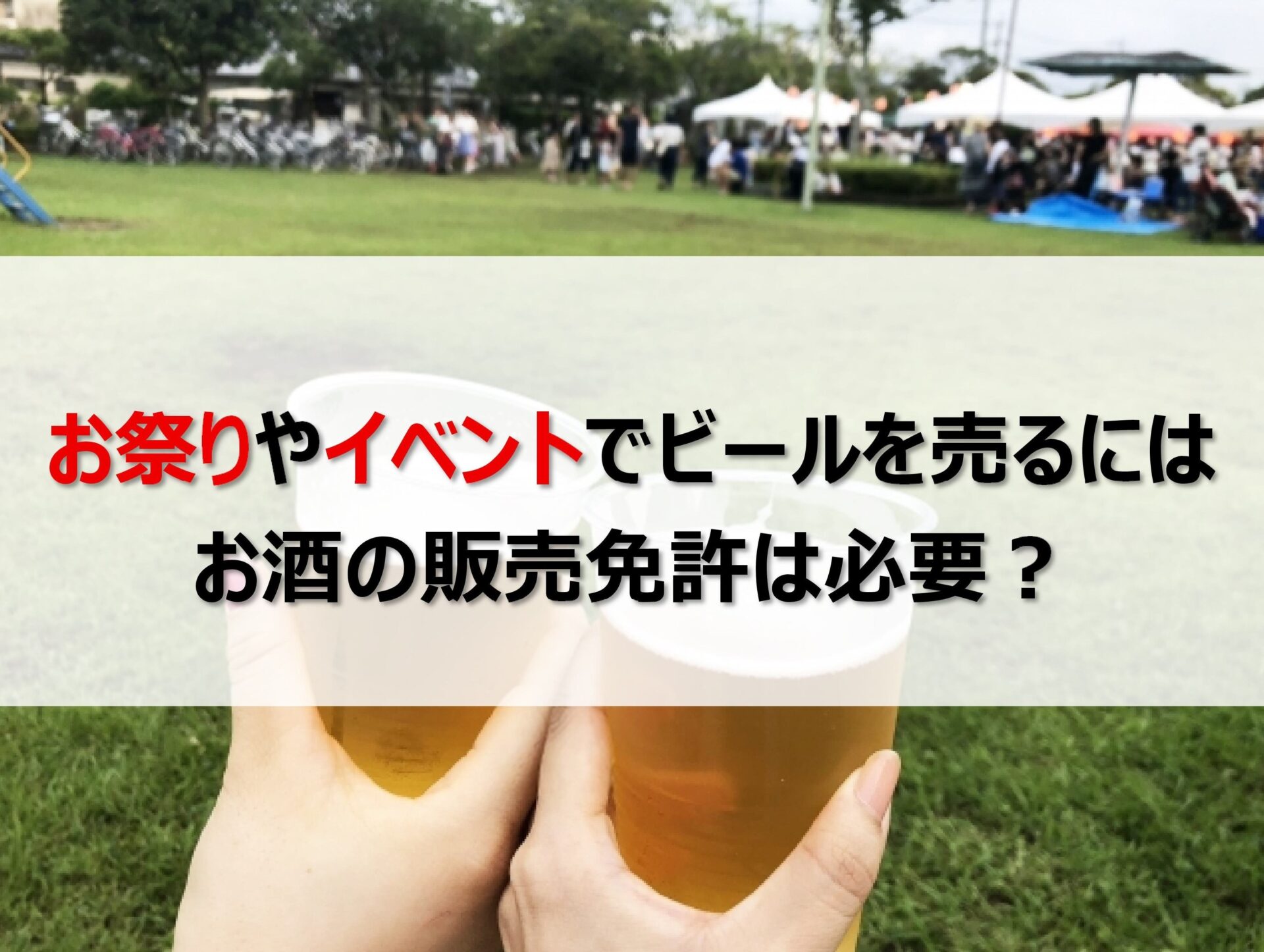
お祭りやイベントでビールを販売するとき、免許や許可は必要なのでしょうか。実は販売方法によって求められる手続きが変わるため、迷う方が少なくありません。
お酒の販売にあたっては、酒税法、食品衛生法、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律 など、複数の法律があり、販売方法によって酒類販売業免許が必要な場合や飲食店営業許可が必要な場合があります。この記事では、販売方法による手続きの違いを解説します。
目次
持ち帰り販売は「期限付酒類小売業免許」が必要
イベント等で、酒類を持ち帰り販売する場合、「期限付酒類小売業免許」が必要です。たとえば未開封の瓶ビールなど、購入後に持ち帰ることができる販売方法がこれに該当します。
なお、「期限付酒類小売業免許」を申請するためには、すでに酒類販売業免許もしくは酒類製造免許を取得している酒類取扱業者であることが前提です。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
その場で飲ませる提供方法なら「期限付酒類小売業免許」は不要
一方、会場内で飲ませる提供方法なら「期限付酒類小売業免許」は不要です。
ビールをコップに注いで販売する、ワインをグラスで提供するといった形式がこれに当たります。
「酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業を行う場合には、販売業免許は必要ありません」
「祭りの会場においてビール等コップに注ぐなど、その場で酒類を提供するような場合は、販売業免許は必要ありません。」
期限付酒類小売業免許が不要な場合でも、食品衛生法に基づく飲食店営業許可等が必要となることがあります。また、イベント主催者が手続きをしている場合もあるため、事前に必ず主催者や保健所に確認しましょう。
販売方法によって必要な免許と許可の違い
| 販売方法 | 期限付酒類小売業免許 | 飲食店営業許可 |
| 持ち帰り販売 | 〇 | × |
| その場で飲ませる提供方法 | × | 〇 |
| 両方行う場合 | 〇 | 〇 |
上の表の通り、販売方法によって必要な免許や許可が変わってきます。
期限付酒類小売業免許が必要かどうかは税務署の酒類指導官や専門の行政書士へ、飲食店営業許可が必要かどうかは、管轄の保健所に相談するとよいでしょう。
その他ポイント
・20歳未満の者への提供は、「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」違反となり、罰則の対象です。必ず年齢確認を実施しましょう。
・持ち帰り販売とその場で飲ませる提供方法を両方行う場合は、販売用のお酒と飲食提供用のお酒を仕入れから売上まで明確に分ける必要があります。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
まとめ
・持ち帰り販売は「期限付酒類小売業免許」が必要
・その場で飲ませる提供方法なら「期限付酒類小売業免許」は不要
・期限付酒類小売業免許が不要な場合でも、食品衛生法に基づく飲食店営業許可等が必要となることがある
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。