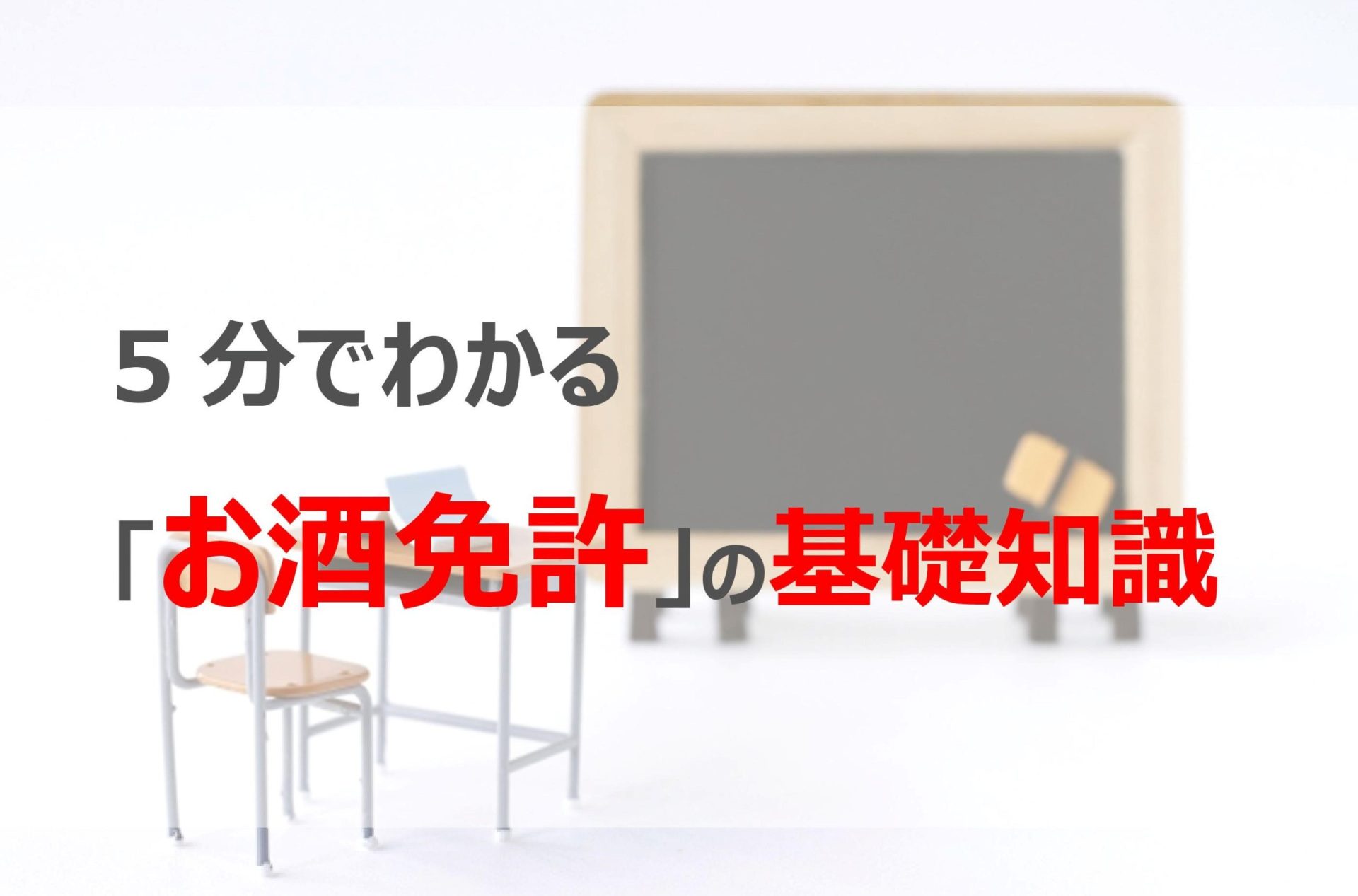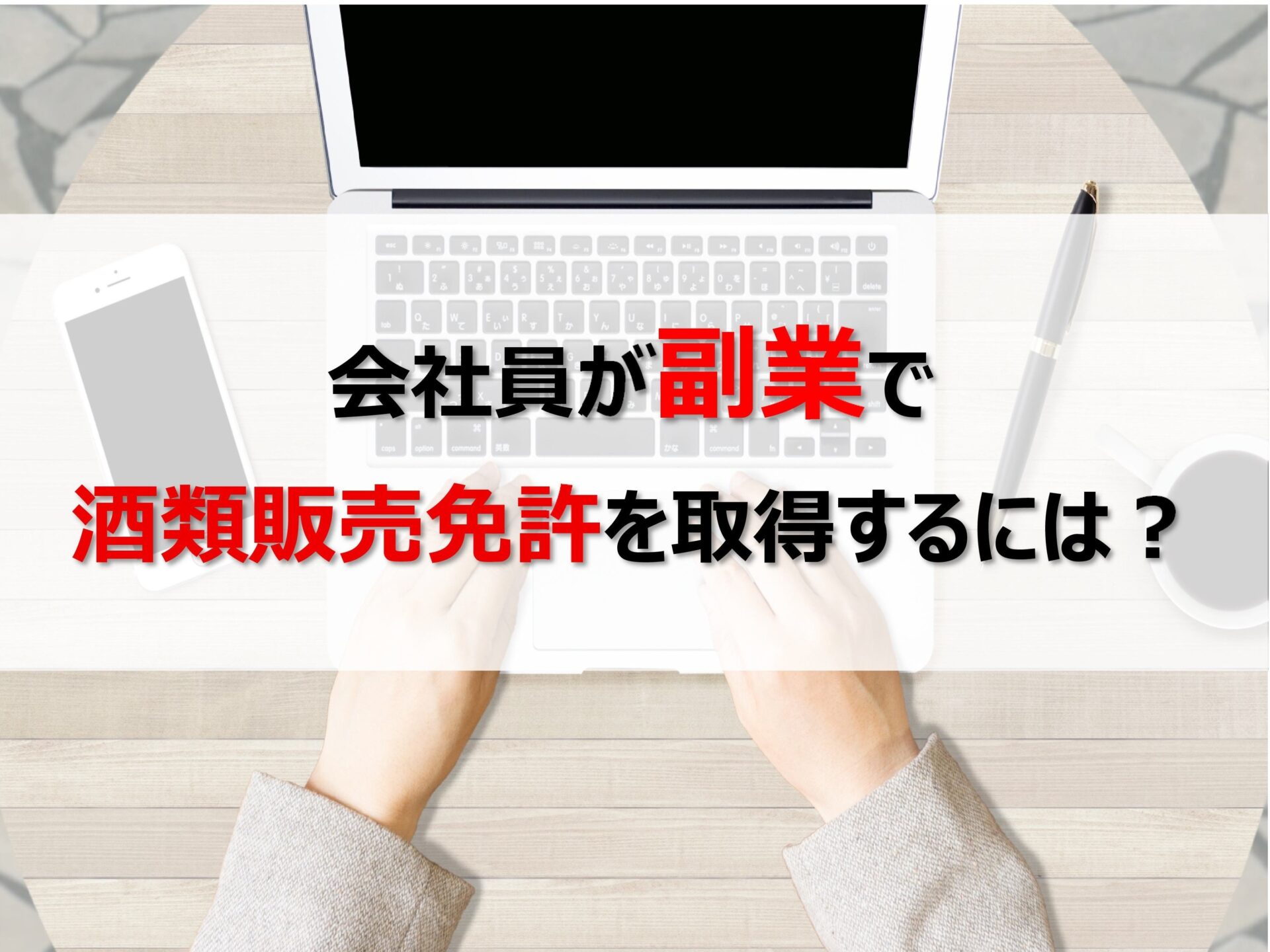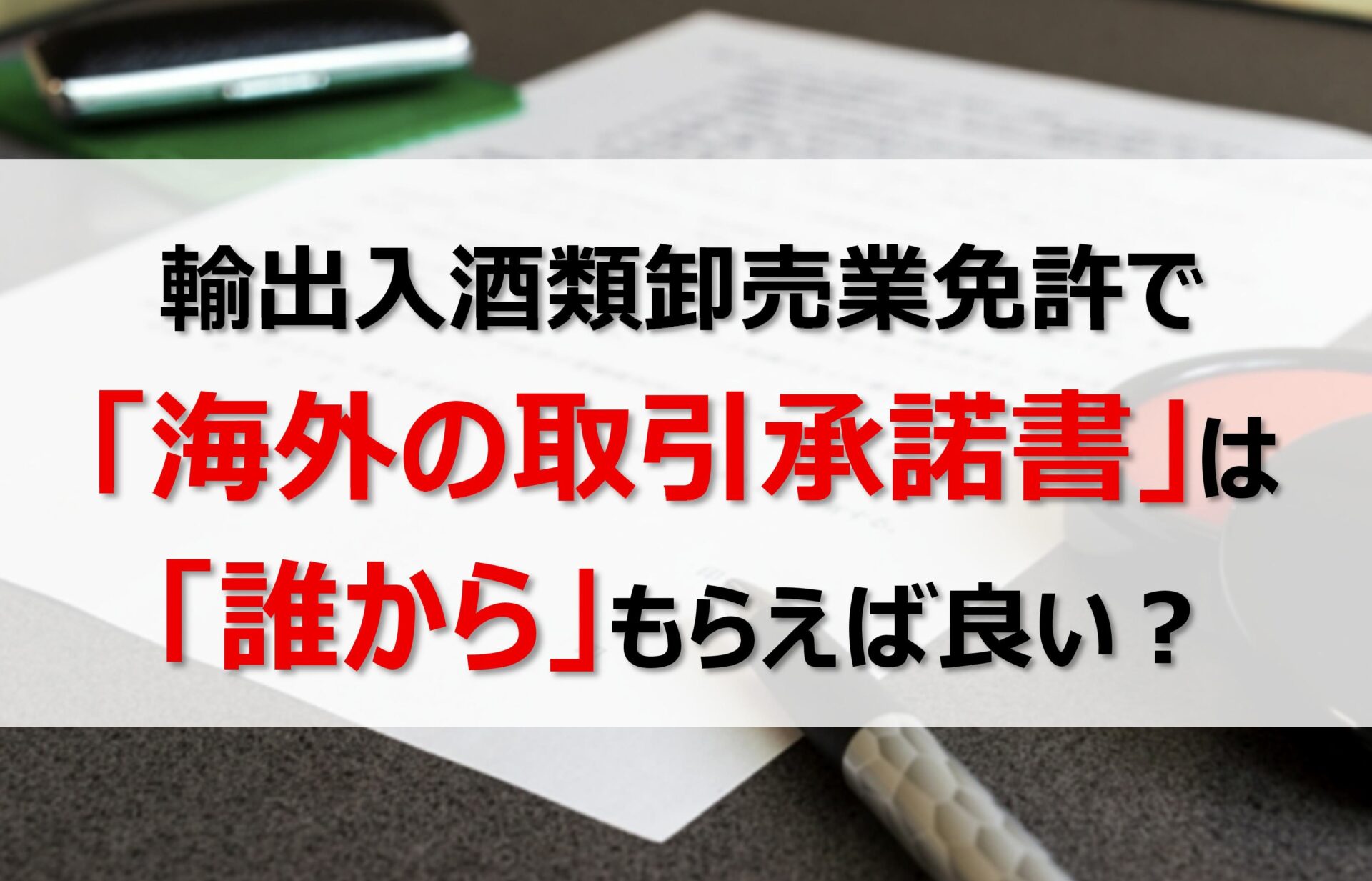委託製造(OEM)したオリジナルのお酒を販売するには どんなお酒の免許が必要?
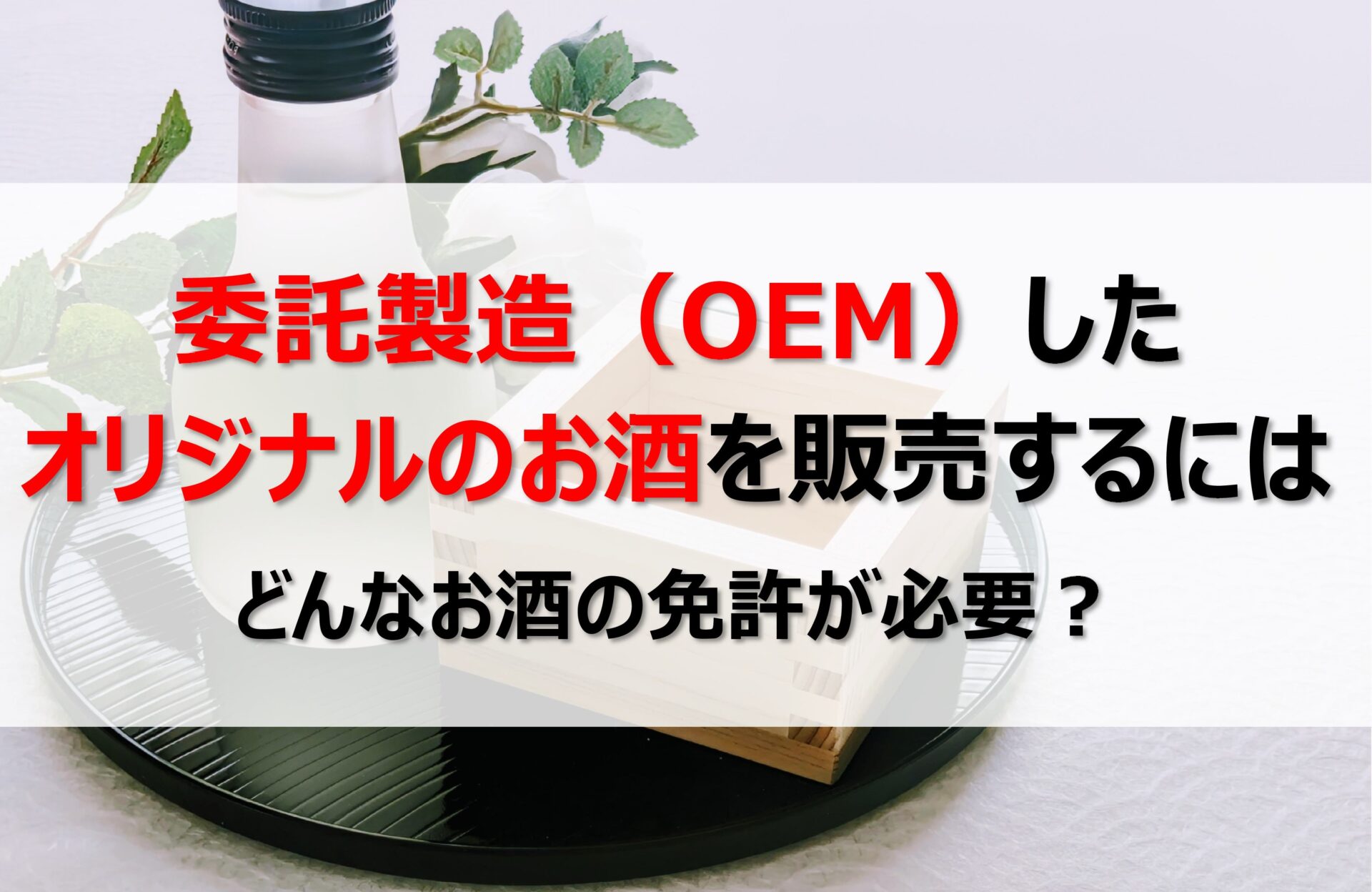
「オリジナルの日本酒やクラフトビール、ワインをOEM製造で作り、自社ブランドとして販売したい」――そんな企業や事業者が増えています。
オリジナルのお酒を売るためにはどんな免許が必要なんだろう?と悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、オリジナルのお酒を販売する際に必要な「酒類販売業免許」の種類をケース別に解説します。
目次
委託製造(OEM)なら「製造免許」は不要
まず、OEMでは製造を酒蔵やメーカーに委託するため、自社で「製造免許」を取得する必要はありません。
その代わりに、完成したお酒を消費者や事業者に販売するには必ず「酒類販売業免許」が必要になります。
酒類販売業免許は「誰に」「どのようなお酒を」「どのような方法で」販売するかによって必要な免許の種類が分かれます。
販売形態に応じて適切な酒類販売業免許を取得しましょう。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
オリジナルのお酒を売るときに必要な3つの免許
オリジナルのお酒を販売する場合必要となる3つの免許をケースごとに紹介します。
ケース1:小売店などの店舗で消費者に対面販売する場合
「一般酒類小売業免許」が必要です。
この免許は、オリジナルのお酒に限らず原則としてすべての品目の酒類を販売(小売)することができる販売業免許です。また、飲食店への販売もこの免許で可能です。
飲食店は「一般消費者」と同様に扱われるため、卸売業免許は不要です。ただし、酒類販売業者(酒屋など)や酒類製造業者に対して販売する場合には、「酒類卸売業免許」が必要になるため注意が必要です。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
ケース2:ECサイトやカタログで全国の消費者に通信販売する場合
「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
自社のECサイトやカタログなどでオリジナルのお酒を消費者に通信販売したい場合に必須の免許です。
こちらも一般酒類小売業免許と同様、免許条件の範囲内であればオリジナルのお酒に限らず販売することが可能です。ただし、大手の国産メーカー(年間の課税移出数量が3,000kℓ以上)が製造する酒類については、通信販売をすることができません。
そのため、委託製造(OEM)先が該当する大手メーカーである場合は、事前に販売可否を確認するなど、十分な注意が必要です。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
ケース3:オリジナルのお酒を酒販店へ卸売する場合
「酒類卸売業免許」が必要です。
酒類卸売業免許には複数の区分(全部で8種類)がありますが、オリジナルのお酒を卸売する場合、「自己商標酒類卸売業免許」が該当します。
自己商標酒類卸売業免許とは、「自己(自社)が企画・開発した商標または銘柄のお酒」に限り卸売できる免許で、扱えるお酒の品目に制限はありません。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
まとめ
委託製造(OEM)を活用すれば、製造免許を持たなくてもオリジナルのお酒を販売することができます。
ただし販売するためには販売形態に応じて適切な酒類販売業免許を取得することが必要です。
- 店舗販売 → 一般酒類小売業免許
- 通信販売 → 通信販売酒類小売業免許
- 卸売販売 → 自己商標酒類卸売業免許
「どの免許が必要なのか判断が難しい」「複数チャネルを組み合わせて販売したい」という場合は、税務署の酒類指導官や専門の行政書士に相談するとよいでしょう。
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。