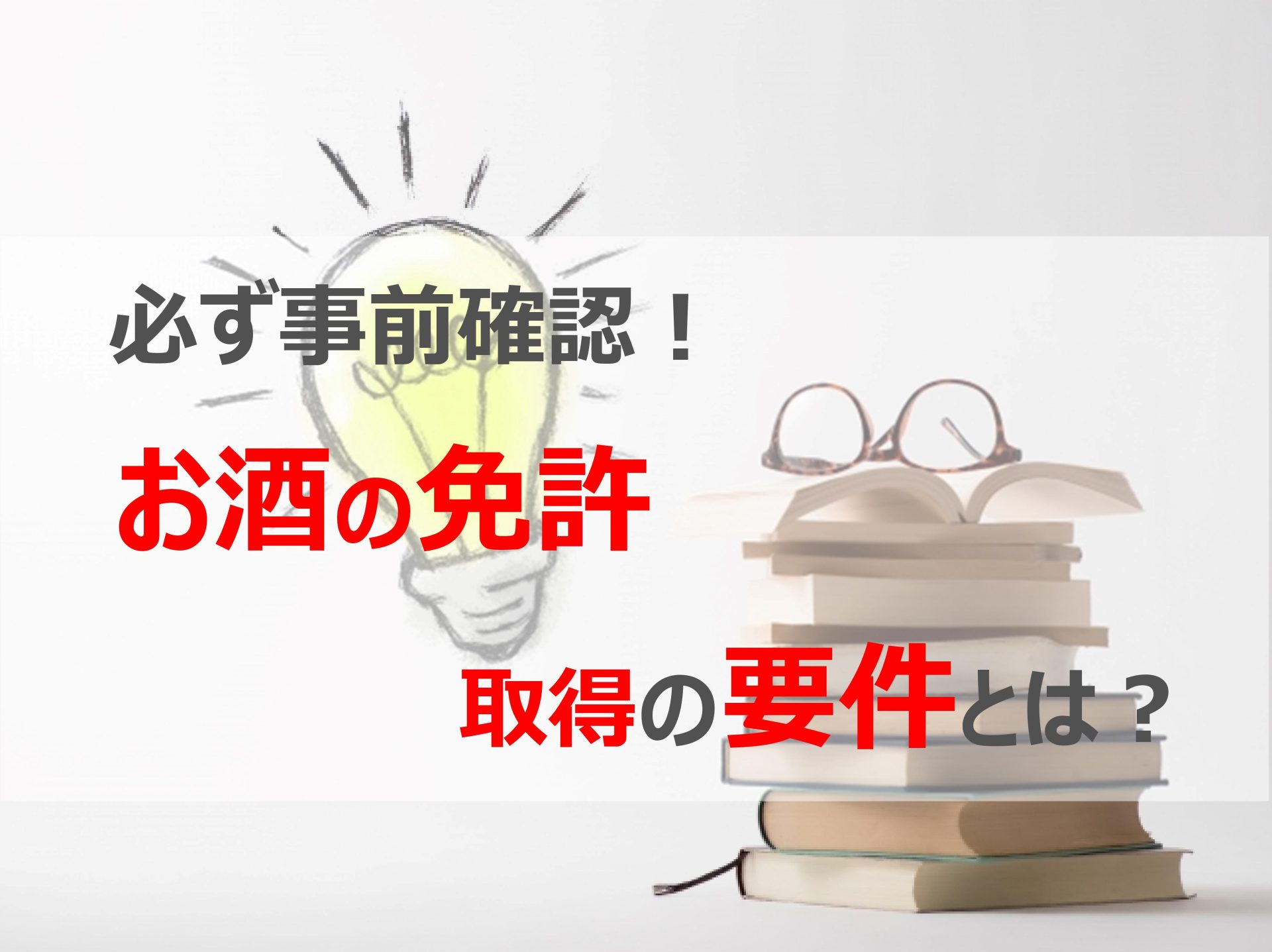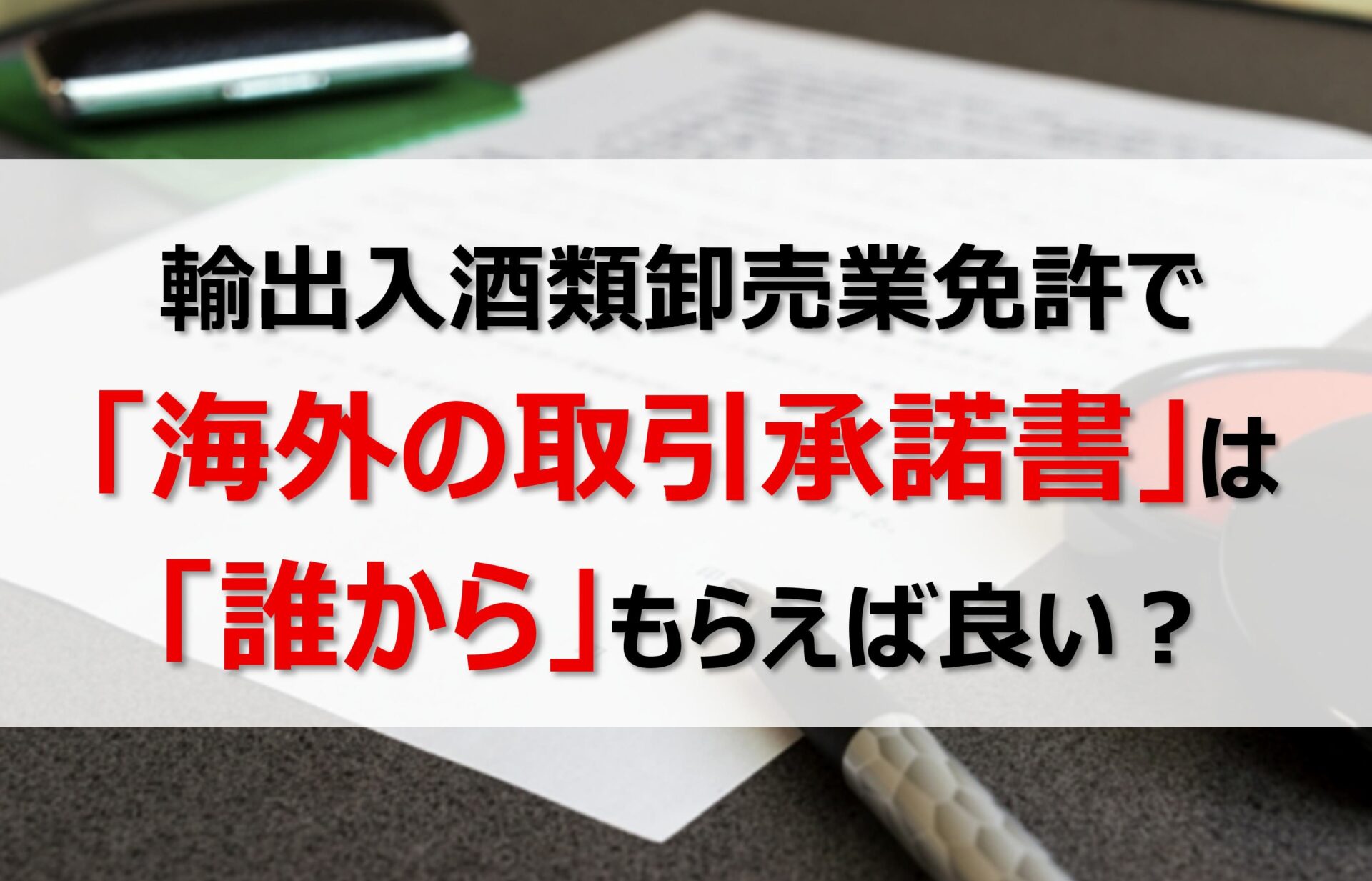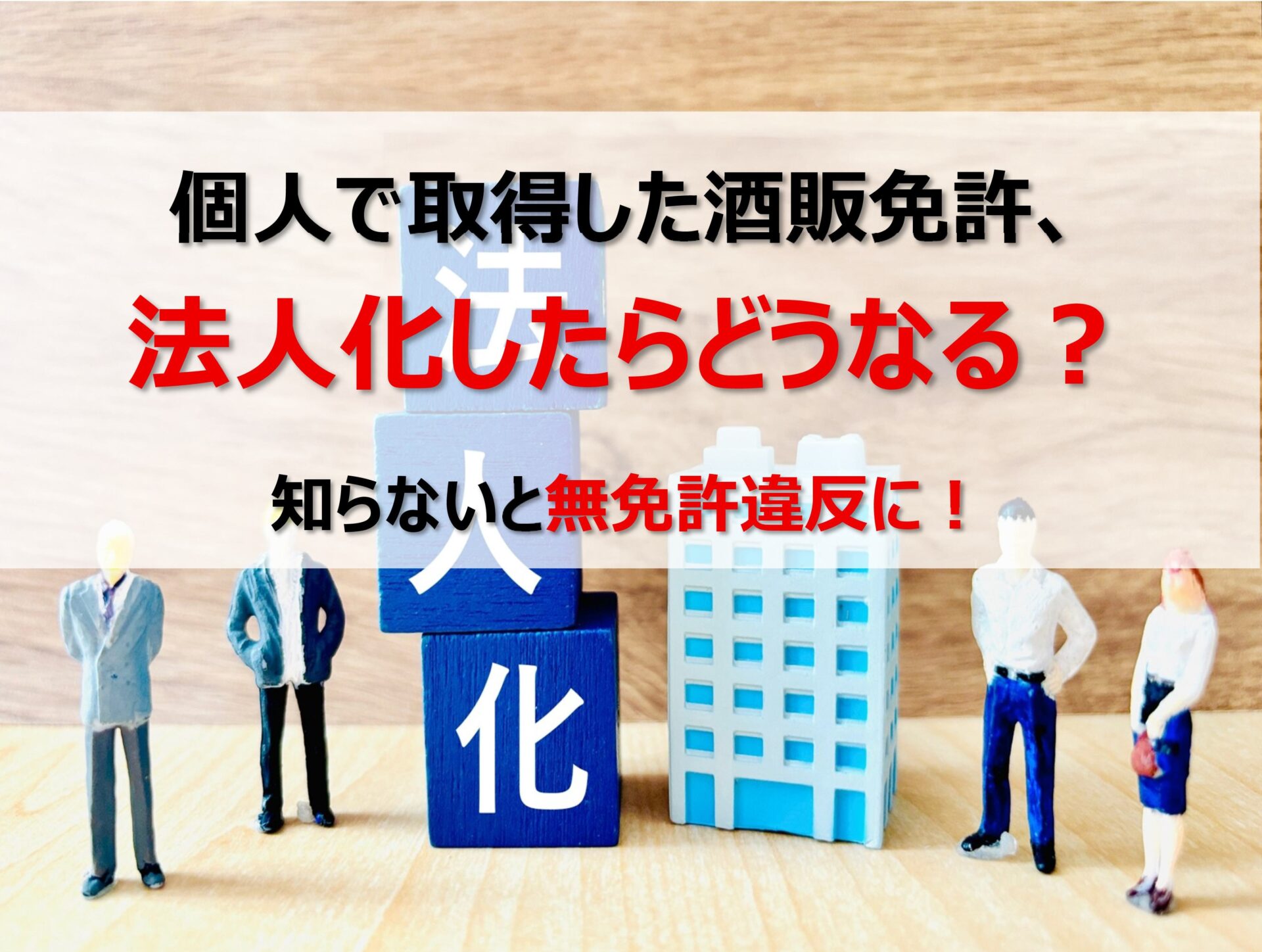酒類販売業免許申請に必要な「履歴書」を書く際のポイント
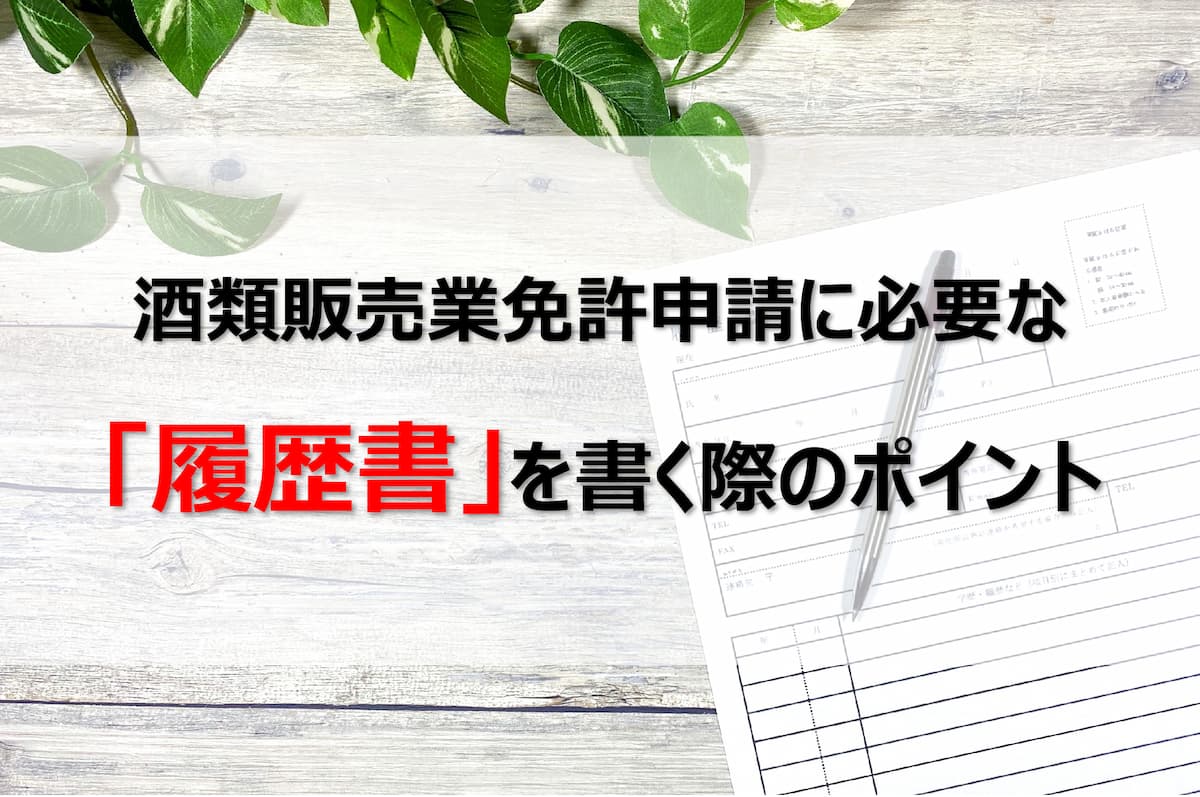
お酒の免許の審査には大きく4つの要件があります。そのうちの1つである「経営基礎要件」は、資金、経営状況等について、免許を付与するにふさわしいかを判断する基準をいいます。審査では、「経営の基礎が貧弱であると認められる場合」に該当しないかを審査されます。
酒類販売業免許申請では「経営の基礎が貧弱 ではないか」を審査するため、「申請者の履歴書」の提出がもとめられます。
お酒の販売を行うにあたって十分な知識や能力があるかを見られることになるため、職歴をしっかり書いてアピールするとよいでしょう。
目次
法人なら役員全員分の履歴書を準備
酒類販売業免許を申請する際に提出する「申請者の履歴書」。
個人の場合は、申請者の履歴書を提出しますが、法人で申請をする場合は、役員全員分の履歴書を提出する必要があります。ここで言う「役員」とは、法人の履歴事項全部証明書(法人登記簿)の「役員に関する事項」に記載されている役員のことです。代表取締役、取締役のほか、監査役等も記載されている場合は、それらすべての人の履歴書を準備しましょう。
職歴をしっかり書いて経験をアピールしましょう
酒類販売業免許の審査では、申請者に「酒類販売業を経営する十分な能力」や「適正な酒類販売を行える知識」があるかどうかが問われます。経営能力や知識を判断する材料となるのが申請者の職務経験です。求められる経験内容は、免許の種類によって異なります。
例えば、一般酒類小売業免許の場合、お酒の製造業または販売業の経験が3年以上、もしくは何らかの経営経験が必要になります。
全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許の場合はさらに経験年数が必要となり、ぐっとハードルがあがります。
履歴書に記載された職歴から、申請者の経営能力やお酒に関する知識を読み取ることになりますので、すべての職歴を記載するようにしましょう。複数の勤務経験がある場合、ひとつの会社での勤務年数では足りなくても、それぞれの勤務期間の通算で規定年数に達していれば、十分な経営能力や知識があると判断される場合もあります。また、ソムリエや利き酒師、ビアテイスターなどお酒に関する資格を持っている場合は、資格取得年月日と合わせて記入しておくとお酒の知識をアピールできます。
経営能力や知識が足りなくても、酒類販売管理研修の受講で補うことができる場合もあります。
▼こちらの記事もあわせて読みたい▼
経営経験や知識が十分と言えるか心配な人は、税務署の酒類指導官や専門特化した行政書士に相談してみるとよいでしょう。
無職の期間があっても大丈夫
事情があって無職の期間があった場合、審査担当者にその経緯がわかるように履歴書に記載しましょう。無職の期間があるからといって、それを理由に酒類販売業免許が取得できないということにはなりませんので安心してください。
履歴書のフォーマットは自由
酒類販売業免許の申請に使用する履歴書には決まった様式はありませんので、自分で用意する必要があります。
履歴書はどのようなものでも構いませんが、住所・氏名・生年月日・電話番号といった本人に関する情報と、経験をアピールするための職歴欄が入っているものを使いましょう。市販の履歴書やウェブ上のテンプレートを使う場合は、顔写真は貼る必要はありません。また、志望動機など免許申請とは無関係な欄は空欄のままで大丈夫です。
手書き・パソコン入力どちらでもいい?押印は必要?
酒類販売業免許の審査で見られるのはあくまでも経験内容ですので、履歴書は手書きの必要はなく、パソコン入力でも構いません。「役員の履歴書が必要だけれど、多忙なため本人に作成を依頼するのが難しい」という場合もあるでしょう。履歴書は内容が正しければ本人が作成しなくても構いませんし、本人の押印も不要です。
まとめ
- 法人で申請する場合、役員全員分の履歴書が必要
- お酒に関する知識や経営能力などの経験をアピールするものなので、職歴はすべて記入しましょう
- 履歴書のフォーマットは自由
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。