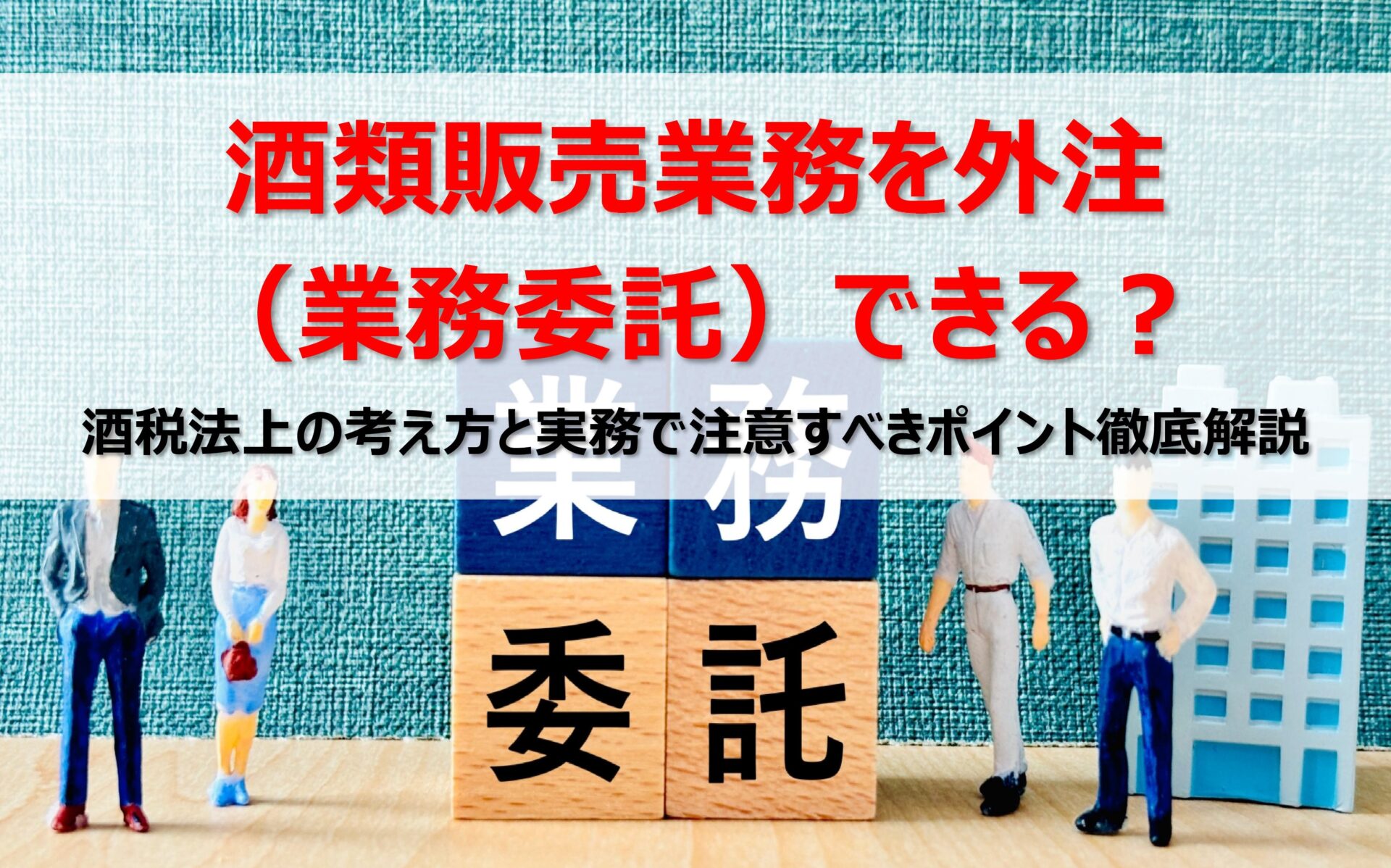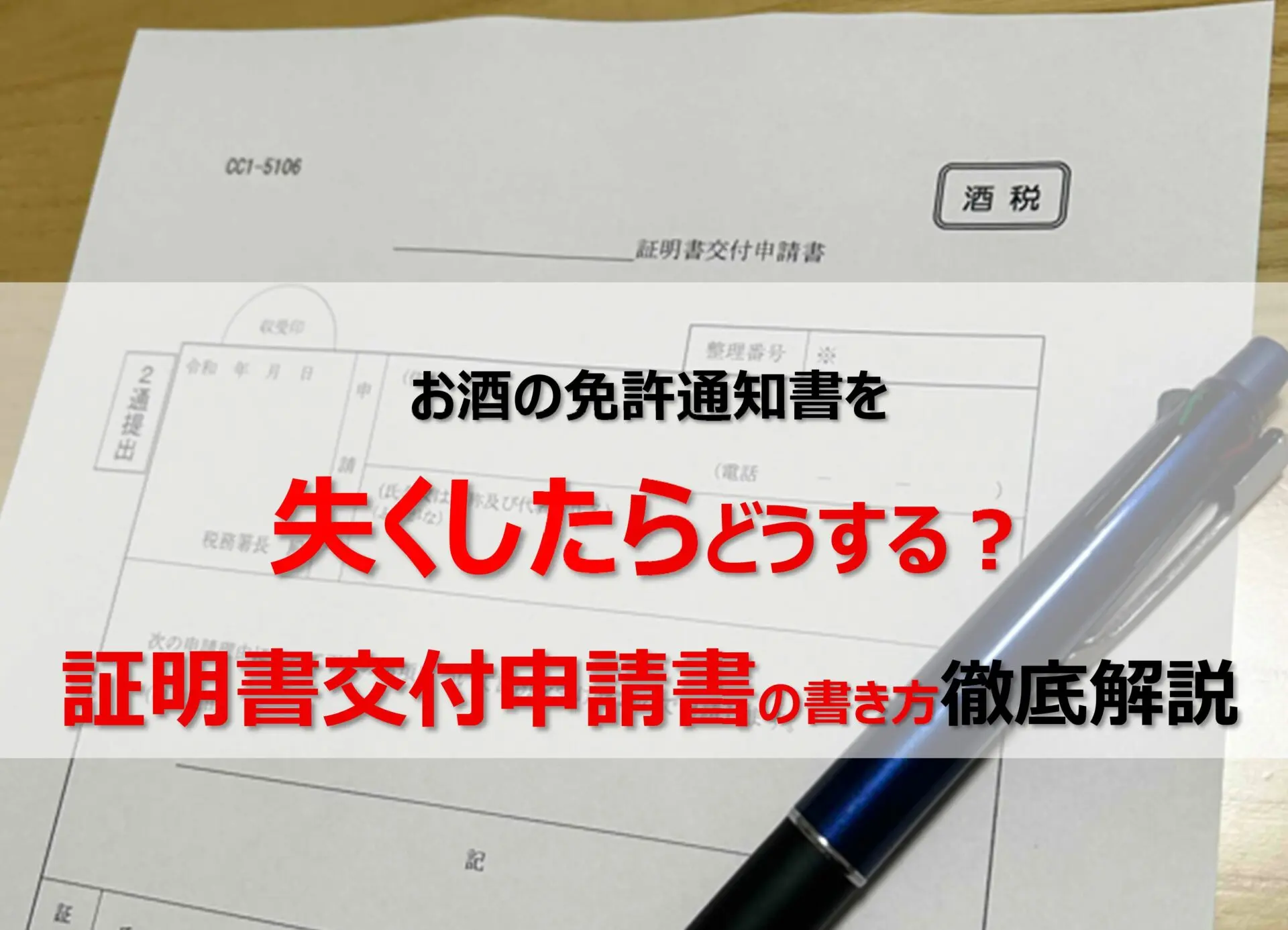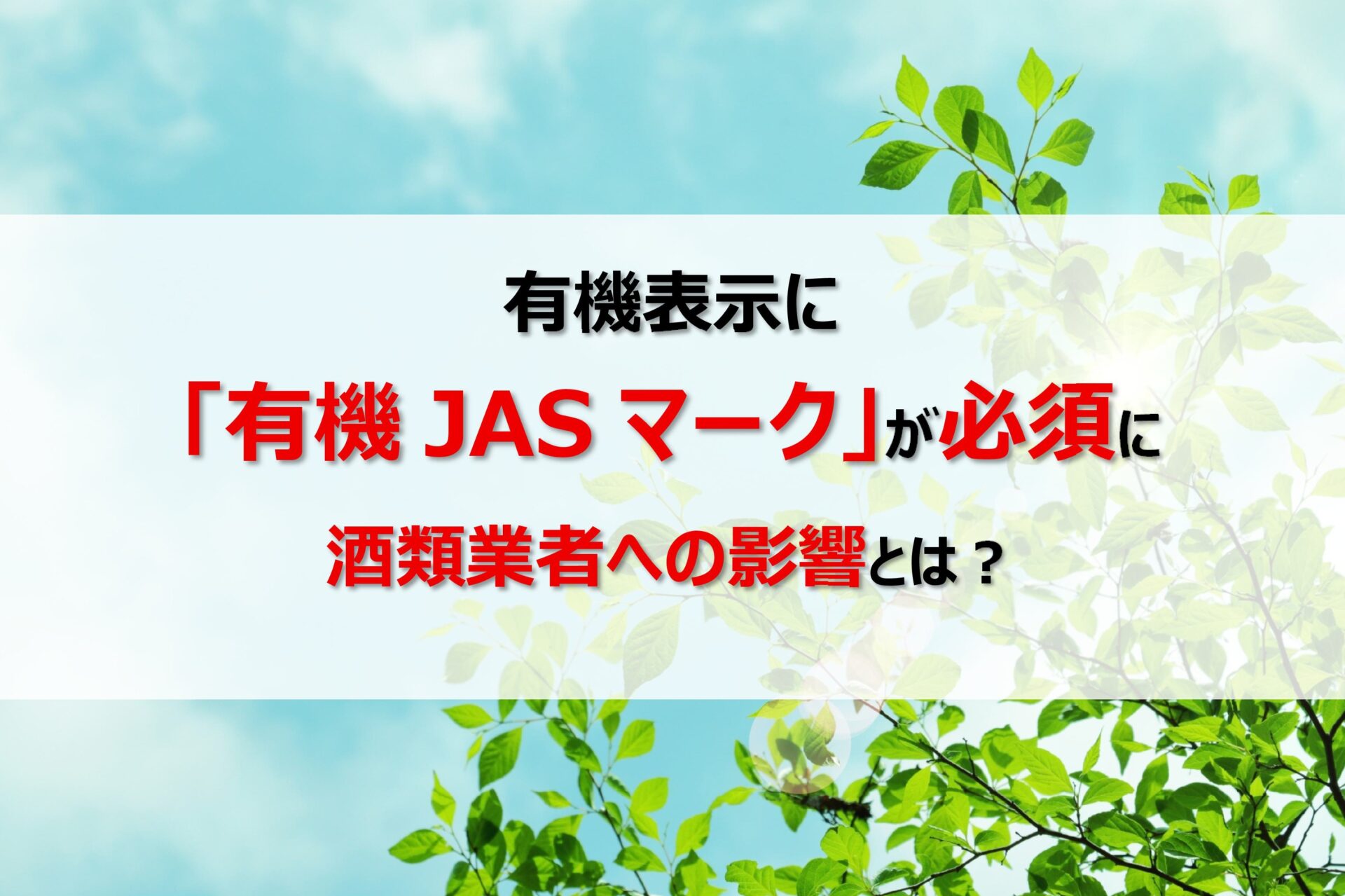お酒の免許申請における「酒類の品目」ってなに?
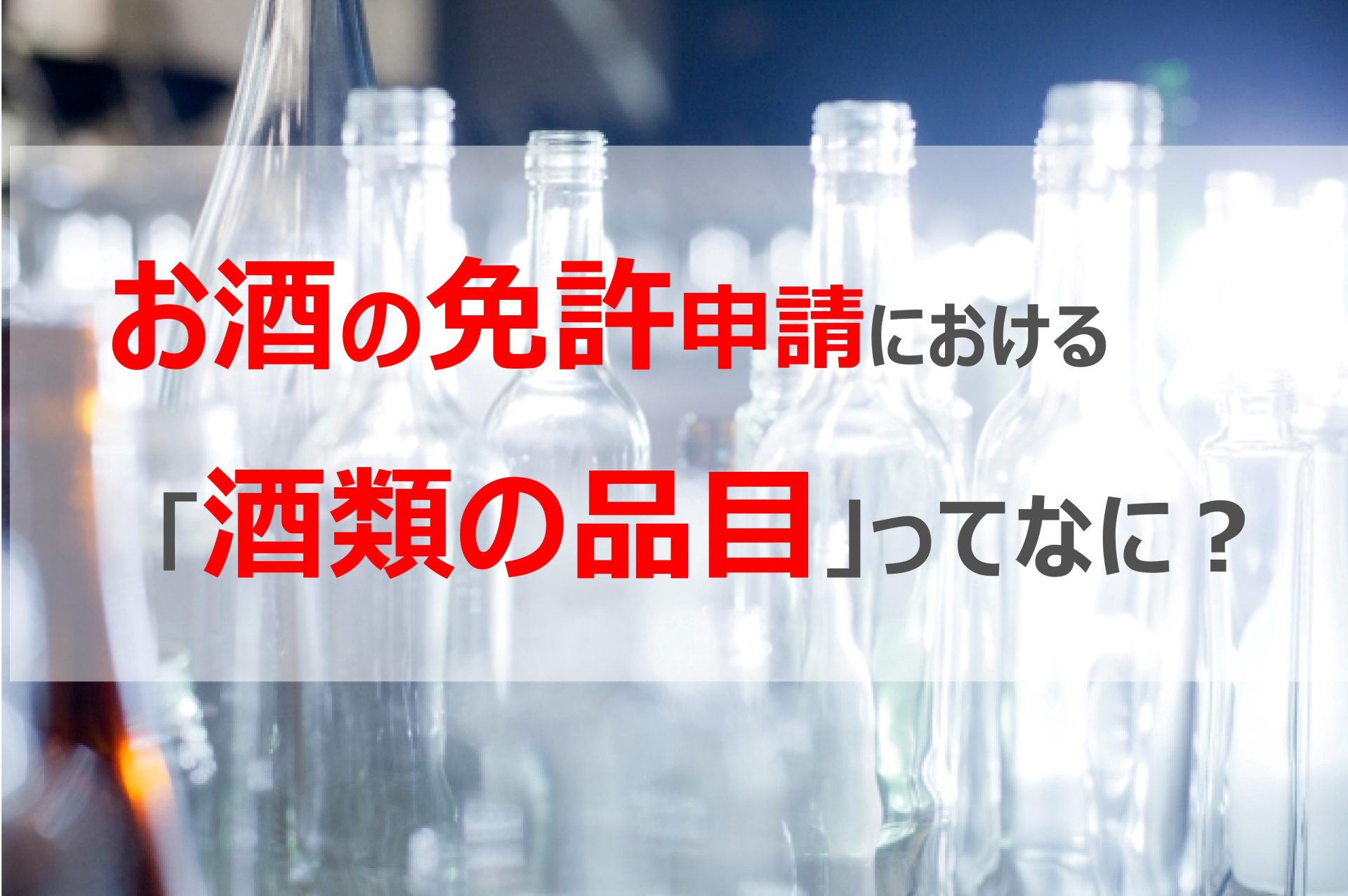
酒類販売業免許を申請する場合は、取り扱う(販売する)予定のお酒の「品目」を決めなければなりません。
普段、酒販店やスーパーで目にするお酒には、たくさんの種類がありますが、一般的には、大きく分類すると、醸造酒、蒸留酒、混成酒の3つに分かれていることはご存知でしょうか? これは、それぞれのお酒の製造方法の違いによる分類となります。
しかし「酒税法」では、酒類を、課税上の必要性から製造方法による分類とは異った分類がなされ、さらに「品目」分けもされています。酒類販売業免許の申請では、「酒税法」上のお酒の分類・品目についても把握しておくことが必要でしょう。
そこで、今回は「酒税法」上のお酒の分類「品目」についてみてみたいと思います。
目次
「酒税法」上の酒類の種類
酒類販売業免許制度を規定する「酒税法」では、製造方法による分類を踏まえたうえで、酒類を大きく次の4つに分類しています(酒税法第2条第1項)。
| 種 類 | |
| 発泡性酒類 | 「ビール」、「発泡酒」に該当するもの、および「その他の発泡性酒類」 |
| 醸造酒類 | 「清酒」、「果実酒」または「その他の醸造酒」に該当するもの |
| 蒸留酒類 | 「連続式蒸留焼酎」、「単式蒸留焼酎」、「ウイスキー」、「ブランデー」、「原料用アルコール」または「スピリッツ」に該当するもの |
| 混成酒類 | 「合成清酒」、「みりん」、「甘味果実酒」、「リキュール」、「粉末酒」または「雑酒」に該当するもの |
酒税法上の種類は、課税上の必要性からの分類で、さらに種類ごとに「品目」を設け、酒類を細かく区分しています。
「酒税法」上の酒類の「品目」
「酒税法」上の酒類の「品目」とは、商品としての特性の違い等に着目した分類と言えるでしょう。
品目は、全部で17区分に分かれています(酒税法第3条第7号から第23号)。
| 品目 | 定義の概要 |
| 清酒 | 米、米麹および水を原料として発行させてこしたもの (アルコール分が22度未満のもの) |
| 合成清酒 | アルコール、焼酎または清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの (アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの) |
| 連続式蒸留焼酎 | アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの (アルコール分が36度未満のもの) |
| 単式蒸留焼酎 | アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの (アルコール分が45度以下のもの) |
| みりん | 米、米麹に焼酎またはアルコールを加えてこしたもの (アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの) |
| ビール | 麦芽、ホップおよび水を原料として発酵させたもの (アルコール分が20度未満のもの) |
| 果実酒 | 果実を原料として発酵させたもの (アルコール分が20度未満のもの) |
| 甘味果実酒 | 果実酒に糖類またはブランデー等を混和したもの |
| ウイスキー | 発芽させた穀類および水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
| ブランデー | 果実もしくは果実および水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの |
| 原料用アルコール | アルコール含有物を蒸留したもの (アルコール分が45度を超えるもの) |
| 発泡酒 | 麦芽または麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの (アルコール分が20度未満のもの) |
| その他の醸造酒 | 穀類、糖類等を原料として発酵させたもの (アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上のもの) |
| スピリッツ | 上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの |
| リキュール | 酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの |
| 粉末酒 | 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの |
| 雑酒 | 上記のいずれにも該当しない酒類 |
17品目に分類される酒類について
酒税法で区分される17品目について、具体的にどのような商品が該当するのかをみてみたいと思います。
| 品目 | 定義の概要 |
| 清酒 | 原料にお米を使い、漉(こ)して透明にした日本酒(アルコール22度未満)。製造方法により、本醸造酒、吟醸酒、純米酒、普通酒などに分類される。 |
| 合成清酒 | 合成清酒とは、アルコールに糖類、有機酸、アミノ酸などを加えて、清酒のような風味にしたアルコール飲料。 |
| 連続式蒸留焼酎 | ホワイトリカーなどの、無色透明で原料の特徴をほとんど感じない焼酎。平成18年(5月)の酒税法改正以前の焼酎甲類。 |
| 単式蒸留焼酎 | 原料の風味が非常に豊かで、味わい深い焼酎。 麦焼酎、米焼酎、芋焼酎、黒糖焼酎、泡盛、蕎麦焼酎など。平成18年(5月)の酒税法改正以前の焼酎乙類。 |
| みりん | 一般的には、本みりんという名称で流通し、芳醇な甘みと豊かな風味があり、飲むことができる。 ※みりん風調味料や発酵調味料といった、類似品の販売は酒販免許が不要。 |
| ビール | 麦芽、ホップ、水を原料とし醸造したもの(麦芽100%)または、麦芽、ホップ、水、および、副原料を用いて醸造したもの(麦芽50%以上)で、いくつかの伝統的なタイプに分類されている。 ペールエール、ヴァイツェン、ケルシュ、アルト、スタウト、ピルスナー、アメリカビール、メルツェン、デュンケル、ボック、ランビックなど。 ※日本の大手ビールメーカーが造るビールは、ピルスナーを基にして醸造されているケースが多い。 |
| 果実酒 | ワイン、スパークリングワイン、シャンパン、フルーツワインなど果実を原料とした醸造酒。 |
| 甘味果実酒 | 果実以外の原材料としてブランデーや香草などを使用したものや糖分を添加して発酵させた醸造酒で、ポート、シェリー、ベルモットなど。 |
| ウイスキー | 発芽させた穀類・水を原料として糖化させ、発酵させたアルコール含有物を蒸留した蒸留酒。スコッチ、アイリッシュ、アメリカン、ジャパニーズ、カナディアンなど。 |
| ブランデー | グレープブランデーとフルーツブランデーがあり、いずれも果実酒を蒸留して造られる。コニャック、アルマニャック、シェリー、グラッパ、カルヴァドスなど。 |
| 原料用アルコール | 主に日本酒(清酒)などの増量、品質調整、アルコール度数の調整などに用いられるアルコール。 |
| 発泡酒 | 麦芽の使用割合が50%未満の、ビールの原料として認められていない原料を使用したもの。 |
| その他の醸造酒 | 穀類、糖類等を原料として発酵させた醸造酒。どぶろく、黄酒(老酒、紹興酒)、ビール類似製品の新ジャンルの一部など。 |
| スピリッツ | 焼酎・ウイスキーに該当しない蒸留酒、または、水でないもの(例:ウーロン茶)で割った飲料。一般的には、ジン、ウォッカ、ラム、テキーラなど ※花酒、アクアビット、コルン、ピンガ、アラック、白酒などもある |
| リキュール | 酒類に糖類や香味成分などを混ぜ合わせたもの。 カンパリやキュラソーなどの西洋リキュール、梅酒・杏酒・薬味酒などの日本リキュール、チューハイなどのソフトアルコール飲料、ビール類似製品の新ジャンルの一部 |
| 粉末酒 | 業務用の大ロットでの販売はされているが、小売販売はされていない |
| 雑酒 | 灰持酒(赤酒、地酒(じしゅ)、地伝酒など)。 |
酒類販売業免許を申請する際には、収支の見込み(兼事業の概要付表)(様式:CC1-5104-1(4) 販売業免許申請書 次葉4)を作成します。販売を予定する酒類の「品目」が、ある程度明確になっていると、収支の見込みも立てやすいのではないでしょうか。
海外のお酒と酒税法
海外のお酒の分類が、日本の酒税法の分類と必ずしも一致するとは限りません。例えば、海外ではビールとして販売されている商品が、日本では酒税法上、含まれる副原料によっては発泡酒に該当する場合があります。マッコリについても、含まれる原料の違いにより、「リキュール」、「その他の醸造酒」、「発泡酒」などに区分されるので注意しましょう。
酒類の販売においては、「品目」による酒税率が異なります。取り扱う商品が、日本の酒税法上のどの「品目」に該当するのかをしっかりと把握し、日本の「酒税法」の規定に基づいて、適正な酒類販売を行いましょう。
まとめ
- 酒類は、酒税法上4種類に分類され、さらに、17品目に区分される。
- 海外の酒類は、日本の酒税法に照らして、「品目」が異なる場合がある。
- 酒類販売業免許申請における「品目」について、疑問の場合は、管轄の税務署または専門の行政書士に問い合わせましょう。
お酒免許ドットコムでは、お酒に関する許認可のご相談を承っております。
初回相談無料・全国対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。